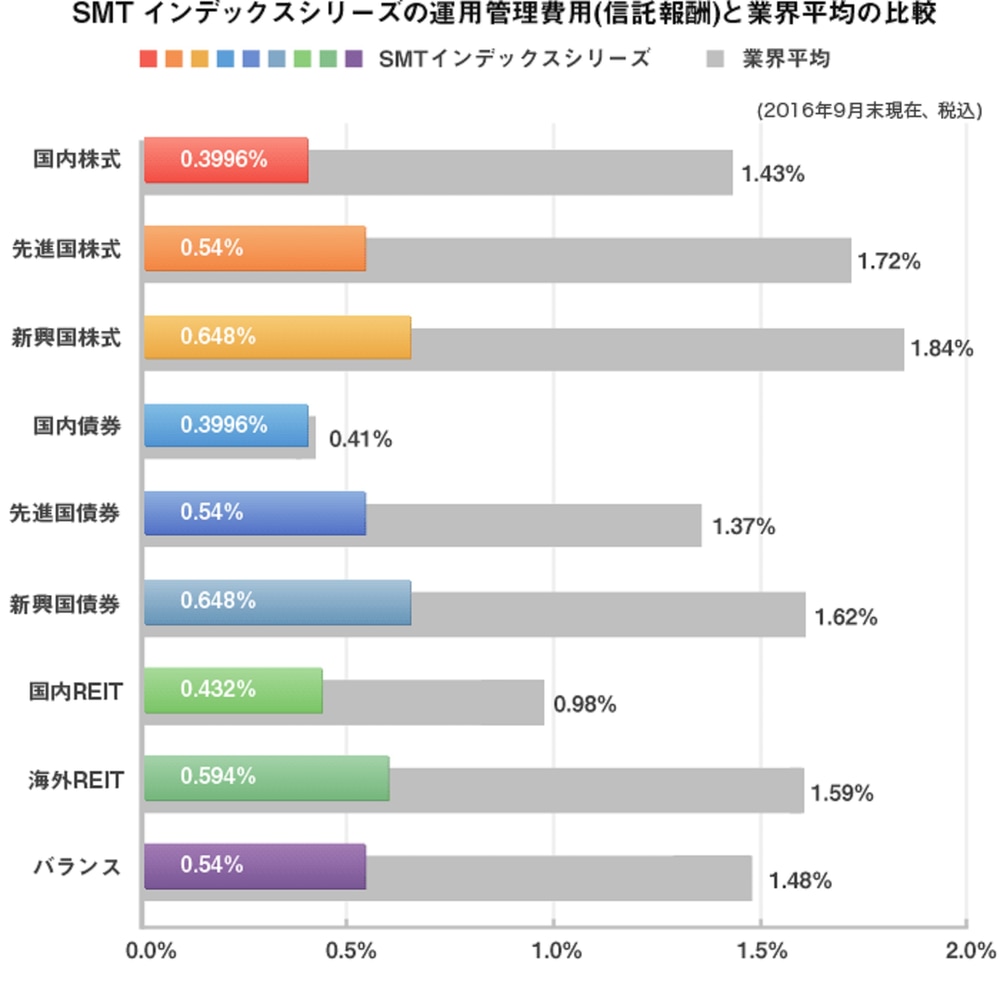父親・故金正日総書記が得意としてきた「瀬戸際外交(作戦)」がもはや通用しないことを息子の金正恩労働党委員長は一刻も早く悟るべきだろう。
朝鮮半島が一触即発状況に陥ったことは今回が初めてではない。しかし、金正日総書記時代と根本的に違うのは米国にトランプ大統領が登場したことだ。正恩氏はトランプ氏の性格を多分十分に理解していないのだろう。「戦略的忍耐」を表明し、北側の度重なる国連決議違反に対しても静観し続けたオバマ前米大統領とは、その出自からそのキャリアまで全く違うのだ。トランプ大統領の米国にはもはや「瀬戸際作戦」は通用しないのだ。
朝鮮半島の政情はここにきて米国と北側の心理戦の様相を帯びてきた。なぜならば、両国とも「もし……するならば絶対に許さない」と表明し、武力行使も辞さない姿勢を見せているからだ。
北側は国営メディアを通じて得意のプロパガンダを駆使し、「相手が望むならば核戦争も辞さない」と宣言。一方、トランプ陣営は「核実験や弾頭ミサイルの発射の兆候が見られれば、即先制攻撃で破壊する」と警告を発しているのだ。両国とも武力行使の用意があることを繰り返し表明している。すなわち、北朝鮮も米国も武器のボタンに手をかけている状況だ。
ところで、北朝鮮と米国双方は本当に武力衝突を考えているのだろうか。北側は世界超大国の米軍と正面衝突した場合、勝算はまったくないことを軍事専門家でなくても分かるはずだ。だから、金正日総書記は瀬戸際外交を展開し、土壇場で米国が手を引くと期待していたのだ。幸い、相手側は土壇場で対話路線に転換させてきた経緯がある。正恩氏も父親と同じように瀬戸際作戦を展開させている、といった気持ちがあるかもしれない。
一方、トランプ氏の場合、対北作戦を展開させる前に2回、派手な軍事活動を指令している。同大統領は7日、地中海の米海軍駆逐艦からシリア中部のアサド軍のシャイラト空軍基地へ巡航ミサイル、トマホークを撃ち込む指令を出し、13日には、アフガニスタン東部のナンガルハル州のイスラム過激派テロ組織『イスラム国』(IS)の拠点に非核兵器では最高火力を持つ「MOAB」(GBU-43)を初めて投下させている。
トランプ氏の軍事デモンストレーションに対抗し、正恩氏は16日午前、弾道ミサイル1発の発射を命令したが、ミサイルはどうやら発射直後、爆発した。この段階でトランプ氏と正恩氏の脅迫作戦の勝負ははっきりしたのだ。米軍は北が弾道ミサイルを発射しようすれば、北のミサイル機能をマヒさせる電子攻撃を仕掛け、落下させるからだ。
北は昨年10月段階で計8度、中距離弾道ミサイル「ムスダン」(射程3500キロ)を発射し、成功は同年6月22日の1回だけだった。グアム米軍基地まで射程に収める弾道ミサイルの開発という平壌の宣伝文句が空しくなるほどの結果だったのだ。
弾道ミサイルを開発し、核搭載ミサイルで米本土を攻撃すると豪語した金正恩労働党委員長に対し、米国は電子戦を展開させ、軍事力の差を示したわけだ。今回のミサイル発射失敗も同じ理由が考えられるのだ(「米軍の電子戦で『ムスダン』は不能?」2016年10月21日参考)。
ちなみに、米軍は80機の戦闘機を運ぶ米原子力空母カール・ビンソンを朝鮮半島近海に派遣する一方、トマホーク巡航ミサイルを発射できる駆逐艦2隻のうち1隻は現在、朝鮮半島から約480キロ離れたところで待機中だ。
正恩氏は面子を大きく失わない段階で挑発を中止すべきだ。さもなければ、トランプ氏は米海軍特殊部隊を動員させ、奇襲攻撃に出ざるを得なくなるのだ。なぜならば、「もし、……ならば」と繰り返し表明してきた立場上、トランプ氏は一旦手をつけた刀(武器)を容易に鞘に納めることはできないのだ。
トランプ氏と中国の習近平国家主席の間で対北政策で一定の合意が達成された兆候が見られる。米財務省は14日、中国を「為替操作国」に認定することを見送る一方、中国国際航空は17日から北京と北朝鮮の首都・平壌を結ぶ便の運航を停止するとともに、中国旅行社は北観光を全面中止するなど、人的交流の制限に乗り出してきているのだ。金正恩氏を取り巻く情勢は限りなく北に不利だ。
正恩氏もトランプ氏も世代は異なり、国は違うが、面子を重視する点で似ている。その上、両者とも「計算できない、予想外の言動をする人物」と受け取られていることだ。換言すれば、朝鮮半島の危機とは、武力衝突の危機というより、「計算できない、予想外の言動に走る」2人の指導者の“次の一手”が読めない危険性を意味しているわけだ。データ主義が席巻する21世紀の国際社会では、次の一手が予想できないというほど怖いことはないのだ。世界は今、この恐怖と対峙しているのだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年4月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。