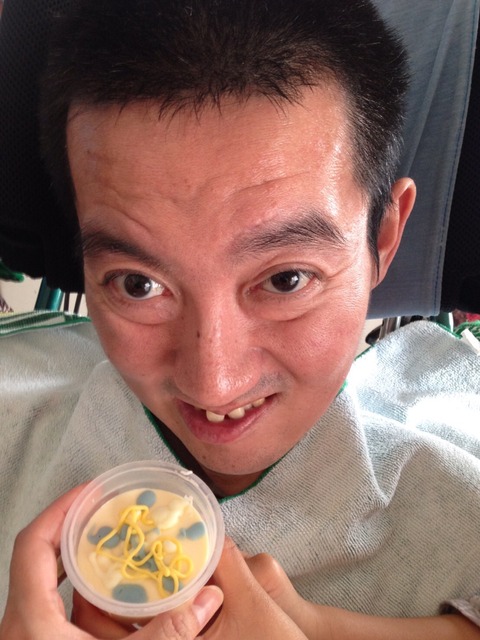つくられたイメージ
欧米列強は18世紀以降、本格的に海外を植民地化した。植民地化によって、現地人を搾取して、利益を収奪したという一般的なイメージがあるが、植民地経営はそれほど簡単なものではなかったし、収奪する程の利益など、植民地にはほとんどなかった。
海外を植民地化することは莫大な初期投資がかかり、費用対効果という観点からは、とても受け入れられるようなものではない。常時、軍隊を駐屯させる費用、行政府の設置・運用とその人件費、各種インフラの整備、駐在員の医療ケアなど、莫大な費用がかかる。その行政的手続きも極めて煩雑になってくる。
初期コストや投資金を無事に回収し、安定的に利益が出せるかどうかの保証などもない。植民地ビジネスはリスクが大きく、割に合わないのだ。「植民地=収奪」という根拠のない「つくられたイメージ」を一度、捨てるべきだ。
教科書や概説書では、植民地経営の成功例ばかりが書かれている。例えば、オランダはインドネシアを支配し、藍やコーヒー、サトウキビなどの商品作物を現地のジャワの住民に作らせ(強制栽培制度)、大きな利益を上げていたというようなことだ。しかし、このような成功例はごく一部であって、ほとんどの場合、投資金を回収できず、損失が拡大するばかりであった。実際、19世紀、ヨーロッパのアフリカの植民地経営などはほとんど利益が上がらなかった。
文明化への使命
では、なぜ、欧米は大きなリスクをとりながらも、植民地化に取り組んだのか。それは経済的な動機というよりも、思想的な動機が強くあったからだ。

セシル・ローズ(Wikipedia)
近代ヨーロッパでは、啓蒙思想が普及した。啓蒙とは「蒙を啓く」つまり無知蒙昧な野蛮状態から救い出す、という意味である。啓蒙は英語でEnlightenment、光を照らす、野蛮の闇に光を照らす、という訳になる。啓蒙思想に基づき、西洋文明を未開の野蛮な地域に導入し、文明化することこそ、ヨーロッパ人の使命とする考えがあった。
イギリスのセシル・ローズ(Cecil John Rhodes、1853年~1902年、は南アフリカのケープ植民地首相)などはこうした考え方を持っていた典型的な人物であった。
ローズは、アングロ・サクソン民族こそが最も優れた人種であり、アングロ・サクソンによって、世界が支配されることが人類の幸福に繋がると考えていた。
開明化された地域が資本主義市場の一部に組み込まれれば、利益をもたらすという狙いも最終的にはあったかもしれないが、「文明化への使命」という考え方が割に合わない植民地経営のリスク負担を補っていた。
当時のヨーロッパ人というものは、我々が考える以上に非合理的であり、昔ながらの精神主義に拘泥していたと言ってよい。
村山談話

村山元首相と河野元外相(日本記者クラブより引用)
実は、日本の植民地政策にも、このような啓蒙思想を背景とする思想的動機が強くあった。韓国や台湾を植民地化して、当時の日本に利益など全くなかった。元々、極貧状態であった現地に、日本は道路・鉄道・学校・病院・下水道などを建設し、支出が超過するばかりだった。それでも、日本はインフラを整備し、現地を近代化させることを使命と感じていた。
特に、プサンやソウルでは、衛生状態が劣悪で、様々な感染症が蔓延していたため、日本の統治行政は病院の建設など、医療体制の整備に最も力を入れたのだ。
日本人はヨーロッパ流の啓蒙思想をいち早く取り入れ、近代化に成功し、それを精神の前提として、植民地政策を展開した。何の儲けにもならないことのために。
1995年、当時の首相村山富市が発表した「戦後50周年の終戦記念日にあたって」と題された談話(いわゆる「村山談話」)には、以下のような下りがある。
植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。
このような文言は「植民地=収奪」という「つくられたイメージ」を前提にしていると言わざるを得ない。植民地支配によって、我が国は「多大の損害と苦痛」を「与えた」のではなく、「被った」のである。
宇山 卓栄(うやま たくえい)
著作家。1975年、大阪生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。大手予備校にて世界史の講師をつとめ、現在は著作家として活動。『世界史は99%、経済でつくられる』(扶桑社)、『民族で読み解く世界史』(日本実業出版社)などの著書がある。