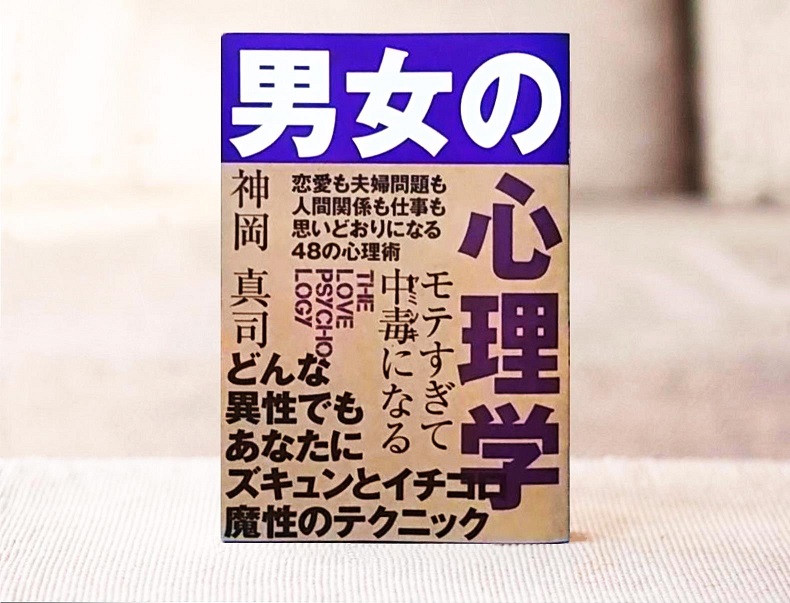アメリカでリバタリアンと呼ばれる人達の多くは、極めて小さな政府と金本位制への復帰を主張している。その根底にあるのは政府と中央銀行への不信である。これに対して主流派のエコノミストやウォール街の人々は、金本位制は金融政策の自由を束縛し、インフレやデフレの抑制、さらには景気対策も打てなくなるといって頭から相手にしない。
しかしそれでは、これまで金融政策はそんなに良いことをしてきたのだろうか?金融政策のせいでブラックマンデー、アジア通貨危機、ITバブル、サブプライム問題が生じたのではないか?
とりわけサブプライム問題は世界の金融システムを崩壊の淵に立たせたほど規模が大きくひどいものであった。これに対して当時の連邦準備制度理事会のバーナンキ議長はQEと呼ぶ超金融緩和策をとって、いわばお金の蛇口を全開にして銀行を救済し、金融システムの崩壊を回避した。
しかし、その副作用は大きく、商品価格の上昇に起因したアラブの春や世界中の株と不動産の異常な値上がり、そしてアメリカの家計の債務バブルの膨張など、今なお問題は解決するどころか、不気味に拡大し続けている。
いずれ何かのきっかけで、こうしたバブルの大崩壊が起こるであろうが、経済学者たちは、これだけ金融政策の副作用を目にしても反省しないのだろうか?
政治家が反省しないのは分かる。株価が上り、為替レートが下がることは、目先資産家や企業の支持を得ることとなる。日本でも経済界に限らず、人手不足で就活生はかりそめの好景気の恩恵を享受している。国民が現状をよしとしているのだから、これに反対の政策は政治的には取り得ない。
そしてクラッシュが来た時、国民の悲鳴に応えるために各国の中央銀行は、出口に向かおうとしている金融政策を180度反転させて、低い金利を更に下げられるだけ下げ、既に大量に買っている国債等を腹いっぱいになるまで購入するだろう。一方、各国政府は国債を大量発行して大規模な財政出動をするに違いない。その結果、政府・中央銀行の信用はガタ落ちとなる。これは言い換えれば、国債やその国の通貨の価値がとめどなく下がる(インフレになる)ということである。
これが10年前だったら、ストーリーはここで一段落して、後は国民が不況とインフレの中で悲惨な思いをするだけであった。しかし、今は違う。
リーマンショックとそれを引き起こした金融当局に反旗を翻す形で2009年にビットコインが生まれた。そして紆余曲折はあるが、仮想通貨は徐々にその存在感を増してきている。これからは、国民は一方的にバブルのツケを払わされるのではなく、仮想通貨を手にすることで自分たちの資産保全をすることが可能になり、また、モノやサービスの売買を紙切れ同然となったその国の通貨ではなく、仮想通貨で取引するようになるかもしれない。これはまさに、中央銀行が国民に見放される状況に他ならない。
旧聞になるが、2010年に当時の世界銀行総裁のゼーリック氏が超金融緩和策をとる(主としてアメリカの)政府・中央銀行に対して、法定通貨の信認の維持に努める必要があると警鐘を鳴らした。また、最近のIMFのレポートでも、仮想通貨が広く使われ、法定通貨が使われなくなったら金融政策の効力が低下するため、各国中央銀行は国民の法定通貨に対する信頼をつなぎとめることが必要と言っている。
仮想通貨の発展とともに中央銀行が通貨価値を自在に操ることができた時代は過ぎ去ろうとしている。

岡山県倉敷市出身。東京大学法学部を経て1975年大蔵省(現、財務省)入省。その後、官費留学生としてフランス国立行政学院(ENA)留学。財務省大臣官房審議官、世界銀行グループの国際金融公社東京駐在特別代表などを歴任し、2008年退官。 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社専務取締役、株式会社日本決済情報センター代表取締役社長を経て、2018年6月より同社顧問。著書に「フランス人の流儀」(大修館)(共著)。