自分の死に関しての恐怖は、
小林武彦(著)「生物はなぜ死ぬのか - 死生観が一変する現代人のための生物学入門!遺伝子に組み込まれた「死のプログラム」とは?」
で、相当和らげていただきました。その書評動画は、
【研究者の書評-19】小林武彦(著)「生物はなぜ死ぬのか」さだまさし・YUIも登場!? 日々の「生」を楽しみたいという希望が生まれる良書
に紹介していますが、今回は、自分の死ではなく、親の死に関しての自分の気持ちに関するものです。
7月中旬から8月中旬までの5週間、日本に一時帰国している間に、約2年10ヶ月ぶりに北九州の若松の実家を訪ねていました。
僕の両親は戦前生まれで82歳の父は、コロナ前までは車も運転して、すごく元気だったのですが、コロナ中に倒れて今は「介護2認定」を受けています。
父方の祖父は76歳でその生涯を閉じたので、父親が倒れた時は、コロナで帰国もできずにヤキモキして、父親も死んでしまうのではないかと、寝付けない日々が続いていたのです。
小倉にある大きな病院と、地元若松の病院でリハビリを続けた父は、記憶があまり続いていないし、視力がほぼ無くなってしまっているけど、家での生活はなんとかできているので、今回の帰国で再開してほっとしているところです。父親にはまだ少なく5−6−6年、できれば10年ぐらいは生き続けて欲しいと心から願っているところです。
そんなタイミングでの、今回の本。
は、あの「国道16号線」で一世を風靡(?)した、東工大の教授、柳瀬博一さんの父親を看取った時のエピソードが綴られた暖かいエッセーです。
この本を読むまでは、あの納棺師の映画「おくりびと」のようなことは映画の中だけで、実際のお葬式では、葬儀屋さんが葬儀をして、遺族はただ傍観(?)するものだと思っていました。
「この世界の片隅で」という映画の主人公「すずさん」に似た納棺師の方の指導の元、なんと柳瀬さんと弟さんは、納棺を自分で体験することになります。
それまでは、父親の死を少し距離を置いた感じでいた柳瀬さんは、父親の衣服の着替えで、体に触ることで、父親との心の距離を一気に縮めていきます。
死者を弔うことは、すなわち自分の心の中のケアであること。納棺を通じて体験してその心のケアをしていく様は、そう遠くない将来、自分にも訪れる父親の死に対して、僕の心が随分軽くなったと、著者の柳瀬さんに感謝しているところです。
今回の帰国では、両親と写った僕の幼児期の写真を沢山スキャンしてきました。僕は18歳で家を出ていますが、親の有り難みがこの歳になってどんどん強くなってきていることを実感しています。「孝行したいときに親はなし」ということで、これからはなんとか自分で出来る限りの親孝行をしたいと思っています。
でも、親は、三国志の劉備元徳の母親のように、自分たちへの孝行をするよりは、社会に貢献する僕を望んでいるようなので、親孝行はすなわち研究と教育で僕が社会に貢献することだと思っています。
■
動画のノギタ教授は、豪州クイーンズランド大学・機械鉱山工学部内の日本スペリア電子材料製造研究センター(NS CMEM)で教授・センター長を務めています。





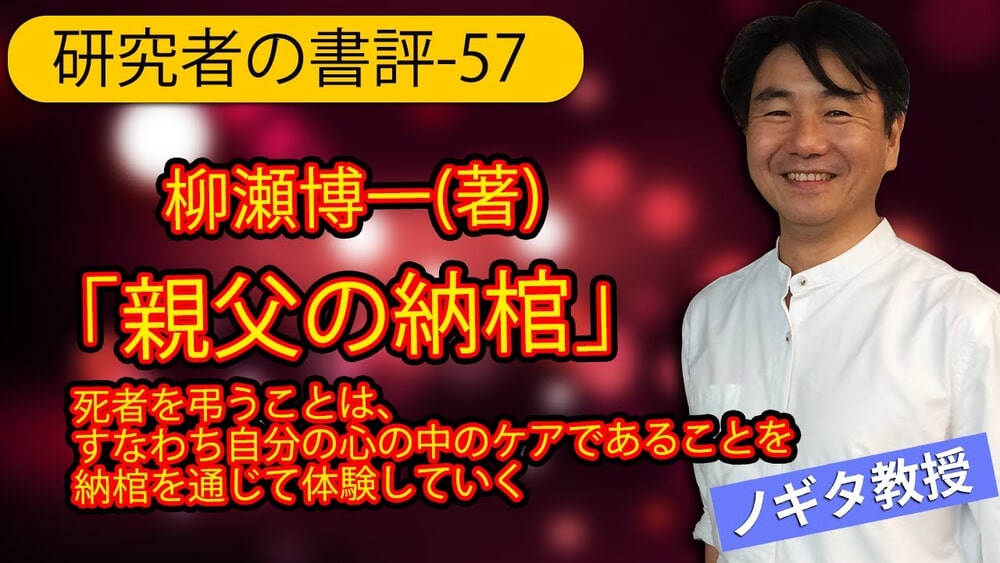
![[柳瀬博一, 日暮えむ]の親父の納棺 (幻冬舎単行本)](https://m.media-amazon.com/images/W/IMAGERENDERING_521856-T2/images/I/514Bn8D-H9L.jpg)








