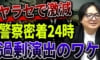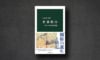異次元緩和批判本が続々と
安倍政権下で日銀総裁を務め、異次元金融緩和策(アベノミクス)を10年も続けた黒田東彦氏は、いつまで沈黙を守り続けるつもりでしょうか。異次元緩和・財政膨張策への検証、批判が噴出しています。前任の白川方明総裁は分厚い回顧録を残しました。黒田氏には証言する責務があると思います。

黒田前総裁 日本銀行HPより
日銀は異次元金融緩和を含む過去25年間の金融政策の検証(多角的レビュー)を昨年末に発表し、10年という長期化の代償が極めて大きいと、批判的に総括しました。
さらに2014年後半の金融政策決定会合の議事録が先月末に公表され、同年10月の追加緩和(国債買い入れ拡大、ETF=上場投信の購入など)は「反対意見が多く、5対4の薄氷の決定だった」ことが明らかにされました。そんな際どい票差と知り驚きました。
「多角的レビュー」では「マネーと物価の間には、単純な貨幣数量説がするような関係はみられなかった」旨の記述がされ、黒田氏の持論である「マネーを増やせば物価が上がる」との主張を否定しています。安倍政権寄りだったリフレ派(金融財政膨張派)へのけん制を意図しているようです。
異次元金融緩和策は、当初から「無謀な実験」「大胆すぎる冒険」との指摘が聞かれ、もしこの会合で方向転換をしていれば、1年半で「実験」は終わり、泥沼に足を踏み入れたような金融、財政の危機的な状況には至らなかったと思います。安倍政権には怒涛の勢いがあり、政治的な圧力が金融政策の正論を沈黙させてしまったのでしょう。植田・新総裁による方向転換では遅きに失し、正常化には途方もない時間を要する。
日銀出身のエコノミストらからも、異次元緩和策批判の出版が相次いでいます。「異次元緩和の罪と罰」(講談社新書、山本謙三=元理事)、「日本銀行/わが国に迫る危機」(同、河村小百合=元日銀職員)、「持続不可能な財政」(同、河村小百合・藤井亮二)などです。
さらに「日銀の限界」(幻冬舎新書、野口悠紀雄=元大蔵省)、「日本の経済政策」(中公新書、小林慶一郎=元通産省)など、他省OBの批判論も少なくありません。野口氏は「2%という物価目標は廃棄すべきだ。円安によるインフレの輸入で国民は苦しんでいる。円安是正が物価対策だ」とまで主張しています。
日銀の次期審議員に小枝淳子・早大教授が選出される予定で、これで政策決定委員会(正副総裁3人、審議委員6人)はリフレ派(金融緩和、財政拡大派)1人となり、正副総裁を含め、金融正常化を考える委員が多数派となります。ただし、日銀が500兆円もの国債を保有し、国債発行残高がGDP比で250%以上という財政金融状態を正常化するには、「途方もない年数がかかる」が常識になっています。
2014年当時の審議委員だった木内登英氏は「異次元緩和から折り返す最後のチャンスだった。金融拡大は誤りだった」(日経1月30日)と指摘しています。白井さゆり氏は「2年で物価上昇率2%をという目標はどう考えても無理な情勢になっていた。ただし、新たなアクションをとらなければ、日銀が約束をほごにしたと思われる。だから追加緩和に賛成した」(同)と、苦し紛れの弁明をしています。
白井氏あたりが追加反対をしていれば、日本の金融財政がこんなにひどい状態にならずに済んだのです。今頃になって白井氏に「副作用の大きさからすると、出口がいかに困難かを示唆している」と言われても無責任です。せめて「政治的な勢いに負け、私の判断は間違っていた」というべきでしょう。
黒田総裁は「好転している期待形成モメンタム(勢い)を維持すべきだと」と発言したと、議事録にはあります。黒田氏は自らが率いた異次元金融緩和を今、どう考えているか証言すべきです。黒田氏から発言がほとんど聞かれないと思っていましたら、読売新聞の連載「円転変/プラザ合意40年」という連載の第2回(1月7日)に登場しているのを見つけました。
「プラザ合意40年」に関する連載ということもあって、異次元緩和に関する黒田氏の発言は全体の半分程度です。現在は政策研究大学院特任教授です。要旨は以下の通りです。
- 物価上昇率2%目標は未達が続いた。長らく続いたデフレで物価や賃金は上がらなという「ソーシャル・ノルム(社会通念)が根付いた影響のせいだ。
- ウクライナ戦争(22年2月~)で原油、農産物などの一次産品の暴騰と円安進行によって輸入物価が急上昇し、物価上昇率は3%を超えた。
- 行き過ぎはマイナスだが、日本経済にとって円高より円安がプラスと思っている。企業は円建て輸出価格を引き上げて企業収益を増やし、海外子会社の収益を現地通貨(ドル)から円に換算することで利益が拡大する。企業は増えた利益を賃上げで還元したり、設備投資をするとよい。
これらの指摘に納得できない人は多いでしょう。
- 異次元金融緩和という大胆な政策をとれば、社会通念が変わり、物価が上がり始めると、黒田氏は就任当初に発言してではないか。
- 国内の通貨供給量を増やせば、物価が上がる(貨幣数量説)を当初、唱えていました。物価上昇が始まったのはウクライナ戦争、一次産品の値上がり、円安という外的要因でした。国内だけをみていた異次元緩和策は大筋で効かなかったと、黒田氏は認めることになります。
- 円高より円安がプラスということも就任時には語っていません。異次元金融緩和は円安を意図していないと、日銀は弁明していました。つまり「意図していない円安=インフレ輸入」が物価を押し上げていたわけで、「通貨供給量2倍、物価上昇率2%、2年」は目標と手段の設定が間違っていたことになります。
さらに「賃金があがれば、企業は価格に転嫁するから物価が上がる。賃上げしても物価上昇で実質賃金が目減りする。望ましい賃上げは、企業の生産性の向上の結果であることだ。現在はコスト・プッシュ型の物価上昇になっている。日本として取り組むべきは実体経済をよくすることだ」と、野口悠紀雄氏が主張し、政府、日銀が指摘する「物価と賃金上昇の好循環」の間違いを指摘しています。
異次元金融緩和・財政膨張策(日銀による事実上の財政ファイナンス)は、その規模、期間からして金融史に残る前例のない出来事で、「効果は少なく、代償が大きく、正常化に途方もない年数を要する」という評価になると思います。黒田氏による本格的な弁明を期待します。
編集部より:このブログは「新聞記者OBが書くニュース物語 中村仁のブログ」2025年2月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、中村氏のブログをご覧ください。