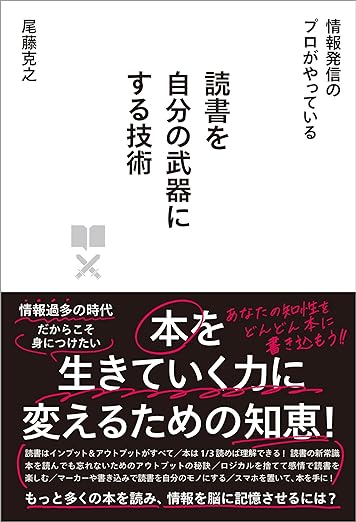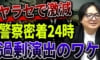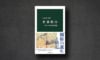EyeEm Mobile GmbH/iStock
母が亡くなった。まだ心の整理がつかない。人生において、これほど悲しい出来事は初めてで、後悔の念にさいなまれている。ぜひ、前の記事もお読みいただきたい。
医師の言葉が奪った希望:医師の倫理とは何か?がん告知の在り方を問う

余命宣告は慎重になるべきである
筆者には医師の知人が多い。その多くは著者仲間であるが、話をするたびに医師は聖人ではないことや、悪い医師も存在する現実を理解できる。多くの医師は献身的に患者の命を守り、素晴らしいケアを提供している。しかし、一部の医師は自己利益や名声を優先することがある。
不適切な診断や治療ミスによって患者に甚大な被害をもたらすケースも少なくない。また、コミュニケーション不足や医療過誤の隠蔽など、倫理的に問題のある行動をとる医師も存在する。
医師が余命宣告を行うことは義務ではない。患者にとって非常にデリケートな問題である。余命を知ることで精神的な負担が増大し、残された時間の質が低下する可能性があるためだ。大きなショックが予想されるため、本人の精神状態や希望を熟慮した上で判断する必要がある。
筆者の家族では次のような告知がなされた。この医師の告知内容をさらに詳細にお伝えしたい。
医師:CTなどの結果は未だですが私くらいになると確定させることができます。間違いなく死にます。助かりません。1カ月もたないと思います。(ビシッ!)
母は卒倒し椅子から崩れ落ちる。私たち家族も言葉を失う。
父:もたないとはどういう意味ですか。圧迫骨折ではないのですか?
医師:膵臓を原発巣とした「がん」です。肝転移も見られるためステージ4です。間違いなく1カ月もちません。絶対に死にます!!いますぐに入院しましょう!(満面の笑顔)
私は医師の告知に強い違和感を覚えていた。家族や患者の同意もなしに、「死ぬ」「助からない」「膵がんステージ4」を連呼したからである。
即座に「告知義務違反」だと考えたが、この場で声を荒げても得策ではない。医師と看護師の対応を静観していた。一方、数週間前に受診した整形外科の誤診も疑っていた。
医師の無配慮が患者と家族を苦しめる
余命宣告は鉄砲みたいなものだ。発射すれば無防備な患者と家族にどれほどの痛みを与えるかわからないはずはない。多くの医師は、患者やその家族に対して配慮しつつ、できるだけ丁寧に、誠実にメッセージを伝えようとしているはずである。
この医師は、余命宣告を楽しんでいるようにさえ見えた。満面の笑みを浮かべながら、有無を言わさずに入院手続きを進めたからである。日頃の仕事のうっ憤やストレスの発散に、患者を利用しているのではないかと疑いたくなるほどだった。
この医師は自分の親にも同じことが言えるのだろうか?
「ステージ4のガンで助からない。1カ月もたない、間違いなく死ぬ!」
と言えるのだろうか。
膵がんは進行が早い。ベストな治療を選択しても死は避けられなかったかも知れない。しかし、大きな精神的ショックを与えなければ、ここまで短時間で死に至ることはなかっただろう。
生まれたからには、誰もがいつかは必ず死を迎える。医師に求められるのは、患者がその日までどのように生きるか、そしてそれをどのように支援するかを考えることではないのか。死を避けられないなら、残された時間をどう過ごすかを考えて欲しかったが、この医師にはその意識が欠落していた。
生きる気力を失った母は急速に衰弱し、「もう死ぬのだから殺してくれ」「痛いのは嫌だから安楽死をさせてくれ」が口癖になった。母も苦しかっただろう。しかし、残された家族にとっても耐え難い日々が待っていた。
医師に問われる倫理観
当初は、民事訴訟はもとより、医師会への懲戒請求、病院の倫理委員会への告発など、あらゆる手段を考えていた。しかし、葬儀が終わり、一旦は矛に収めるつもりだった。争っても母は喜ばないからである。しかし、美容外科医が検体画像を投稿した非常識な報道を目にしたことで、医師の倫理観について問いたくなった。
医師の一言が、取り返しのつかない影響を患者と家族に与えることを、真摯に考えるべきである。医師の氏名等の公表は現時点では控えるが、いずれ事態が進展した段階ですべてを明らかにしたい。そして、医師の倫理観について、世論の判断を仰ぎたいと考えている。
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
2年振りに22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)