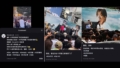今年の「新語・流行語大賞」に高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が選ばれたという。「働いて」が5回も続くと、国民は「俺たちは十分働いていないのか」といった後ろめたさを感じるかもしれない。ただ、当方は日本からの今年の「新語・流行語大賞」の発表を聞く直前、「地球の自転が加速してきた」というニュースを読んだばかりだったこともあって、高市首相は一日が短くなることをご存知の上であの「働いて」という言葉が飛び出したのではないか、と深堀したほどだ。
地球の一日は24時間、86400秒と受け取られているが、地球はいつも同じ速度で自転しているわけではない。2020年以降、地球は24時間を超える速度で自転してきていることが明らかになった。ミュンヘン工科大学の地球物理学者ローランド・ペール氏は「やや意外だ」と述べている。あらゆるデータや兆候がこれまで減速を示していたからだ。地球の自転が更に加速すれば、一日はもはや24時間ではなく、短くなる。これこそ、日本の国民経済に責任を持つ高市首相が思わず「働いて」と5回も叫ばなければならなくなった本当の理由だったのかもしれない。

地球、NASA提供
オーストリア国営放送(ORF)のウェブサイト科学欄で1日、「地球の自転が早くなっている」という興味深いテーマの記事が掲載されていた。
地質学者によると、14億年前、地球の自転はわずか18時間だった。その原因は月にある。例えば、月は現在、地球から年間3.82センチメートルの速度で遠ざかっている。
月は地球のハンドブレーキのような役割を果たしてきた。二つの質量の相互引力に関連する。例えば、サンゴ礁や堆積物のデータは、5億年から6億年前は1日の長さがまだ21時間だったことを示しているというのだ。地球はその時、今よりはるかに速く自転していたことになる。
ただし、ペール氏によると、「月のハンドブレーキ」はそれ以来、地球の自転を遅くしてきた。地球の自転速度低下の主な原因は、月が地球から徐々に遠ざかるからだといわれてきた。地球物理学者は「月が遠ざかると、地球はピルエット中に腕を伸ばすためにスピードを落とすアイススケーターのような動きをする」というわけだ。
ところが、理論や予測に反して、地球はここにきて減速するどころか、加速しているというのだ。ペール氏によると、ウィーン工科大学などの測定結果がそれを示しているという。地球深部で微妙な動きが起きているのではないか、というわけだ。
ペール氏は「地球のマントルと核は現在、同じ速度で回転していない」と考えている。この現象は原理的には知られているが、研究やモデル化は困難だと言う。
ただし、地球の自転の速度が速くなったとしても、地球上に生きている我々にはもちろんその変化を体感できない。日常生活では実質的な変化はない。地球の自転速度の変動は、地球の歴史を通して繰り返し発生してきている。例えば、2024年7月5日には観測史上最短の1日となったが、その差はわずか1.66ミリ秒だった(ミリ秒とは1000分の1秒)。
しかし、世界標準時などを決定する精密な原子時計は、昼の短さを確かに検知している。かつては昼の長さが86,400秒よりも長かったため、1970年代以降、定期的に閏秒が時刻に追加されてきた。地球の自転による天文学的な時間(世界時)と、原子時計で定められた正確な時間(国際原子時)とのずれを調整するためだ。
太陽系では、重力条件の小さな変化が長期的に蓄積され、大きな影響を及ぼす。これは、カオス理論でよく知られているバタフライ効果に似ているという。「バタフライ効果とは、力学系の初期状態のわずかな変化が、時間とともに予測不能なほど大きな結果をもたらす現象」を指す。だから、地球の自転の加速現象を無視できないわけだ。
最後に、地球の自転が早まった場合について、人工知能(AI)にまとめてもらった。
「地球の自転が早まると、1日の長さが短くなるほか、気象が荒れたり、GPSや通信システムに影響が出たりする。わずかな変化でも蓄積されると、特にコンピューターの正確な時刻管理に支障をきたす可能性がある」。
参考までに、商品の価値はその商品を生産するのに投下された労働の量(労働時間)によって決まる、という「労働価値説」(マルクス主義経済)があるが、資本主義経済には当てはまらない。「働いて働いて・・」労働時間を増やしたとしても国民経済が復興する保証はない。もちろん、高市首相はご存知だろう。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2025年12月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。