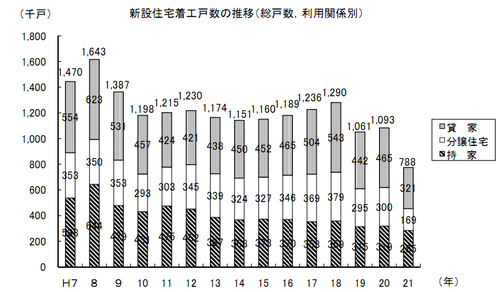さて、年が明けても電子書籍関連の話題は各ニュースサイトに挙がっている。CES(International Consumer Electronics Show)でも数多くのタブレットや電子書籍端末が披露されたらしい。国内でも新たなサービスが立ち上がっている。しかし、これらはすべて“紙書籍の電子化販売”という色合いが強い。昨年巻き起こったほとんどすべての電子書籍に関する話題はこれだ。
そう考えると、昨年は、実は“電子書籍元年”ではなく“新刊書籍の電子化元年”だと言えるだろう。もちろん10年以上前から紙書籍は電子化されてきたわけだが、新刊を電子化したのは昨年が初めてだったのではなかろうか。その他、いろいろな端末が発表・発売されてきたが、コンテンツ自体は紙書籍の電子化でしかない。
端末も、キンドルはネットへのアクセス可能ではあるが紙書籍の電子版用端末だし、ソニーのReader国内版に至ってはネットへのアクセスもなく、閲覧特化型である。他方、iPadやシャープのGALAPAGOSは、動画なども再生できる端末である。
コンテンツが紙の書籍の電子化だけであれば、それら端末の利点を活かしきっていない。であれば、今年は、それらリッチコンテンツ再生型電子書籍端末の利点を活かしたメディアがますます登場してくるだろう。というのも、紙書籍の電子版では1冊あたりの利益も薄く、規模を追求しないとビジネスになりにくいのだ。
その点“リッチコンテンツ書籍”とも言えるものであれば、付加価値を付けさえすれば、それなりの値段をつけることができる。いままで見たこともない商品であれば、売り手主導で値段を決定できる。質はともかく情報商材などは良い例だ。平均価格が13000円というから恐れ入る。
であれば、書籍と情報商材のあいだの価格で売れる“リッチコンテンツ書籍”というものも考えられるだろう。そうすれば電子書籍専門出版社は、新しいビジネスモデルを創造し、永続的に価値あるコンテンツを生み出していくことができる。リッチコンテンツであれば制作コストが高くなることが問題ではあるが、そこをクリアすれば先が見えてくる。もちろん広告宣伝などの課題は残されているが、これも試行錯誤の上で方法は見つかっていくだろう。
広告宣伝を考えると既存の出版社は、書店ネットワークをうまく利用できる。昨年は、電子書籍を紙の書籍を販売するための宣伝に利用した出版社も多かったが、今年は徐々に、書店で販売する紙の書籍は、端末で発売する“リッチコンテンツ書籍”の宣伝と割り切るパターンも増えてくるだろう(取次からの反発は横に置くとして……)。書店では、より安く書籍を販売し、紙書籍は“リッチコンテンツ書籍”のチラシと考え、本命の電子書籍に誘導する戦略も考えられる。
そのパターンではないのだが、先般iTunesストアに登場した『原色美人キャスター大図鑑』(文藝春秋)は、紙の書籍の内容に加え、キャスターのインタビューやプロフィールページ、ハイビジョンムービーや連続写真などを付けて8割程度の値付けで販売している。個人的には紙書籍と同じ値段でも売れると思うので、無理に安くせず1300円で販売してほしかったが、ターゲット読者にとっては垂涎の的であろう。
このパターンでは登場するキャスター自体がコンテンツなので、ギャラを割りきればコストも抑えられる。このように、端末が普及していくと考えられる今年は、紙の書籍の電子化ではなく、制作の段階から紙で販売することすら考慮せずに端末のみでの再生に特化した電子書籍が増えていくことだろう。そういった意味で、もはや主役は紙の書籍ではなく“リッチコンテンツ書籍”なのだ。であれば、電子書籍の“原料”である紙の書籍は必要ない。つまり今年は『リッチコンテンツ書籍元年』ともいえよう(笑)