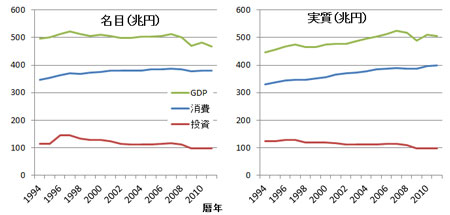今月の金融政策決定会合で、日本銀行は一段の金融緩和の実施を決めた。それが、株価や為替レートと言った資産価格には好影響を与えているとしても、金融緩和というのは、そもそもやればやるほど景気刺激的な効果があると本当にいえるのものなのだろうか。
前にも「米国の実質GDP改定値」という記事の中で一度書いたことがあるけれども、標準的(canonical)なニュー・ケインジアン・モデルには、摩擦要因(friction)として「価格の粘着性」しか取り込まれていない。価格の粘着性だけが摩擦要因であるという仮定を受け入れると、インフレーション・ターゲティングの枠組みの下で「物価の安定」を図ればすべてうまくいくことになる。しかし同時に、金融危機は起こり得ないことになる。
他方、この間の経験からすれば、「金融危機が起こり得る」モデルでなければ、現実の理解と政策立案に資するものとはならないことは明らかである。2007-09年の米国での金融危機の場合には、金融仲介機構の機能不全が実体経済の悪化をもたらした。こうした問題を検討するためには、当たり前のことだが、金融仲介機構の存在に実質的な意味のあるモデルを考える必要がある。
このことは、換言すると、金融仲介機構の存在意義につながる「金融・資本市場の不完全性というもう1つの摩擦要因」も考慮しなければならないということである。例えば、情報の非対称性の存在などから、貯蓄超過主体と投資超過主体が直接に取引することは不可能だとしよう。それゆえ、貯蓄が投資に転化されるためには、金融仲介サービスの供給が不可欠だとしよう。こうした想定の下では、経済活動水準は金融仲介サービスの供給量によっても左右されることになる。
こうした方向でのマクロ経済モデルの見直しを比較的分かり易く紹介した論文としては、Woodford (2010)がある。このWoodfordの論文では、金融仲介サービスの供給量は、スプレッド(金利差)の増加関数だとされている。通常のマクロ経済学のモデルでは、金利は1つの変数として扱われている。しかし、金融仲介機構の存在に実質的な意味があるとすれば、少なくとも貯蓄提供者(貸し手)に支払われる金利と貯蓄利用者(借り手)が支払わなければならない金利を区別することが不可欠である。
これら2つの金利が同一のものであれば、金融仲介機関にとっての利ざやは存在しないことになり、金融仲介サービスは供給されないことになる。この意味で、1種類の金利しか含まないマクロ経済モデルは、金融仲介サービスが必要とされない(金融・資本市場が完全な)世界に関するモデルであって、金融仲介機構の存在を正当に考慮したものになっているとは言いがたいものである。こうしたモデルに基づけば、金融緩和はやるほど効果的だということになる。
しかし、貯蓄が投資に転化されるためには金融仲介サービスが不可欠で、金融仲介サービスの供給量はスプレッド(金利差)の増加関数であるような世界を考えると、結論は異なったものとなり得る。すなわち、貯蓄提供者(例えば、預金者)に支払われる金利がすでにゼロになっていて、それ以下には下がれない状態で、さらなる金融緩和によって貯蓄利用者(借り手)が支払わなければならない金利の低下を促したならば、スプレッド(金利差)は狭まっていくことになる。このことは、金融仲介サービスの供給量を減少させ、経済活動水準をむしろ抑制するものとなる。
平たく言うと、十分な利ざやを確保できなくなれば、金融仲介機関はリスクをとって積極的に貸出を行うといったことはできなくなる。借り手からみても、借入金利が低下することはプラスでも、金融仲介機関の貸し付け姿勢が消極化することはマイナスである。後者のマイナス効果が前者のプラス効果を上回るようだと、一段の金融緩和は望ましいものだとは言えなくなる。
要するに、緩和施策でスプレッドを潰していくと、十分な金融仲介サービスの供給は行われなくなるおそれがある。植物に水をやることは、その育成のために必要だが、水をやればやるほど、その成長が促進されるというものではない。水をやりすぎると、根を腐らせてしまうことにもなりかねない。そうした懸念を金融緩和に関してはしなければならない局面にまで、既に来ているのではないか。
--
池尾 和人@kazikeo