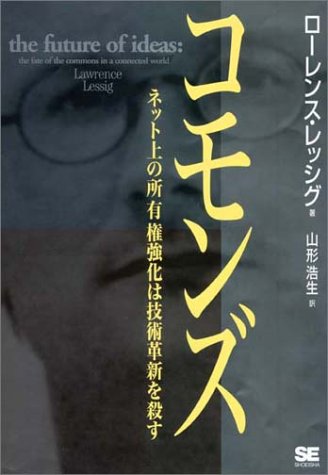日本経済新聞電子版(2012年2月24日)に『見るだけで感動、超高精細がもたらす新体験-テレビの未来(4)』という記事が出ていた。「立体感や実物感が新たな視聴体験につながる」「フルHD(1920×1080画素)をはるかに上回る超高精細映像が家庭に届く時期が近付いている。」セットメーカーは液晶テレビやプロジェクタあるいは業務用カメラの製品化を進め、通信業界では動画の圧縮技術が進展し、NHKは2020年から7680×4320画素映像の衛星を用いた試験放送を始める計画だという。
この記事には違和感を持たざるを得なかった。技術者は「より美しく」を求めるだろうが、利用者はHDの先を望むだろうか。同じように技術が先行した3D映画は、すでに「失速気味」という記事が2月15日付けの読売新聞に出ていた。「ALWAYS 三丁目の夕日’64」では3Dと2Dの興行収入比率が1対2だという。記事の結びにあるように「デジタル化という技術革新によって可能になった3次元の映像空間がどこまで広がるかは、あくまでも中身次第」なのだ。
近畿大学が1月19日に発表した『大学生の携帯情報端末の利用に関する調査』によると、スマートフォン所有者の78.9%がメディア視聴にスマートフォンを利用しているが、ワンセグ視聴は14.9%に過ぎない。PCでのメディア視聴の利用率も75.3%と高い。調査ではメディアの種類は特定できないが、僕のゼミ生がよく見ているYouTubeやニコニコ動画だとすると、彼らは精細度ではなく自分の嗜好に合う中身の映像を選択し楽しんでいる、と推定される。
より高性能を提供した結果、失敗したのがテレビゲーム機だ。ファミコン以来ゲーム機の性能は急激に上昇していったが、それに追随していったのはヘビーユーザだけだった。暇つぶしの利用者はスマートフォンでゲームを楽しむようになっている。リアルな映像表現は利用者をつなぎとめていないのだ。
超高精細も同じで、利用者を引き付ける中身がなければ普及するはずはない。超高精細技術の製品化に力を注ぐよりも、アップルやグーグルが主導するネットTVの時代にどのようなビジネスモデルで立ち向かうかを、業界は考えるべきだ。
山田肇 -東洋大学経済学部-