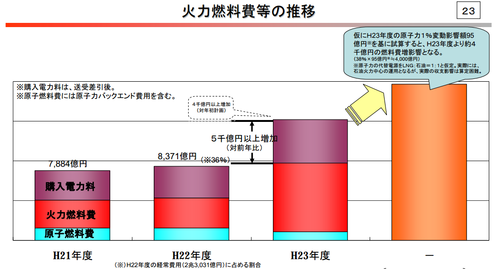勝間和代氏の新刊『「有名人になる」ということ』(ディスカバー携書)は、私のように文筆をなりわいとしている人間からすると、かなり興味深い本である。
勝間氏は、一時、ベストセラーを連発し、時代の寵児としてもてはやされた。たんに本が売れただけではない。彼女の生き方は、現代女性にとって一つのモデルとなり、その生き方を真似ようとする女性たちは「カツマー」と呼ばれた。
ただし、最近では、彼女の本がベストセラーの上位に食い込むこともなくなり、カツマーということばがメディアをにぎわすこともなくなった。今回の本では、その顛末が語られている。なぜ彼女の本が売れ、また、売れなくなったかが分析されている。たしかに、こうした本は珍しい。
まず注目されるのは、勝間氏が、「有名人になる」ということをプロジェクトして位置づけている点である。彼女は、JPモルガン証券を退職した後、「SRI(社会的責任投資)ファンド」を立ち上げる。ところが、リーマン・ショックが起こる年に最大の顧客だったヘッジファンドが日本から撤退したりしたため、その事業がうまくいかなかった。
そこで勝間氏は、2008年5月から、自分を売り出すことをビジネスとするプロジェクトをはじめる。このプロジェクトは、2009年末に紅白歌合戦の審査員となり、翌2010年3月の「金スマ」で彼女が特集されることで第1フェーズを終えた。その後、1年の休みの期間を経て、今年の1月からは第2フェーズに挑んでいるという。
勝間氏がこのプロジェクトを成功させるために、どういった試みをしてきたかは、すでにこれまで出版された本のなかでも詳しく説明されていた。本書でも、第2章の「有名人になる方法」で説明されているが、それ以上に興味深い章が、第4章の「『終わコン』有名人としてのブームが終わるとき」の部分である。「終わコン」とは、「終わったコンテンツ」の意味である。
勝間氏は、自分のブームのピークが2009年であったとし、その最後になったのが、『断る力』(文春新書)だったとしている。彼女自身が分析するには、初期の本は長年の蓄積にもとづいて書かれたものだったのに対して、2009年以降に出した本は、新たに取材したり対談したものを書籍にしたもので、初期に比べて濃度が下がっていた。
そのため、売れ行きが落ち、読者からもその点を指摘されていた。ところが、そんななか『断る力』が予想外に売れたために、自分のキャラクターを売ればなんとかなると過信してしまったという。それ以降の本を、彼女は「キャラ売り本」と呼んでいるが、それらはことごとく売れなかった。
勝間氏は、賛否両論がもっとも激しかったのが、『結局、女はキレイが勝ち』(マガジンハウス)だったと述べている。この本には彼女なりの意図があったものの、「いつからおまえは美人になったんだ」と非難囂々だったという。それも、彼女が有名人になり、不特定多数の人間に知られるようになったからで、簡単に反感を買ってしまったというのである。
物書きとして無視できないのが、次の連載についての分析である。勝間氏が有名になることで仕事が集中し、ピーク時には、テレビレギュラー4本、新聞連載3本、週刊誌連載3本、月刊誌連載2本を持つまでに至った。
そうなると、連載を本にして出すということになっていったのだが、そうしたものはことごとく売れなかったという。それでも数万部は出たというから、一般の基準からすればかなり売れたことになる。ただし、以前とは違い、10万部を超えるようなベストセラーは一冊もなかったという。
連載を本にするというのは、一冊書き下ろすより、はるかに簡単だが、そうなるとイージーで、乱発しているという批判を受けることになる。いくら著者として連載原稿に力を入れていても、連載時の字数が少なくて、深い分析にはならず、また、質的にどうしてもばらつきが出てしまうからだ。これは、文筆家なら誰もがこころしておかなければならない普遍性を持つ反省点である。
勝間氏は、こうした反省点をもとに、現在では有名人になるプロジェクトの第2フェーズに取り組んでいるわけだが、果たして彼女はそれに成功できるのだろうか。過信をせず、キャラ売りを止め、コンテンツの質を高めていけば、それはかなうのだろうか。
本を読んで気になったのは、勝間氏が、『結局、女はキレイが勝ち』にまつわる以外、自分が見舞われたバッシングについてふれていない点である。彼女の生き方については、精神科医の香山リカ氏から批判を受け、両者の論争は一時話題になった。
また、原発事故の後には、彼女が中部電力のテレビコマーシャルに出演し、原子力エネルギーの経済性を強調したことなどが批判された。彼女は、その点について反省し、謝罪はしているものの、この本ではそのことについてはまったくふれられていない。
私自身にも経験があることだが、自分が受けたバッシングについて語るということは相当に難しい作業である。世間はあまりに自分のことを誤解しているという気持ちもあるし、できればそれにふれたくはない、あるいは、ふれてもらいたくないという気持ちが生まれてしまう。
私も、地下鉄サリン事件の後に激しいバッシングを受けた後、オウム真理教について一冊本は書いたものの、それでもう終わりにしたいと考えていた。
しかし、バッシングによるダメージから回復するには、10年近い歳月が必要だったし、結局は、『オウム なぜ宗教はテロリズムを生んだのか』(トランスビュー)にまとまったように、オウム真理教の問題に正面から取り組まざるを得なかった。それがなかったとすれば、今のように文筆家として生活を成り立たせていくことはできなかったに違いない。
勝間氏は、一度有名人になれば、もう無名には戻れないと述べている。有名人になれば、ファンもできるかもしれないが、バッシングもつきものである。そして、バッシングを受ければ、やはりそれをなかったことにはできないのである。
バッシングを受けるには、やはり本人にも責任の一端がある。たんに世間の妬みを買うからではない。そうである以上、バッシングを受けた者は、もう一度自己のあり方に反省を加える必要がある。
その点で、バッシングは有名人になる上での「通過儀礼」であり、「試練」であるということになる。通過儀礼の際の試練を乗り越えるには、それを回避したりせず、ぶつかっていくしかない。今勝間氏に求められるのは、『乗り越えていく力』といった本なのかもしれない。
島田 裕巳
宗教学者、文筆家
島田裕巳の「経堂日記」