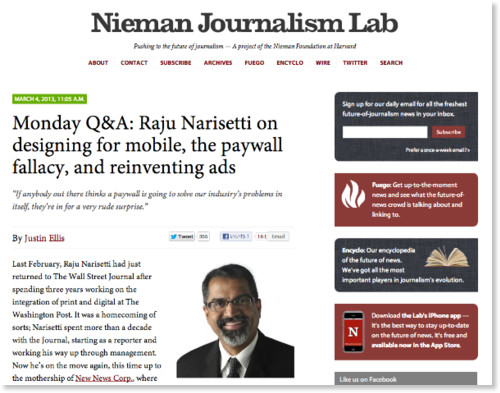デフレーション─“日本の慢性病”の全貌を解明する
個人的に、学者の書いた本を読むと「ふーん」で終わるものと「こりゃ空論だな」で終わるものが大半を占める。
だが、まれに「おお!」となる本がある。本書はまさにその一冊だ。
以前から日本型雇用とデフレには強い相関があるなというのは感じていたが、上手く言葉で説明出来なかったし、ほとんど取り上げる識者もいなかった。本書はその核心部分に大きく踏み込んでいる。
原油や天然ガスのような一次産品は主に需要によって価格が決まるが、工業製品やサービスは需要によって生産量が変わる。価格は生産コストでだいたい決まってしまい、生産コストの中には名目賃金も含まれる。原油価格は上がったり下がったりするけれども工場は操業停止すると言えばわかりやすいだろう。
ただし、日本の労使は終身雇用を守るため(一時金のカットや非正規雇用の拡大により)賃下げを受け入れてきた。
だから、他国では下がりにくい生産コストが下がり、製造するモノやサービスの価格も下がりやすくなってしまった(ついでに言うと、賃金が下がったわけだから、そういう値下がりも歓迎された)。
日本でだけデフレが続いたのは、日本でだけ名目賃金が下がり続けた結果であり、その根っこにあるのは日本型雇用だというのが著者の結論である。
といってもイメージしづらいよという人は、自分の会社で考えてみるといい。どこの大企業でも、社内に儲かっている事業部と万年赤字状態の事業がいくつも併存しているものだ。
儲かっているデジカメ事業部も万年赤字のテレビ事業部も、そろってボーナス1カ月分、「みんなでV字回復目指して頑張ろう、えいえいおー」的な会社があったとする。
儲かってるのにボーナス1カ月分ですむデジカメは、言い換えればすごく割安に生産できるわけだ。さぞ大安売りできることだろう。くわえて、採算のとれないテレビも各社ガマン比べしてズルズル生産を続けるから、家電量販店のテレビ売り場はバナナの叩き売り状態になる。
「おかしいなあ、なんでデジカメ売れてるのに、俺のボーナス上がらないんだ?」
「テレビもデジカメも、どうして値崩れが止まらないんだ?」
という疑問を抱えつつも、みんなはそれなりの生活が送れてしまう。
だって、食品も衣料品も自動車も、日本のすべての産業で同じことが起き生産コストの下がった割安な商品が市場に溢れているから。いわば、日本中がデフレ体質みたいなものである。
でも、失業率も(他国に比べれば)低いし、どんどん身の回りのものも安くなるから、言うほど居心地は悪くない。
こうしてぬるま湯のごとく、デフレは20年続いたというわけだ。
仮に、デジカメ事業部には5カ月分のボーナスを支払いつつ、お先真っ暗なテレビ事業は思い切って畳むような社会を想像してみよう。当たり前だが、デジカメの価格は下がらない。テレビ生産者も減るわけだから、そんなに値下がりはしないだろう。
と書くと「テレビ事業部の人達の生活はどうするんだ!」と青筋立てた反論が来そうだが、そういう面倒は政府が見ればいい話で、赤字事業の従業員の生活まで企業に背負わせる必要はない。彼らは彼らのスキルが必要とされる分野に移動し、新たな場で活躍してくれることだろう。政府はそのためのサポートをすればいい。
では、ぬるま湯だけどデフレが続く社会と、失業率はある程度高くなるけど流動性があってデフレでもない社会のどちらが良いのだろうか。人によると思うが、以下は筆者の個人的見解。
恐らく、両者の最大の違いは“希望”だと思う。流動性のある後者の社会では、商品なりサービスなり、いろいろな新しい何かが生まれそうな予感がする。ベンチャー企業はもちろんのこと、途中で畑違いの分野に移った人は、本人も受け入れた企業も、無数の刺激を受けるだろうから。
だが、前者のぬるま湯状態からは、ぬるま湯以外、わくわくするような何かが生まれるとはとても思えない。
筆者自身、かつては「一時金1ヶ月でみんなで頑張るぞえいえいおー」的組織にどっぷり浸かっていたのでよくわかるが、周囲には「ボーナス下がったから毎月30時間は生活残業するよ」とか「暇だから就業時間中にFX三昧」的なエピソードはいっぱい転がっていたけれども、賃下げ→デフレのサイクルを打破するような何かを産みだすものは、一度も感じたことがない。
理由は簡単で、えいえいおー的組織では「成果を上げる→高い報酬を得られる」ではなく
「成果を上げる→会社の業績がV字回復→みんなでせいぜい一時金3ヶ月程度になるかも」
という企業内トリクルダウン・プロセスしかなく、そういう特殊な報酬システム下で自己犠牲的に頑張る人はきわめて例外的だからだ。
「この仕事をやればいくら」という相場があればこそ、個人はより高い値札を勝ち取るために努力も工夫もするだろうし、理不尽な賃下げに対しては抗議の声を上げるのだろう。突き詰めれば、日本には労働という商品に値札をつける市場が存在しないことが、問題の本質なのかもしれない。
最後に、今後の展望について。
本書も示唆するように、よりよい処遇を求めて多くの労働者がばんばん流動化し始めるまで、日本がデフレ脱却することはないだろう。
政府の産業競争力会議、経済財政諮問会議、そして規制改革会議で、相次いで解雇規制の緩和を含む労働市場の流動化が議論されている点からするに、恐らく政権の中には、そこが本丸だと理解している人間が少なからずいるのだろう。
ただ、仮にそれなりの規制緩和が行われたとしても、企業内のメンタリティがいきなりガラリと変わるものではない。かつて共産主義が崩壊した後、市場経済が浸透するまで長い時間がかかったように、10年以上の月日がかかるだろう。「誰かがボタンを押せばデフレは終わり、自分の給料も上がるはず」と期待している人にとって、それは暗澹たる気分にさせる結論かもしれない。
一方、ゴール自体は明らかすぎるほど明らかなので、自らスキルを磨き、より良いポストに転職する意欲のある人間にとっては、晴れ晴れとした道が開けている。自らはスキルに見合った賃金を勝ち取りつつ、企業が我慢比べをして提供してくれる割安な製品やサービスを利用すればいいのだから。
政府が出来るのは規制緩和まで。その先、どういう人生を送るかは、あくまで自分次第ということだろう。
※一点だけ付けくわえれば、著者は価格や賃金の決定に際して期待はまったく影響しないとしているが、少なくとも賃金についてはかなり影響があるというのが筆者の意見だ。日本の労使は一度上げたらなかなか下げられないので、余裕があっても賃上げには非常に慎重である。
編集部より:この記事は城繁幸氏のブログ「Joe’s Labo」2013年3月18日の記事より転載させていただきました。快く転載を許可してくださった城氏に感謝いたします。
オリジナル原稿を読みたい方はJoe’s Laboをご覧ください。