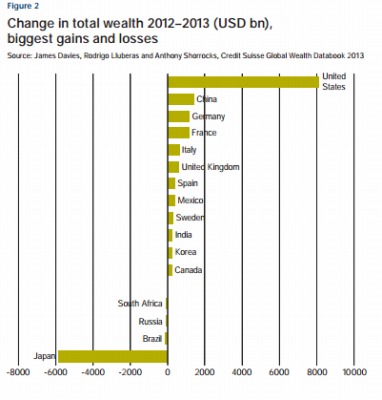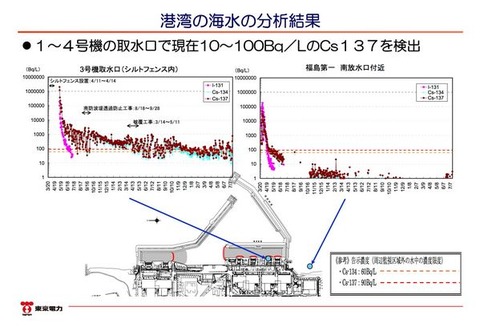米国と日本の教育制度が何から何まで違うことは、日本の知識階級の間でも意外に知られていません。
かく言う私も、終戦後の教科の大改定は勿論「六三制」や「短答式試験(0X式テスト)」などの導入に辣腕を振るった民間情報教育局(CIE)に始まり教育思想に大きな影響を与えたジョン・デューイに至るまで、戦後日本の教育は形も心も米国型一色に固められたとばかり思っていました。
ところが、米国の教育事情を知れば知るほど、日米の教育に対する考えの違いの大きさに驚かされ、その良し悪しや好き嫌い別として米国の制度を「こんな考えもあるのだ」と参考にしながら、日本の教育を考える事も重要ではないかと思うようになりました。
物の見方の違いと言えば、「どこかで本質を外している『デジタル教科書』論争」と言う松本徹三氏のアゴラ記事を読んだ私は、友人でもある松本さんにこんなメールを出した事があります。
「論争の中でフィンランドとPISAが出て来ますが、フィンランドは長い間、北欧の『発展途上国』扱いされて来た歴史があり、その汚名挽回策として採用した教育改革のモデルが『日本的教育』でした。その成果は『標準テストに強いアジア型生徒』の誕生で結実しましたが、この点について 2006年6月から2010年9月までノキアのCEOを務めたオリペッカ・カラスブオ氏が『教育水準の高いフィンランドに本社を置きながら、ノキアはアメリカのグーグルやiPhonのような新技術や新企画をなぜ生めないのか?』と株主総会で詰問されると『フィンランドの教育モデルは日本であって、国全体の平均点は低くても天才を生み出すアメリカの様な教育制度にはなっていない』と答えたエピソードがあります」
これでもお判りの通り、教育の成果は目的によりその計測方法を変えなければならないなど、統計比較だけでは結論を出せない難しさがあります。
「フィンランド教育」を例にとっても、カラスブオ氏の様に「そもそも論」に戻って分析する見方は米国ではよく見られますが、日本では理屈っぽいとして退けられる傾向が強いように思います。
面白い事に、日本の教育行政が「偏差値」「進学率」「試験成績」等の向上と言う数値上の「成果主義」に傾くのに比べ、「成果主義の本場」と言われる米国の教育論が「誰の為? 何の為?」と言う「そもそも論」無しには一歩も進みません。
俳優志望者はハリウッド、エネルギーに関心のある人はヒューストン、自動車はデトロイト、ハイテクはシリコンバレー、そして金融はニューヨークを目指すように、米国は都市まで主要テーマを核として発展してきました。
その為もあり、若者は「何をしたいか?」と言う自分の夢の実現に沿った専門化した教育を求める傾向が強く「偏差値」対策などは頭の隅にもなく、日本のように「偉くなる」為の教育(総合点主義)は人気がありません。
また、教育は「教育を受ける本人とその親の権利」と言う考え方が伝統の米国では、教育の中央集権化と画一化を極度に嫌い、徹底した地方分権と民営化が行なわれています。
1867年に一旦設立された米国教育省(日本の文科省)ですが、翌年には内務省の「局」に格下げされ、その存在すら忘れられた歴史を持つ米国と、全国標準教育を目指す「文科省」が「公平」の名の下に箸の上げ下ろしにまで口を出す日本は文字通り「月とすっぽん」の関係にあります。
その後、幾多の曲折を経て1953年に「保健福祉教育省」として内閣レベルに格上げされた連邦教育行政ですが、教育省として独立できたのは1979年になってからでした。
この時も「地方自治体が立派にこなしている教育に、新たな官僚主義を持ち込む」とか「地方自治体の専権事項を侵害する憲法違反だ」と主張する共和党議員中心の保守勢力の猛反対にあって教育省の設立は難航しました。
難産の末やっと設置された教育省の規模は、職員総数5千人弱と言う、米国省庁の中でも最少の省庁に留められています。
それでも、ダンカン現教育長官は前例の無い巨額な教育予算を獲得する一方、教員組合の抵抗を排してデジタル教育などの教育改革政策を推し進めています。
歴代長官の中でも図抜けて優秀だと評判のダンカン長官は、政策面では教員組合の要求を退けながら、新政策を進めるに必要な教員の再教育予算を獲得して教員の解雇を避ける巧妙なやり方で組合の信頼を得ていますが、彼には直接予算を割り振る権限は無く、新政策に同意した州政府に予め連邦議会で決められたフォーミュラー従って予算を割り振る事に限られています。
彼の成功は、ユニークな経験が支えになっていると言う評判です。
大学教授を父に持ち、貧困家庭子弟教育推進運動家として高名な母のもとにシカゴで生まれたダンカン長官は、子供の頃からの夢は第一がプロバスケットの選手、第二が公教育の専門家になる事でした。
学業にも優れ、199センチの長身にも恵まれた彼は、ハーバード大学のバスケットボール部の主将として活躍し、3回もNBAに挑戦しましたが夢適わず、オーストラリアのプロバスケット球団に入り4年間の選手生活を送りました。
その後シカゴに戻ッた彼は、第二の夢の実現の為に直ちに公教育の道に入り、ここでも多くの革新的なアイデアを実行し、たちまち米国で3番目に大きい600校を統括する学校群の長に上り詰めた人物です。
彼が長官に就任して以来、議会は教育省に多くの新しい権限を与えましたが、それでも教育政策の策定や関係諸官庁との協力推進、教育関係データの収集、教育補助金の配布方針の決定(方針の決定であって、学校レベルの配布権限は与えられていません)、教育現場での市民権法、プライバシー権法などの連邦法との整合性チェック(コンプライアンス)と違反の摘発(警察権も賦与されている)などコンサルタント的な任務にに限られ、学校の監督、教育カリキュラム設定、教科書認定、学力認定、学位賦与などの諸権限は依然として地方自治体や民間団体の所管事項となっています。
米国で日本の文科省に当たる教育省が不必要だと言う論議がされていると知った日本人の多くからは「アメリカの教育が荒廃する訳だ」とか「全国共通の教育の公平をどうする」と言う声が聞こえてくる気がしますが、米国の教育制度で育った人々がノーベル賞を筆頭とした世界一流の科学技術や文化関係の賞の受賞者数で世界を圧倒し、スポーツやエンターテインメントでもをリードしている現実は無視できません。
見方によれば圧勝に近いアメリカ教育の秘密はどこにあるのか?
先ず本稿で「(1)教育省不要説の消えない米国」を取り上げましたが、次稿からは
(2)教科書や教科に口を挟めない米国教育省
(3)国家検定教科書の無いアメリカ
(4)国立大学が全国で五校しかない米国
(5)アジア型、フィンランド型教育と米国の違い
(6)8人のノーベル賞受賞者を排出した公立高校
(7)教科書は貸し出し制で、最低5-6年使うアメリカ
(8)幼児教育と大学が優秀で、中高教育に問題の多い米国
(9)日本では絶対に生まれない「青い目、茶色い目」先生
(10)ノーベル賞やエンターテインメントで圧倒する米国
(11)一極集中の起きないアメリカ
等の特徴を、個別具体的な現象を中心に紐解いていきたいと思います。
2013年10月25日
北村隆司