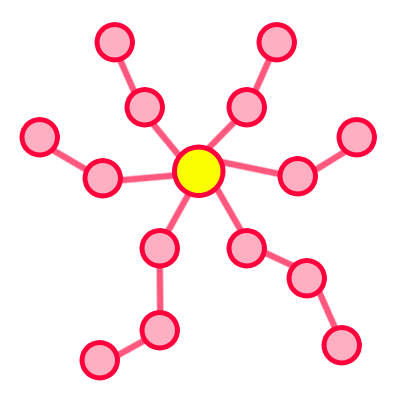秘密保護法が「治安維持法」だとか「全権委任法」だとかいって騒いでいる人々にとっては、平和は空気や水のように当たり前で、安倍政権はそれを「軍国主義」に導くものらしいが、不幸なことに人類の歴史はその逆である。自然状態はホッブズの言ったように「万人の万人に対する戦い」であり、それを抑止することが国家の機能なのだ。
1953年に書かれた本書(文庫による再刊)の出発点は、こういう平和ボケの対極にある。冷戦初期に西側諸国が依拠すべき価値を見失い、すべての価値を相対化する「歴史主義」が横行する状況で、国家は何によって統合されるのかを問うことが本書のテーマである。
ホッブズの自然状態は、思考実験ではなかった。彼はピューリタン革命から名誉革命まで内乱の続いたイギリスで、こうした戦争を終わらせるためには何が必要かを考えたのだ。かつては神の権威が人々を統合したが、神を失った近代人にはそういう共通の価値がない。そこでホッブズは死の恐怖を国家の基礎に置いた。
死んだら天国で救われるというキリスト教の信仰を失っても、死の恐怖はすべての人々が共有しているので、彼らは互いに殺し合う「囚人のジレンマ」を避けて互いに契約を結び、国家をつくるはずだ。その基礎となるのが、生存や財産などについての自然権である。
ホッブズはこうした自然権を実装する手段として権力を考えたが、バークは「自然な権利などというものはない」とし、すべての秩序は伝統と慣習で決まるとのべた。シュトラウスも死の恐怖や暴力だけでは国家は統治できないと指摘し、人々の自然に共有する価値に依拠する必要があるとした。
このように人類に普遍的な正義があるという理論は、一時「ネオコン」がイラクを侵略する根拠として利用したが、シュトラウスのいうのはそういう通俗的な話ではなく、ニヒリズムが知的な世界をおおい、社会を統合する価値が失われて国家がバラバラになることへの警告だ。
しかしその共通善とは具体的に何かという話になると、シュトラウスの話は曖昧になり、マッキンタイアやサンデルと同じようにアリストテレスを持ち出すが(というかこっちが先)、これは欧米圏以外では普遍的な価値になりえない。
天然ニヒリストである日本人には、シュトラウスの危機感は伝わらないだろう。彼らは国家=悪だと決めつける一方で、社会保障には国家が気前よく金をつぎ込むことを求める。国家はもともとバラバラだが、アメリカのおかげで戦争をまぬがれているので、人々は軍事機密もスパイ防止も必要ないと思っている。幸福な国である。