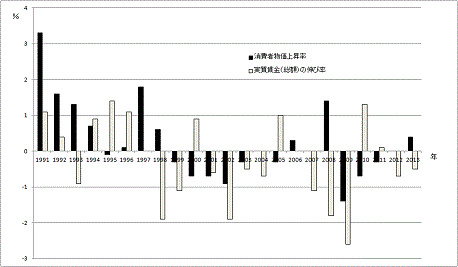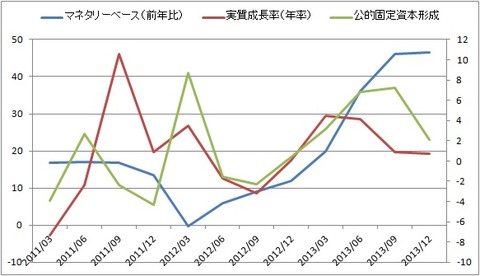1990年代の末頃から、緩やかな消費者物価の下落の中で、(名目賃金の下落の方が大きかったので)実質賃金の下落傾向が生じていた。そのために、名目と実質の区別に自覚的でないままに、あたかも消費者物価の下落が止まって上昇に転じれば、実質賃金も上昇に転じるという思いが生じたと考えられる。「デフレ脱却」が最優先課題だとされたのも、そうした思いからだとみられる。
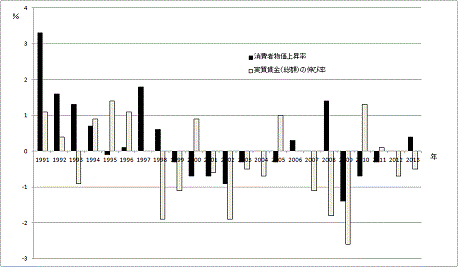
しかし、逆が真である保証はないし、同時に起こっていて相関が高いからといって、一方が他方の原因だとは限らない。実際、消費者物価上昇率がプラスとなった2013年も、実質賃金上昇率はマイナスとなっている。物価動向以上に本質的に重要なのは、われわれの実質賃金が上がるか下がるかである。したがって、この間の実質賃金の下落の本当の原因を知らねばならない。
この点に交易条件の悪化が関連しているということは、一橋大学の齊藤誠さんが強調されてきたことだが、実質賃金と交易条件の関係についてのきわめて参考になる論考(『週刊金融財政事情』2014.3.31号に掲載された深尾京司さんの「労働生産性と交易条件の悪化が招いた実質賃金率の低下」と川口大司さんの記事)を偶々、最近読む機会があったので、そのエッセンスを以下にメモしておきたい(しかし、3人とも一橋だなぁ)。
いま、yを実質GDP、Yを名目GDP、dをGDPデフレーターとすると、
である。したがって、
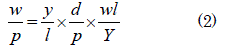
となる。要するに、上式の右辺を約分していけば、左辺になる。
ここで、wは名目賃金、pは消費者物価、lは労働投入量であるとすると、w/pは実質賃金、y/lは労働生産性、d/pはGDPデフレーターと消費者物価の比、そしてwl/Yは労働分配率を示すことになる。
すなわち、(2)式から分かることは、
だということである。上昇(変化)率にすると、かけ算が足し算になることに注意されたい(対数をとって、微分することになるから)。
すると、実質賃金が低下している(実質賃金の上昇率がマイナスだ)ということは、労働生産性の上昇率、(GDPデフレーターと消費者物価の比)の変化率、労働分配率の変化率のいずれに起因しているのかということになる。事実の問題としては、GDPベースでみた労働分配率はあまり変化していない。また、労働生産性の上昇率は鈍っているけれども、マイナスになっているわけではない。ということは、(GDPデフレーターと消費者物価の比)の変化率が大きくマイナスであることに原因があるという結論になる。
それでは、(GDPデフレーターと消費者物価の比)の変化率というのは、何を意味しているのか。GDPデフレーターも消費者物価も物価指数の一種であるが、前者はGDPを実質化するためのものなので、GDPの定義に従って輸出価格の変化率は加算され、輸入物価の変化率は控除される扱いになる。後者の消費者物価には、輸出価格は含まれず、(輸入物のワインとかをわれわれは消費しているので)輸入価格は含まれる。こうした違いから、(GDPデフレーターと消費者物価の比)の変化率は(輸出価格と輸入価格の比)の変化率にほぼ比例することになる。
この(輸出価格と輸入価格の比)が、交易条件と呼ばれるものにほかならない。交易条件とは、どれだけ有利に貿易を行えているかを示す指標である。すなわち、輸出するものが高く売れ、輸入するものが安く買えるならば、有利に貿易できているといえるし、逆に輸出するものが安くしか売れず、輸入するものが高いならば、不利にしか貿易できていないということになる。そして、この間、日本はどんどん貿易において不利な条件を強いられるようになっているのである。
日本が貿易において不利になってきているのには、1つには輸入している石油や食料品といった第一次産品が値上がりしているということがある。しかし、それだけではなく、輸出している工業品の価格が韓国等との競争の中で引き上げられないということがある。第一次産品の値上がりだけが原因なら、ドイツなどの交易条件も悪化しているはずだが、そうはなっていない。
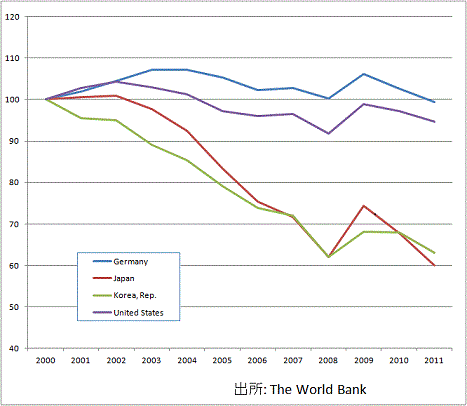
したがって、輸入価格の上昇に見合うかたちで輸出価格を引き上げられないという意味でのわが国の国際競争力の低下が交易条件の悪化につながっているといえる。そして、上記でみたように、交易条件の悪化が実質賃金の低下のもっぱらの原因になっている。以上のことから、実質賃金を上げるためには、労働生産性の向上を図ることに加えて、交易条件の悪化に歯止めをかけることが不可欠であることが分かる。「成長戦略」の主眼は、まさにそこに置かれるべきである。
--
池尾 和人@kazikeo