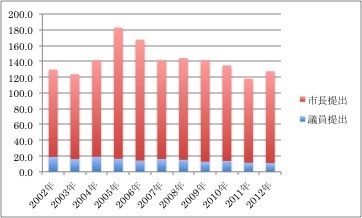都議会のヤジ騒動では、海外メディアが「日本は男尊女卑の儒教社会だ」という類のオリエンタリズムを振り回しているが、日本は儒教とは根本的に異なるボトムアップの平等社会である。この違いを日本人も理解していない。
本書も指摘するように、中国で「国」という概念に含まれているのは皇帝と行政府だけで、民衆は含まれない。人口比でいうと0.1%以下の「官」の世界だけが国だから、「国を守る」とは「王朝を守る」ということに等しい。このような階級社会を維持する上で重要なのは、頭脳労働と肉体労働の分離である。
人体を頭脳がコントロールするように、民衆を皇帝がコントロールするのであって、その逆であってはならない。多くの社会では階級は貴族身分として世襲されたが、中国は頭脳労働を官僚機構という形で組織化した点で先進的だった。宋代以降、人口が流動化すると、地方を支配する貴族の力が弱まり、皇帝と官僚による一元支配が強まった。
とはいえ財政の規模もGDPの数%の「チープ・ガバメント」なので、民衆を実効支配することはむずかしい。そういう少数の頭脳が多数の肉体を支配する構造を固定する制度が科挙だった。これは原則としてはすべての男子が受験できたが、11段階もの試験に合格するには、四書五経だけでなく朱子学などの参考書を丸暗記する必要があり、金と暇のある特権階級の子しか合格できなかった。
科挙では、法律などの実用的な知識は問わなかった。それは階級格差を正統化するシグナリング装置だったので、試験の内容は1000年以上ほとんど変わらなかった。中国の公教育はすべて科挙の予備校で、四書五経とその解釈を教えるだけだったので、科学技術は職人が徒弟修行で伝承するしかなかった。
日本は近世まで部族社会だったので貴族階級がほとんどなく、頭脳労働の特権化もあまりなかったが、明治時代に長州の「尊皇思想」で儒教の中央集権思想が持ち込まれた。高等文官や国立大学は、科挙をモデルにしたものだ。これは初期には身分制度を打破する意味もあったが、今となっては中国的停滞の原因だ。
社会の発展する最大のエネルギーは頭脳労働(人的資本)だが、それを特権化して教育内容を固定化すると国が滅びる。中国の歴史は、教育の自由な発展が社会にとっていかに重要かを教えてくれる。教育が形骸化し、入試が正社員という身分差別を正統化する科挙のような制度になった日本の大学は、その末路を暗示している。