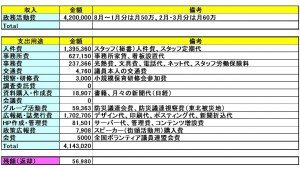ISの人質事件に対して政府は、テレビ朝日などの平和ボケに惑わされないで冷静に対応した。これは当たり前ではない。もし鳩山政権だったら、大混乱になっていただろう。安倍首相がぶれなかったのは、いい意味で彼の長州的ナショナリズムがきいたのだと思う。
本書は明治維新を「討幕運動」ではなく「新国家の建設」として描こうというものだ。維新が長州藩の徳川幕府に対する内戦であることは明らかだが、それだけではあの短期間に内戦が終結し、わずかな犠牲で「革命」が実現した説明がつかない。
その原因を著者は、攘夷という言葉に求める。これは従来、単なる排外主義と解釈され、維新の進行とともになしくずしに開国に方針転換したものと考えられてきたが、実は明治維新後も同じ意味で別の言葉が使われた。それは条約改正である。
幕府が西洋の軍事力との差に驚いて結んだ条約は不平等条約だったため、為替レートの安かった金が大量に流出した。これに対して幕府は金の含有量が2割しかない劣悪な通貨を発行したので、物価が10倍以上になるハイパーインフレが起こり、民衆は怒って新政権を支持した。
尊皇派が求めたのは、開港した横浜を閉ざして通商条約を破棄する破約攘夷だった。それが水戸学の影響を受けた吉田松陰などの長州のファナティックな尊皇思想と結びついてナショナリズムの形をとったが、実際には西洋的な意味での国民意識はなかった。
本書はこのように、明治維新が成功した原因を対外的な危機意識に求める。江戸時代にはバラバラに暮らしていた各藩の武士が短期間にまとまった原因は、まとまらないと侵略されるという「負のナショナリズム」としての攘夷意識にあった。それが各藩を超える天皇という、名目的に残っていた「虚焦点」を中心にしてまとまったのだ。
ナショナリズムは19世紀以降に主権国家を支えるためにつくられたフィクションであり、リベラル派も批判するように「想像の共同体」にすぎない。しかし根源的な意味では、あらゆる共同体は想像上のものである。戦後の日本を支配してきた平和ボケの共同体を離脱する梃子としては、長州的ナショナリズムも意味があるかもしれない。