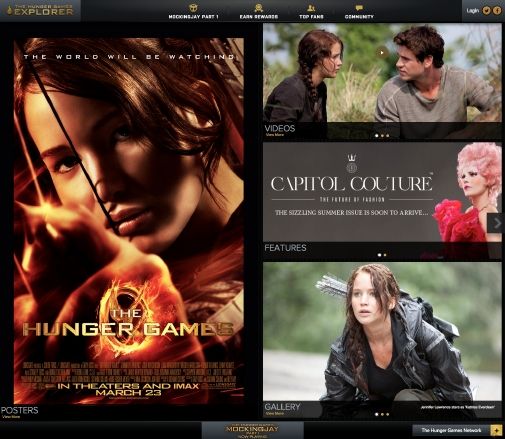イスラム教スンニ派過激テロ組織「イスラム国」が人質のヨルダン空軍パイロットを生きたままオリの中で焼殺したシーンが世界に流れると、欧米諸国では「イスラム国を絶対に許せない」といった声が高まってきている。地上軍派遣に消極的なオバマ米大統領は共和党議員だけではなく、民主党議員からも地上軍を派遣して「イスラム国」を壊滅すべきだという声に直面している。パイロットを焼殺されたヨルダンではアブドラ国王が率先し、「イスラム国」の軍事拠点の空爆を指導するなど報復に乗り出している。
「イスラム国」の蛮行に対してアラブ諸国ではこれまで消極的な批判の声はあったが、欧米諸国の「反イスラム国」に同調したくないという思いもあってか、その批判のトーンは少々腰が引けていた。ところが、「イスラム国」が同じスンニ派のヨルダンのパイロットを焼殺したというニュースが流れると、「火葬はアラーの教えに反する」という強い反発があがり、「イスラム国」打倒を求める声が出てきているのだ。
イスラム教では火葬は禁止されている。肉体がなければ審判の日、復活できないからだ。だから、通常は土葬だ。そのイスラム教の教えに反し、スンニ派過激組織「イスラム国」がスンニ派信者のヨルダン空軍パイロットを焼殺したのだ。これは明らかにアラーの教えに反することから、イスラム教スンニ派最高権威アズハルから批判が飛び出してきたわけだ。
スンニ派諸国内で焼殺に対する批判の声が高まると、「イスラム国」は「焼殺は完全には排除されていない」という外典を引用して応戦するなど、教義論争の様相を呈してきた。異教徒を殺すことには長けている「イスラム国」指導者たちも、人質の焼殺が引き起こした教義論争に戸惑いを感じ、守勢を余儀なくされているという。
神学・教義論争に一旦首を突っ込むと、終わりなき論争が展開されることはわれわれもキリスト教神学界で体験済みだ。自身の主張を裏付ける言葉を探そうとすれば、66巻から成る旧約・新約聖書の中に、自身の神学を擁護する聖句を見つけ出して、その正統性を主張すれば、相手側も同じように聖書から相反する聖句を取り出して反論する、といった具合だ、そのような不毛な神学論争の結果、キリスト教は現在、約300のグループに分裂しているわけだ。
だから、というわけではないが、アラブ圏で突然起きた教義論争に余り突っ込まないが、聖書には「火の審判」という表現が頻繁に出てくるから、その「火の審判」について少し考えてみよう。
新約聖書の「ペテロの第2の手紙」第3章には「その日には、天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう」と、終末の時、「火の審判」があると記述している。「ルカによる福音書」にはイエスは審判者として「火の審判」をもたらす、という聖句がある。だから、聖句を文字通り受け取れば、終わりの日には「火の審判」があるということになる。
しかし、イエスが実際、火で審判されたという箇所は聖書には見いだせない。「火の審判」は何かを象徴していると受け取らなければならない。「ヤコブの手紙」第3章には、「舌は火である」と書かれている。以上から、イエスの口から出た言葉が「火」と象徴され、イエスの言葉を守るか否かが終わりの日、審判されると解釈できる。決して、異教者を火刑に処すことを意味していないのだ。
「イスラム国」テロリストはスンニ派信者をアラーの手ではなく、自身の手で焼殺した。これはイスラム教の教えに明らかに反している。「火の審判」を受けるのは若きパイロットを焼殺した「イスラム国」のテロリストたちだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2015年2月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。