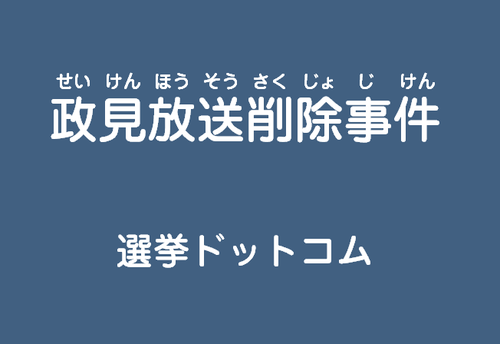大学院を出て就職してから20年余り、日本だけでなく色々な国の企業とも仕事をしてきました。研究開発はリスクが高いのは当たり前ですから、どのプロジェクトが成功するか、確信など持てません。
しかし、「これは失敗するだろうな」というのは、やっている人を見ればわかるようになりました。
見分けるポイントは、当事者、特にマネージャーの熱意・リスクを取る覚悟です。
研究開発はリスクが大きいのが当たり前。大きなブレークスルーを狙うほど、失敗する確率が増えるのは必然です。また、みんなが良いと思っているような常識的な内容はすでにコモディティ化しているわけで、「そんなのできるはずがない」という課題にこそ、大きな成功の可能性があるのです。
このように、非常識なアイデアに賭けるのが研究開発の本質ですから、「リターンもそこそこで良いから、リスクを少なくしたい」というような、「常識的」な感覚では無理なのです。
企業であれ大学であれ、研究をスタートする時は
「その研究をやってみたい!」
「絶対にそれが当たるはずだ!」
という研究者・技術者の熱い思いから始まります。勝手な思い込み、と言っても良いのかもしれません。言葉は悪いかもしれませんが、一種の狂気のような思い入れがなければ、大きなブレークスルーを生み出す可能性がある、ぶっ飛んだ研究などできないのです。
さてそうしてぶっ飛んだ研究者の思い入れで研究開発が始まり、「ものになりそう」となると、実用化を目指して組織的に開発が行われるようになります。
この時、大企業でありがちなのは、年功序列で昇進していった年長の常識人が、言いだしっぺの比較的若い技術者の上に立ち、プロジェクトを運営するようになる。開発が順調ならばそれでも良いのですが、リスクが大きい研究開発は山あり谷あり。むしろ「もう駄目だ」と思うようなどん底の時期が長いのが当たり前です。
研究開発から事業化の間には「死の谷」があると言われるように、長く続くどん底の時期に踏ん張れなければ、プロジェクトは失敗に終わります。そうした勝負どころで、年功序列で昇進していった秀才タイプが上に立つとどうなるか。
そのプロジェクトに人生を賭けるというよりも、失敗しても自分の責任にならないよう、下手をすると言い訳作りを始めてしまう。成功した時は自分の手柄、失敗したら部下のせい、というアリバイ工作です。あるいは、「自分は平穏な会社生活をおくりたかったのに、なぜこんなリスクの高い仕事の責任者にさせられるのか」と思っているかもしれません。
開発を成功させるためには、時には大きなリスクを取る必要がありますが、失敗しないためにできるだけリスクを避けようとする。そうすると大失敗はしないかもしれませんが、成功もしない。挑戦しないことで、成功の芽を摘んでしまう。研究開発に限らないかもしれませんが、どの企業が良い、ダメと言うより、やっている人に熱意、リスクを取る覚悟が無ければだめなのです。
「上司に言われたからやっています」
「たまたま年功序列の巡り合わせでその仕事をやっています」
という人では、下手をすると、できるだけリスクの高い仕事をしない方が最適になってしまう。
仕事をしなければ、失敗もしないという思考です。
研究開発というと、テレビドラマ「下町ロケット」が話題になりました。
このドラマでは、阿部寛さんが演じる主人公(中小企業の佃製作所の経営者・技術者)が作ったロケットエンジンのバルブを、吉川晃司さんが演じる大企業(帝国重工)の財前宇宙航空部長が高く評価する。帝国重工の取締役会で社長に対して、財前部長が「全責任は私が取る」と自分のクビを賭けて、佃製作所のバルブの採用を直訴する。大企業のエリートサラリーマンが誰に頼まれたのでもなく、自ら進んでリスクを取る、このシーンに感動した方も多いでしょう。
ドラマほど劇的ではないにしろ、自社内で開発する場合も、自らリスクを取ってプロジェクトを牽引するマネージャーが居なければ、リスクの高い研究を実用化まで持っていくことは難しいのです。
今の電機メーカーの苦境の理由は色々あるでしょうが、年功序列の人事システムが、変化が激しい研究開発をするのには合っていない、というのもイノベーションを生まれにくくしている一つの理由ではないでしょうか。
ところで、阿部寛さんは、私が所属する中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科のOBです。テレビドラマほど劇的でないにしても、研究開発は熱い思いが無ければ成功しない、人との出会いによっても左右される、とても人間くさいドラマなのです。
「下町ロケット」のように、人生を賭けて何かを成し遂げたい、という熱い思いがある人には、技術者というのはやりがいがある仕事だと思いますね。
編集部より:この投稿は、竹内健・中央大理工学部教授の研究室ブログ「竹内研究室の日記」2016年2月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「竹内研究室の日記」をご覧ください。