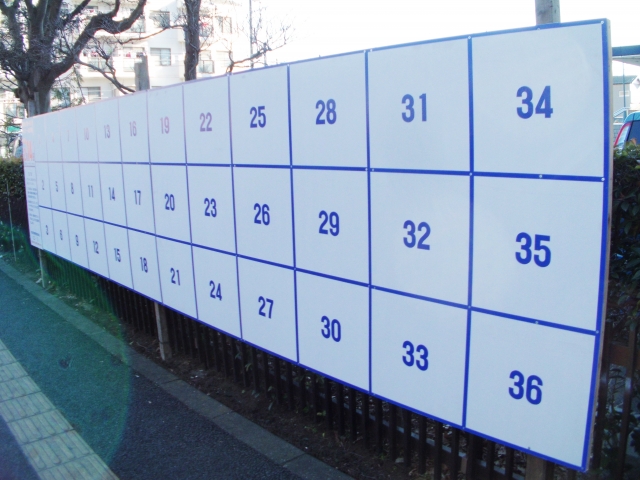橘川 武郎
講談社現代新書
高橋淳志 早稲田大学政治経済学部学生
(投稿原稿)
筆者は「日本電力産業発展のダイナミズム」などの著書がある電力・エネルギー産業の研究者で、経済産業省「総合資源エネルギー調査会基本問題委員会」委員を務めていた。
筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。
電力改革を論じるにあたって、まず電力の大部分を供給している電力会社(ここでは行政用語でいう「一般電気事業者」、東京電力などの十の電力会社のみを指す)をどう変えるか、を検討しなければならない。本書はその議論のスタート地点を提供してくれる。
電力会社はどう変わっていくべきか。
「電力会社は経営の自律性を取り戻すべき」だと筆者は結論づけている。日本の電力供給は、戦時中の一時期を除いて一貫して国営ではなく民営だった。戦後は1)民営2)発送電一貫3)地域別九分割4)独占、の四つの特徴を持つ「九電力体制」(沖縄返還以降は沖縄電力が加わり「十電力体制」)に基づいて運営されてきた。
九電力会社の国営化が考えにくい以上、民間企業としての経営の自律性を取り戻せば国全体のエネルギー・セキュリティにもつながる、という筆者の見解には全面的に賛同する。
石油危機以前には、九電力体制にも「黄金時代」があったという。電力会社は戦時中の国営復興を企む経済企画庁の特殊法人「電源開発」との競争や他の電力会社との低価格・安定供給競争を戦っていた。その日本の高度経済成長への貢献は計り知れない。
では、競争を拒む現在の九電力会社の姿はどこから来るのか。
筆者はその主因を国策民営方式の矛盾に求めている。
電力会社にとって原子力発電は、立地する地域住民・自治体との関係構築やバックエンドといった問題が付随することにより、国家と足並みを揃えることを余儀なくされる電源だ。
原子力発電をその手札に加えたことで、電力会社は国家と同調し官僚化することを余儀なくされた。
端的に言えば、今日の九電力会社への不信の要因は彼らが市場競争を拒み始めたことにあると言える。地域独占が確立されていたとはいえ、石油危機の頃までは九電力会社は政府がつくった特殊法人「電源開発」や他の電力会社と競争していた。
今はPPSとの競争を拒む官僚的組織に成り下がり、メディアと大衆から蛇蝎の如く忌み嫌われる要因を提供してしまっているのは周知の通りだ。
このような日本の九電力体制の現状を踏まえた上で、筆者は目指すべき改革の方向性を本書の中で示している。「歴史的大転換」を論ずるだけあって、あらゆる側面を網羅していて電力改革に関心を持つ人々が手にとって損はない本に仕上がっている。特に原発推進・反対の善悪二分論に辟易している人にとって、原子力発電が占める重みは原子力発電それ自体によって決まることはないという指摘は耳を傾けるに値するに違いない(p14)。
本書を読むことで以下の二点の重要さを改めて認識できた。
まずは改革の前に、現状を正確に把握することの重要さだ。改革を求めると、今起きている変化にばかり目が行きがちになりだ。しかし、目に付きやすい変化の外で厳然と変わらない要素群を含めた全体像を把握することが、改革を成功させるのに重要なのは言うまでもない。
次に数十年先のことを議論する際に、必要以上に悲観せずに希望を持って難問に向き合うことの重要性さだ。その希望の一例も、最終章でもれなく示されている。地域経済活性化にエネルギーが果たせる役割に関心がある方は、この章にぜひ目を通していただきたい。