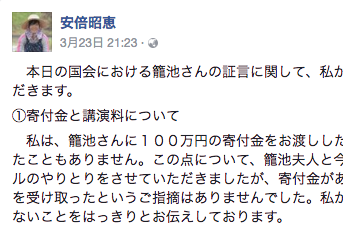明治国家を「絶対主義の天皇制国家」とみるのは誤りだ。天皇がダミーで実権が長州閥にあることは、政治家や官僚に共通の理解だった。帝国議会は法案や予算に「協賛」するだけだったが、政党はそれを否決する権限をもっていたので、それほど無力な存在ではなかった。むしろ明治憲法を起草した井上毅は、政党が政府を超える幕府的存在になることを恐れ、内閣を憲法から削除した。
井上の権力分立の思想は、穂積八束や上杉慎吉など東大法学部の主流に継承された、と著者は評価する。穂積はイギリスの議院内閣制を「立法権と行政権をあわせ持つ専制政体」だと批判し、合衆国憲法の権力分立を理想とした。彼らは立憲君主制に反対したのではなく、議会が政府を支配する権力集中を批判したのだ。「統帥権の独立」も「司法権の独立」と同じく、軍部を政党から独立させる制度だった。
しかしこの制度設計には弱点があった。名目的には天皇が無限の権力をもちながら、実質的には「元老」を中心とする藩閥政府が権力を独占する構造は、元老がいなくなると無政府状態に陥る。吉野作造は1916年に、バラバラになったドイツ帝国を「ドイツは共和国なり」と評したが、共和国は戦争のような非常事態を指導する「主権者」がいないため、ナポレオンやヒトラーのような独裁者が出てくる可能性がある。
日本は古代から天皇という名目的な主権者を置き、その代理人と称する独裁者をつねに排除するシステムを内蔵する世界最古の共和国ともいえる。それは洗練されたシステムだが、主権者が不明なので危機管理に弱い。前の戦争がその失敗例だが、朝鮮半島が非常事態に直面しているのに国会が幼稚園の問題に1ヶ月も費やす現状もほとんど無政府状態である。
著者は史実にもとづいて慎重に議論を進めており、その歴史認識にも共感できるが、終章にいきなり出てくる「反原発」や「憲法9条」は本論とつながっていない。戦後の日本を支えてきた「アメリカの平和」が終わった今、必要なのは著者が「短絡的なリアリズム」として否定する地政学的な現状認識だろう。