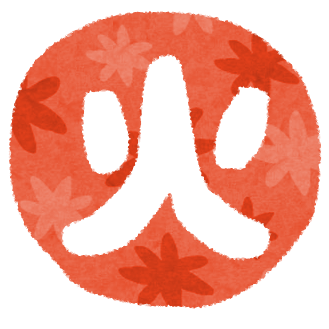色についての考察を続ける。
中国の北方で、キュウリは「黄瓜(ホァングア)」で、文字通り、日本にはこの言葉がそのまま入ってきた。だが、中国の南方に来て気づいたのは、「青瓜(チングア)」と呼んでいることだ。南方にはしばしば、中国中原地方の古い伝統が残っていることを考えれば、キュウリはもともと「青」だったのではないか。色の誕生から考えても、青は黄よりも早い。現代のわれわれからすれば、明らかに「緑」にしか見えないが、それは古人の色彩感覚を失ったからに過ぎない。
人類が色によってものを識別するのは、かなりあとになってのことに違いない。なぜなら身の回りに最も多い「緑」がまず生まれていなければならない。だが「緑」は糸へんに、「井戸の水」である。織られた布の色を指しているので、人工的なものだ。だから日本人は信号機の緑を、より慣れ親しんだ「青」の名で呼ぶ。
原初的な色の文字はまず「赤」だ。

大きな火である。「赤誠」「赤心」、あるいは「赤貧」「赤脚(素足)」の言葉があり、雑物がない徹底したさまを示す文字だ。日本語では、「あか=明るい」につながり、「赤の他人」「真っ赤なウソ」という。そこには本来、古人の火への信仰があった。京都の「大文字の火」がなぜ「大」なのかについては諸説あり、判然としないようだが、火、そして、大きい火=赤への信仰があったとは考えられないだろうか。弘法大師にあやかるよりも、もっとロマンチックではないか。
次に「黒」がある。
 <
<
やはり火にかかわる。火を使った結果、ものはあぶられ、死に絶え、炭化する。くろは「暗い」につながる。赤が太陽の照る昼ならば、黒は火の消えた夜である。色というよりは、暗黒の世界を示したに違いない。
「白」もまた火を連想させる。

烽火を焚いたような形だ。口が並んでいる。人々が議論しているのだ。その結果、道理が顕かになる。だから「明白」「坦白(正直に話す)」「潔白」という。火というよりは日、太陽光線に近い。「白日」である。
そして、「青」。

井戸から生まれてくるもの。地下に眠る鉱物を示してる。世の中に出て間もない。だから「青春」「青年」と言われ、日本語では「青田」「青二才」の表現として生きている。こう考えれば青果の意味も理解できる。
色が先にあるのではなく、形や性質があって、それに人間が色をつけた。色眼鏡で見るとは、まさにこのことを言う。人は考える苦労を惜しむから、簡単な色分けにすがろうとする。それでは誤解や錯覚を塗り重ね、色を固定化することになる。かといって色を排除するのではない。色の裏に隠された本当の姿を探すことが大事なのだ。
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年5月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。