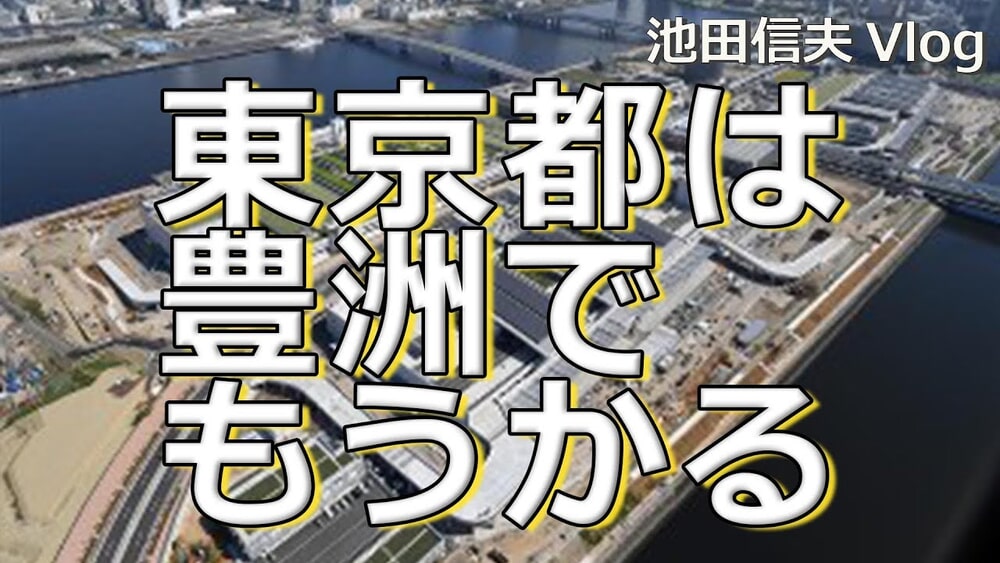前川前文科省事務次官の「出会い系バー」への出入りを大きく報じた読売記事を、私が徹底批判した【読売新聞は死んだに等しい】は、予想を大きく上回る反響を呼び、ネットの世界を中心とする不買運動も拡がるなど、読売新聞に対する批判は高まっている。
加計学園問題について、国家戦略特区を担当する内閣府職員から文科省職員が「官邸の最高レベルが言っている」「総理のご意向だ」などと伝えられた内容の文書について、前川氏が、同記事の3日後の記者会見で「確かに存在した」と述べただけではなく、文科省内からも、「存在した」との話が相次ぎ、結局、文科省も文書の存在について再調査をせざるを得ない状況に追い込まれた。加計学園問題は、今後、一層重大な事態を迎えることが必至の状況になってきた。前川氏の証言も文科省内部の声も無視し続けている読売新聞の報道のいびつさは一層顕著になっている。
読売新聞社及び読売グループは、まさに極めて深刻かつ重大な事態に直面している。
上記ブログ記事でも述べたように、今回の前川氏に関する記事の問題は、言論報道機関としての新聞社の「不祥事」である。組織として、それを正面から受け止め、信頼を回復するために最大限の取組みをしなければならない。
そのような事態において最も重要なのが、組織のトップの対応であることは言うまでもない。昨年6月に、読売新聞グループ本社社長に就任した山口寿一氏が、今回の問題にどう対応するのか、そこに、読売新聞の組織の命運がかかっている。
実は、その山口氏が検察や裁判所を取材する「司法記者」だった時代、現職検事だった私とは深い付き合いがあった。山口氏は、事件の分析・評価、取材・記事化など、あらゆる面で優れた能力の持ち主で、なおかつ、人間として極めて信頼できる人物だった。私にとって、当時の山口氏は、腹を割って話をすることができる大事な存在であった。
山口氏と私との付き合いは、90年代初頭、私が検察庁から公正取引委員会事務局に出向したころに遡る。出向前に関わった捜査で、「ストーリーありきの調書中心主義捜査」「不当・違法な取調べ」の現実を知り、特捜検察に深く失望していた私と山口氏の問題意識はほとんど一致していた。しばしば飲食を共にし、検察や公取委・独禁法の問題などについて、意見を交わした。
その後、公取委から東京地検特捜部に戻った私は、まもなく始まったゼネコン汚職事件の捜査体制に組み込まれた。「特捜の暴走」に加担させられることに苦悩していた私にとって、唯一の理解者だったのが、当時社会部の遊軍記者だった山口氏だ。彼自身、検察側だけではなく、検察の暴走捜査に押しつぶされそうな捜査対象者に対して、独自の取材を試みたりしていた。事件の真相に迫り、不当な捜査を止めたいという思いを共有していたと思っている(このゼネコン汚職事件をモデルに、特捜の暴走と司法マスコミとの癒着を描いた推理小説(【司法記者】講談社文庫:2013年、ペンネーム由良秀之)には、検察の「組織の論理」に反発し独自の行動をとる若き検事と、その検事に水面下で協力し連絡を取り合いつつ、独自の取材を行う記者が登場するが、その記者のモデルとなったのが山口氏である。)。
その後、私は、一旦は検事辞職を申し出たが、当時の人事課長等に慰留されて検察の世界に残り、その後、広島地検特別刑事部、長崎地検等で、独自の手法による検察捜査に取り組んだ(【検察の正義】(ちくま新書:2010年))。山口氏とは、その間も、折に触れて、連絡を取り合っていた。
そのような電話でのエピソードの一つに、「特捜部50周年キャンペーン」がある。司法クラブの各社が、露骨な「東京地検特捜部賛美記事」の特集を組むことを最高検検事から半ば強要されていることに不満を抱いていると聞いたことは、著書でも紹介している(【検察が危ない】(ベスト新書:2010年)p.119)。
このような話をしてくれたのが、当時、読売の司法クラブキャップだった山口氏だ。司法記者としての彼が、権力に利用されることに対する抵抗感という、極めて真っ当な感覚を持ち合わせていたことを示している。
捜査の重要な局面で、彼が、わざわざ東京から来てくれて、私の話し相手になってくれることもあった。
広島地検特別刑事部長の時代、広島県が設定していた海砂採取の期限延長を画策した採取業者と県議会議長・議員との癒着を追及した事件の際、広島に来てくれた山口氏とは、捜査の方向性や、瀬戸内海での海砂採取の環境問題としての重要性などについていろいろ議論をした。この事件は、政治資金規正法違反事件の検察捜査から海上保安部との共同捜査による砂利採取法違反事件に展開し、県内の全業者が摘発されたために、県は、期限を延長することなく採取を全面禁止にした。閉鎖水域での海砂採取禁止は、その後、瀬戸内海に面する他県にも波及していった。
長崎地検次席検事の時代、公共工事利権を背景とする、自民党の地方組織の集金構造の解明に向けて取り組んだ自民党長崎県連事件では、「検察の組織の壁」に何回も阻まれた(前掲【検察の正義】最終章「長崎の奇跡」)。検察裏金問題の関係で自民党政権に借りができたのか、最高検・法務省からの捜査への圧力は強烈だった。その最も重要な局面でも、山口氏は、長崎まで来てくれたことがあった。次席官舎で深夜まで飲み明かし、最高検・法務省の壁を打ち破ることに関して多くの助言をしてくれた。山口氏は、その後、配下の記者を長崎に出張させ、読売本社社会部としての取材・報道も試みてくれた。
このように、検事時代の私が自分なりのやり方で現場の検察捜査に取り組み、苦悩していた時、いつも力になってくれたのが山口氏だった。検察について、彼と話したこと、議論したことは、私にとって大きな糧となっている。
そういう山口氏とは、私が検察の現場を離れ、コンプライアンスを専門とする大学教授・弁護士の活動を始めて以降も、親しく付き合っていた。報道の現場を離れ、法務部長等の立場で新聞社の経営問題に関わるようになっていた山口氏は、私が桐蔭横浜大学コンプライアンス研究センター長を務めていた2005年、各業界の主要企業のコンプライアンス責任者をメンバーとする研究会を立ち上げた際に、読売新聞の法務部長として研究会に参加してくれた。当時は、独禁法等に関する読売新聞の法務的な重要課題について、私に相談をしてくることも多かった。もちろん、私も、彼からの相談に対しては、可能な限りの助言をした。
しかし、私が東京地検特捜部の陸山会事件の捜査に対してメディアを通じて検察を厳しく批判するようになった2009年頃から、山口氏は、私とは全く連絡をとらなくなった。長く続いていた年賀状のやり取りも途絶えた。
その後、一度だけ、私の方から、山口氏の携帯電話に連絡をとろうとしたことがある。当時読売新聞社専務であった山口氏をめぐる問題が週刊文春で取り上げられた際だった(2014年2月6日号「仰天スクープ ナベツネも知らない読売新聞の『特定秘密』」「”御庭番”山口専務が謎の女性に入れ揚げ 会社を私物化」)。そこで書かれていることが、私の認識する山口氏とはあまりにもかけ離れたものだったので、その真偽を確認したかったのと、もし、それが事実であれば、一言助言・忠告をしたいと思ったからだった。しかし、留守番電話にメッセージを入れても、秘書を通じて伝言を頼んでも、山口氏からの連絡はなかった。
少なくとも、私が知る司法記者時代の山口氏は、今回の前川氏に関する記事を書いたり、関わったりすることの対極にある記者だった。しかし、今回の前川氏に関する記事について、読売社内では、「山口社長が社会面に書くよう命令した」と言われているとも報じられている(【政権「忖度メディア」の現場記者に今何が起きているのか!?】週刊プレイボーイ6月17日号)。
類まれな傑出した司法記者だった山口氏が、今回の前川氏に関する記事に主体的に関わるような人物になったのだとすれば、彼がグループ社長になるまでの間に大きな変節があったことになる。その背景には、読売新聞という組織の病理があるのであろう。それがいかなるものなのか、山口氏自身が最も良く知っているはずだ。
山口氏には、今一度、司法記者時代の「原点」に立ち返ってもらいたい。そして、グループの総帥としての統率力を発揮して、新聞社の組織を歪めてきた病理を正してもらいたい。
それ以外に、読売新聞を救い、言論報道機関として再生させる手立てはない。
編集部より:このブログは「郷原信郎が斬る」2017年6月9日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、こちらをご覧ください。