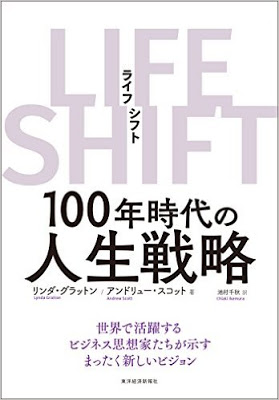東西両ドイツの再統一を実現し、欧州連合(EU)の統合を促進してきたヘルムート・コール元独首相の歩みについて、独週刊誌シュピーゲル最新号(6月22日号)は30頁余りの特集を組んでいた。そこには人間コール氏の側面が浮かび上がるようなエピソートが溢れていた。多分、日本の読者にとって初耳のエピソードもあるだろう。そこで2、3の面白いエピソードを紹介する。
コール氏は大男だ。193cmで体重も久しく120kgを超えていた。コール氏は食事が大好きだった。その食事摂取量は通常の人の2倍から3倍にもなったという。知人や友人と食事をしている。隣席の人があまり食べないと、「君は食べたくないのかね」と言って自分のフォークでその人のお皿から食べ物をつまみ、自分の口に平気で入れてしまう。
車で移動する時は秘書に「食べ物を買っておいただろうね」と必ず念を押す。車が動き出すと、秘書か準備していたおやつや軽食を早速食べだす、といった具合だ。大好物はパスタとそのソースだ。メインが終われば、必ずプディングを食べたという。
シュピーゲル誌によると、ドイツの首相の食事は一様に健康には程遠いという。ヘルムート・シュミット首相(任期1974~82年)はインスタントスープとコーラを、ゲアハルト・シュレーダー首相(同1998~2005年)はストレス解消のために頻繁に赤ワインを飲んでいたといった具合でゆっくりと食事を楽しむことは少なかったという。
その点、コール氏は例外だ。コール家は代々大男が多く、それでいて長寿の家系だったという。大好きな食事を人の2倍、3倍食べながらも大病に罹ることもなく長生きする。コール家系の誇るDNAが羨ましくなる。
コール氏の人間関係ははっきりしていた。友か敵かの2通りしかなかった。中途半端な第3者はいなかった。コール氏が党関係者や知人に要求するものはロイヤリティ―だった。それを知っている関係者はコール氏が深夜遅くまでその日の出来事の話をする時、疲れたと言って席を立てば、コール氏から「あいつはロイヤリティ―がない」といわれる恐れがあったから、必死になって眠気と戦ったという。ある関係者などは膝に針を刺して眠気と戦いながら、退屈なコール氏の話に耳を傾けざるを得なかった、という。
コール氏は政敵や好きでない人から批判されたり、バカにされたとしても、その場で顔色を変えないが、後でその人間が何を言ったか決して忘れることがなかったという。記憶力は抜群だったという。
コール氏はルードヴィヒスハーフェン・アム・ライン生まれの地方出身の政治家だった。ベルリンや大都市出身の党関係者からバカにされたり、揶揄されたりするのが嫌だったという。その点はコール氏は小心だった。
興味深い点は、東西両ドイツの再統一問題に対するコール氏の姿勢だ。コール氏の時代、多くの知識人たちは、「ドイツの分断はアウシュビッツ強制収容所のユダヤ人虐殺など多くの戦争犯罪を犯した民族への刑罰」と捉える傾向が支配的だった。そのため、ドイツの再統一という発想はタブーであり、考えられないことだった。コール氏が両ドイツの再統一を主張し出した時、政治家や知識人たちの間から「戦争犯罪を否定する考えだ」といった批判の声が飛び出したという。
コール氏は戦後の「戦争犯罪による民族刑罰論」を脱皮し、ドイツ民族の再統一を主張し、それをやり遂げた。コール氏が「ドイツの戦争犯罪刑罰論」から抜け出すことが出来た主因は、同氏がナチス・ドイツ政権と全くかかわりのない戦後初めての政治家だったということもある。
シュピーゲル誌にはまだまだ多くのエピソードが紹介されている。それを知ると、コール氏という政治家を身近に感じだす。コール氏は偉大なドイツ政治家だったが、それだけではない。非常に愛すべき人間だったことが理解できる。
ただし、コール氏は41年間連れ添ってきたハンネローレ夫人を不幸なことで亡くして以来、再婚した現夫人のマイケ・コール・リヒター夫人に余りにも依存してしまった結果、2人の息子さんやその孫との交流は閉ざされ、長男のヴァルター・コール氏は、「父親の死を運転中のラジオニュースで知った」というほど父親と2人息子の家族とは意思相通が完全に途絶えていた。亡くなった父親を慰問するために実家を訪ねたヴァルター・コール氏の家族は門前払いされている。
家庭内の問題は部外者があれこれ言えないが、コール氏は政治の世界に生きてきた人間だった。家庭内の交流が欠けていたのかもしれない。その点、本人も含め家族にとって寂しいことだったろう。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年6月26日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。