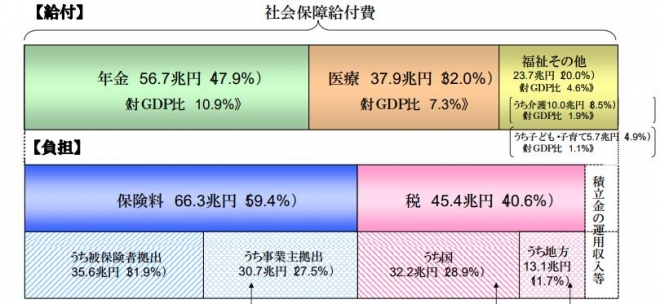10年前の話になるが、東野圭吾の推理小説で、ガリレオシリーズの『容疑者Xの献身』が大ヒットした。原作は各賞を受け、映画も好評だった。台湾、香港で中国語版が公開され、非公開だった大陸でも海賊版がネットで流れ、それをみた多くの若者が東野圭吾ファンになった。私のいる大学でも、文学部の教授が「最近の中国の学生は東野圭吾ばかり読んでいて、古典を読んでくれない」とこぼすほどだ。
私の先学期のクラスでも、同作品の評価を論じた男子学生がいた。私は原作を読んでいないが、映画のあらすじは次の通りだ。

高校教師をしているが、人生の生きがいを見失った優秀な男性数学者、石神哲哉(堤真一)が、自殺をしようと首に縄をかける。ちょうどそこへ、引っ越してきたばかりのアパートの隣人が呼び鈴を鳴らす。女児を連れた女性、花岡靖子(松雪泰子)だった。闇夜を照らす明りのようなその笑顔に、石神は救われる。靖子は元ホステスで、小さな手作り弁当のお店を開いて生計を立てている。前夫は暴力を振るって金銭をたかるチンピラだ。
石神の靖子への思いは、愛情と呼ぶには淡い感情だったが、彼にとっては初めて抱く愛情だったのだろう。その気持ちにすがって、彼は生きる一縷の望みを得る。一人暮らしの石神は毎日、靖子に会うために彼女の店で弁当を買い求める。薄幸の男女が、砂漠のような都会の片隅で、奇跡的な出会いをする。
ある晩、靖子を訪ねてきた元夫から暴力を振るわれ、靖子と娘は抵抗しているうちに殺してしまう。薄い壁から物音を聞いた石神は、母子を救おうと、完全犯罪を計画する。翌日にホームレスを殺して、それを元夫に見せかけ、彼女たちのアリバイを偽装するのだ。恋愛の経験がない石神には、こうした形でしか愛情を表現するすべを知らない。最後は、石神の学生時代のクラスメートで、物理学者の湯川学(福山雅治)が、数学のパズルを解くように、完全犯罪を解決していくというストーリーだ。
中国ではその原作に基づき、中国の俳優を使って撮ったリメイク版が今年3月、公開され、話題になった。ネットでの評価は中の上程度で、チケットの売り上げは4億元を超えたので、ヒット作と言ってよい。気になっていたが映画館に行くチャンスがなく、先日、ようやく中国の動画サイトで公開されているのをみた。


感想は二点。
まず、都会の希薄な人間関係や心の病、さらにはホームレスの存在など、現代中国(大陸)の都市部では、すでに日本と同様の社会現象が普遍化しているのだという実感だ。同じ社会背景がなければ、深い感情を共有することはできない。リメイクにタイムラグが生じたのも、当時はまだ、多くの中国人がストレートに共感できる社会的背景の乏しかったことがあげられるだろう。この10年の変化はかくも大きいということである。
中国には、日本のような手土産をもって引っ越しのあいさつをする習慣がないので、中国版では、隣人の女児が学校のチャリティーに出す古本を提供してもらうため数学者の家をお願いに訪れる、との設定になっている。それ以外は、中国でも個人経営の弁当店はあちこちにあるし、クラブのホステスも職業として存在しているので、社会背景として違和感がない。家庭内暴力も大きな社会問題となっている。
一方、作品の内容に関する感想は、チケットの売り上げとは矛盾するが、かなり厳しい採点をせざるを得ない。登場人物がみな「まとも過ぎる」のだ。中国版では、日本版の湯川学に当たる役が、警察研究機関の学者になっている。そのため、正義を代表する型にはまってしまって、「非正統」の感じがない。あくまで自分の学問の趣向として難事件を推理する独自のスタイルがないと、湯川学の味わいが出ない。勧善懲悪一辺倒では、ガリレオが生かされない。
中国版の靖子役も、薄幸の感じが全く出ていないので、リアルさに欠け、非常に白けた印象を与える。社会の底辺で暮らす者の明るさと暗さの双方を演じなければならない、要の役柄だ。身近の映画ファンに聞いたら、女優は監督の友人として友情出演しただけなので、演技はさほどうまくない、とのこと。こういう私情がはさまるとせっかくの作品も台無しだ。
そして、本作品において最も重要な数学者の役。中国版でも、数学にしか関心がなく、世間との接点を持つことのできない孤独さは好演されていると思う。だが、物語の核心である、隣人の女性への特殊な感情が十分に描かれていない。好意を寄せる相手の目をじかに見ることもできない臆病な心、それでいて、自分を死から救ってくれた、隠しようのない愛情がこぼれ落ちてくる。この点では、堤真一の演技が圧巻だ。ラストシーンの警察署での号泣は、ゆがんだ愛情の苦悩が、迫真の演技で表されていた。むしろ、彼の好演が、リメイクを色あせたものにしていると言ったほうが良いかもしれない。
もともと、中国に石神哲哉のような内向的な性格の男性が少なく、「非正統的」な感情への理解が十分でないことも一因かも知れない。「宅男」は中国でも急増しているとは言え、オタク文化発祥の日本には、こうした男性が少なくない。こうなると文化的な問題なので、優劣では論じられなくなる。
ともかくも、中国版をみて、堤真一と松雪泰子の好演を改めて見直すことができたのは収穫だった。もう一度、日本版の『容疑者Xの献身』をみたくなった。
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年9月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。