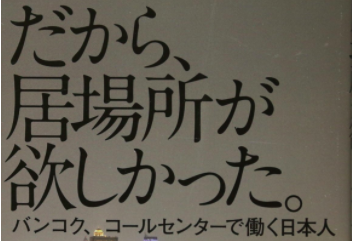中央軍事委員に出席した習近平氏(新華社より引用:編集部)
25日の第19期中央委員会第1回全体会議(1中全会)では中央軍事委員会の新指導部も選出された。習近平が主席を続投する一方、副主席には制服組の許其亮と張又侠の2人が留任し、文官の任用はなかった。従来11人だったメンバーも7人に減らされ、権力の集中を図った。18回党大会で常務委員が9人から7人に縮小され、権力の分散による分裂を避けたのと同じ理屈だ。
注目の人事は、中央軍事委入りの不文律だった大将クラスの条件を破り、昨年、中将に昇進したばかりの張昇民(59)を抜擢したことだ。陝西省出身の同郷で、習近平との縁が深いと思われる。習近平は今年1月、張昇民を中央軍事委規律検査委書記に任用し、綱紀の緩んだ軍内を立て直す重責を与えた。
共産党の権力の源泉は軍の掌握にある。党・国家のトップになるためには、あらかじめ中央軍事委副主席として準備をするのが慣例だ。そこが空席になったことは、後継者不在、つまり習近平の長期政権を端的に物語っている。
習近平の経歴からはっきりわかるのは、豊かな軍経験だ。清華大学を1979年に卒業後、国務院弁公庁に入り、当時、副総理兼国防部長だった耿颷(こう・ひょう)の秘書を務めて以来、河北・福建・浙江・上海の各地方を歴任しながら常に現地軍区の肩書も持ち続けた。総書記に就任する2年前の2010年、すでに中央軍事委副主席に就任している。軍の創設に参加し、それを育てた革命世代の二代目、紅二代の強みがある。
習近平の父親、習仲勲は文革後に名誉回復し、広東省のトップとして改革・開放政策をリードした。その際、陝西出身で、南方に全く縁のない習仲勲を支えたのは、広東一帯を牛耳っていた戦友の葉剣英(人民解放軍総参謀長、国防部長などを歴任した軍の重鎮)だった。習仲勲は軍の力を深く知っており、あえて息子に、官途の第一歩として国防部長の秘書をお膳立てしたのである。
軍の要職には紅二代も多い。こうした長い軍との関係があって初めて、習近平は政権掌握後、江沢民が登用した徐才厚、郭伯雄の中央軍事委副主席経験者2人を相次ぎ腐敗問題で摘発できたことは、間違いない。
江沢民は15年にわたって中央軍事委主席を務め、軍内に大きな影響力を温存した。総書記の座を胡錦濤に譲った後も、2年近く中央軍事委主席の椅子に座り続け、胡錦濤を牽制した。権力基盤としていかに軍の存在が大きいかを物語る。しかも、2004年9月、江沢民は完全引退に際し、胡錦濤に対し「重要事項は江沢民に相談する」との密約まで結ばせた。習近平が、江沢民による軍支配を打破した力は並大抵ではない。
今回の最高指導部人事について、私は少し前、ボードに書かれた名簿を見せられたことがある。習近平に「党主席」の肩書がつき、李克強首相に続き、胡春華・前広東省党委書記と陳敏爾・重慶市党委書記が入っていた。首をかしげたのは、栗戦書が規律検査委書記、胡春華が副首相と中央軍事委副主席を兼ねていたことだった。
中央の経験が乏しい栗戦書が、王岐山が残した重責を担うのは荷が重すぎるし、習近平にとっては、恩人にかなりの政治的リスクを背負わせることになる。これは考えにくい。さらに、胡春華を中央軍事委副主席として、後継指名を確定させるかのような人事もあり得ないと思った。私の判断は「偽物」で、少なからずそのリストを見た党関係者も否定的だった。党大会前はさまざまなリストが飛び交うので、注意しなければならない。軍人事は一つの大きな目安になる。
胡春華の中央軍事委副主席説に接し、前回の第18回党大会でのある記憶がよみがえった。胡錦濤が総書記と中央軍事委主席を同時に退く条件として、子飼いの李克強を中央軍事委副主席に就任するよう求めたという伝聞だった。胡錦濤と同じ共青団畑で、軍にまったく足場のない李克強の権力は、軍に幅広い人脈を持つ習近平とは比べ物にならない。せめて副主席の肩書があれば、拮抗することができる。実現はしなかったが、胡錦濤が親心としてそう考えたのだろう、と当時は受け取った。
新たな政治局員の経歴をみても、習近平と軍人を除き、過去にも現在にも軍での肩書を持っている者は見当たらない。憲法で国家主席の三戦は禁じられているので、5年後、習近平が国家主席を退くことは必至だが、それに先立ち、中央軍事委主席の座をいきなり軍経験のまったくない後継者に譲るとは思えない。権力の安定を考えれば、無謀な人事となる。軍人事からも習近平政権の長期傾向が見て取れる。
(続)
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年10月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。