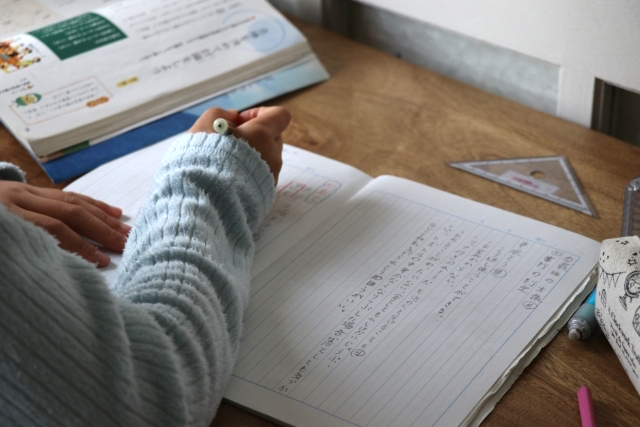「姨媽的後現代生活」ポスター(Wikipedia:編集部)
中国の知人に勧められ、許鞍華(アン・ホイ)監督の映画作品「姨媽的後現代生活」(邦題「おばさんのポストモダン生活」2006年)を観た。東京国際映画祭でも上演され、2008年の第19回福岡アジア文化賞で大賞を受賞している。許監督は中国人の父と、日本人の母を持つ。遼寧省鞍山市で生まれ、幼少期に家族とともに香港に移住した。
作品の主人公もまた、中国東北出身の女性だ。退職後、夫と娘を捨てて大都会の上海に移り住み、かつて習った英語を生かして家庭教師をする。多少なりとも文化水準を持った東北の女性にとって、上海はあこがれの大都会だ。偶然出会った男性と恋愛をするが、結局、相手はペテン師で、利用されただけだった。農村からの出稼ぎ女性に同情して家政婦に雇うが、価値観が違い過ぎてうまくいかない。最後は大けがをして入院し、田舎から娘が身を引き取りに来て、元通りの生活に戻る。女性の自立、都市と農村の格差、現代的生活の刺激と落とし穴、そんな時代背景が淡々と描かれている。
正直なところ、深い感動はなかったのだが、主人公の女性と男性ペテン師がやり取りをするくだりが印象に残った。大きな時代のうねりの中で、個々人の運命は大海に漂う小舟のように見える。そこで、ペテン師が蘇軾(蘇東坡)の詩を引用し、これ見よがしに言う。「長恨此身非我有」。わが身がわが身であってわが身でないかのような感じが恨めしい、との感慨である。
蘇軾の詩『臨江仙』は、彼が北宋の首都・開封での政治闘争に敗れ、湖北省に左遷された時代に書かれた。全文は以下の通りだ。
夜飲東坡醒復醉 夜東坡に飲んで 醒めては復た醉う
帰来彷彿已三更 帰り来れば 彷彿として已に三更
家童鼻息已雷鳴 家童の鼻息 已に雷鳴す
敲門都不応 門を敲けども都て応えず
倚帳聴江声 帳(とばり)に倚って江声を聴く長恨此身非我有 長に恨む 此の身の我が有に非ざるを
何時忘却営営 何れの時にか 営営たるを忘却せん
夜闌風静穀紋平 夜闌(た)けて風静かに 穀紋(こくもん=さざ波)平らかなり
小舟従此逝 小舟此より逝きて
江海寄余生 江海に余生を寄せん
「東坡」は、蘇軾が名付けた寓居だ。東の坡(ば=丘)にあることからそう呼んだ。憂鬱を晴らそうと、そこで酒を飲む日が続いたのだろう。酔っては覚め、覚めてはまた飲む。もう真夜中で、下男も高いびきで寝ているから、戸をたたいても全く気づかない。やむなく帳に寄りかかって、川の水音に耳を澄ますしかない。恨めしいのは、自分が自分であって自分でないことだ。いったいいつになったら、こんな追い詰められたような、あくせくした暮らしを忘れられるのだろうか。夜は更け、風も静まって、川面のさざ波も消えている。小舟を漕ぎ出し、何の憂いもない広大な海で余生を送りたい。詩人はそう叫ぶ。
蘇軾は40歳後半で都落ちはしたが、まだ官途への未練がある。自ら田畑を耕し、飢えをしのぐ暮らしを送りながら、夜になると迫ってくる孤独や憂鬱を酒でごまかそうとする。だがいくら酔っても出口は見つからない。意のままにならぬこの身が、もはや自分のものだとは感じられない。荘子は「汝の身は汝のものではない。天地の定めである」と説いたが、そこまでの境地に達するのは容易でない。
我が身を振り返れば、もとより名利へのこだわりもなく、あくせくした感じからも解き放たれている。天地の定めとは言えないまでも、縁による天命を感じることはある。酒は憂さを晴らすものではなく、楽しみや喜びを深めるものだ。だが、憂患の意識が薄れているわけではない。目はさえている。50も半ばに達し、ようやくわが身を友とすることができるようになった。そんな気がする。冒頭の映画に深い共鳴がなかったのは、老いのせいなのか。
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年12月12日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。