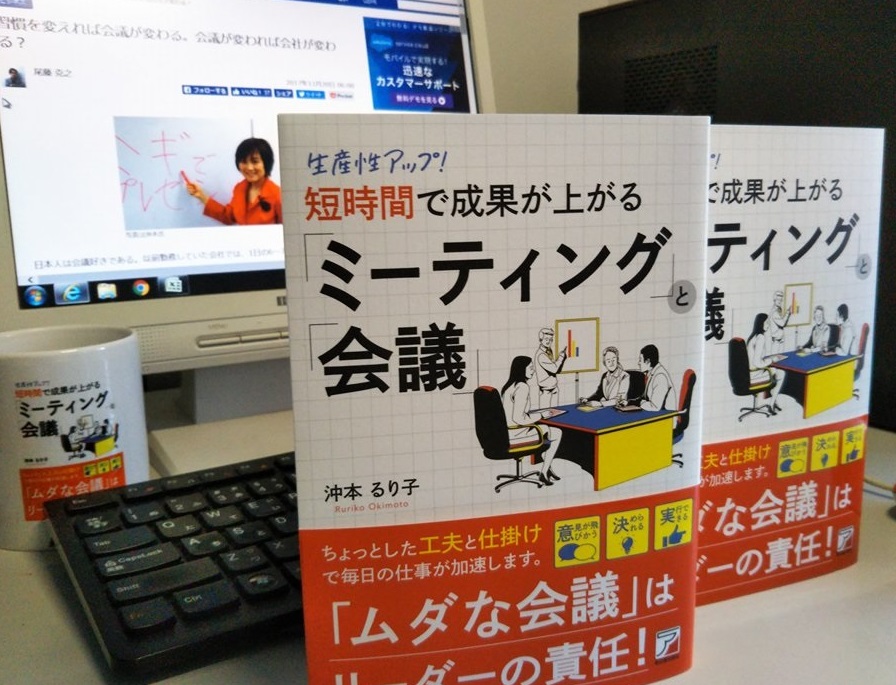范東昇学院長は四川省内江市の范長江記念館を訪れ、父のいくつかの遺品とともに邦訳『中国の西北角』(松枝茂夫訳、改造社、1938年)の初版を贈呈した。関係者が集まった正式の式典が行われ、公式報道もされた。思いもよらなかったが、私も不在ながら、寄贈者として感謝状まで受けた。


さらにおまけがついて、私は学内メディアからも追いかけまわされたが、私は自分のことではなく、人の「縁」について話した。
邦訳がなぜ生まれたか。1983年再刊(筑摩叢書版)の「解説」に、訳者の中国古典文学者、松枝茂夫が書いている。気が付けば、私の書棚には、松枝茂夫編訳の中国古詩集が並んでいる。その松枝が生々しいルポルタージュの翻訳をしたのは、当時、改造社にいた増田渉に「面白いから訳したらどうか」と勧められたからだという。増田渉は後に魯迅研究でその名を残す。
松枝「解説」いわく、
「昔からノンポリの私は最初あまり気乗りはしなかったが、生活のためにやってみることにした……たしか四十日あまりかかって一気に訳了したと思う。別に投げやりにしたわけではない。訳しているうちに著者の熱気にあおられて、我にもなく興奮してしまったのだ」
松枝は初版の序で、
「図表を種にして机上ででっちあげたものでなく、文字通り足で書かれた人生記録だ」
「その深い学識と卓越した政治理想は彼が単なる一介のジャーナリストでないことを窺わしむるに足る。しかも字裏行間に燃え上がっている著者の烈々たる民族精神は読者を振い立たせずにはおかないものがある」
と激賞している。、
解説によると、邦訳は3000部刷ったというから、記念館に寄贈されたのは三千分の一ということになる。松枝、増田という二人の若者、後に日本を代表する中国文学研究者が、見たことも、会ったこともない中国人ジャーナリストに惹かれ、もっぱら中国への深い関心に突き動かされて一冊の邦訳を生んだ。それが日中の戦争、国交回復をはさみ、80年後、ようやく作者の故郷に戻った。その過程に、私と范院長という日中の元記者がかかわっている。私は昨年、范院長と出会い、彼の推薦を経て現在の職場にいる。
しかも、増田が魯迅と知り合ったのは、当時、上海にあった内山書店の店主、内山完造の紹介を通じてだった。初版の古本が東京神田に移った内山書店に蔵されていたことを思えば、奇縁はさらに深まる。
それぞれの縁はバラバラで、どうしてそこに現れたのかわからない。気付かないまま、ふとそこにある。だが、それ自体に価値があるのだ。だから、縁が見えない糸によって結びついていくと、その価値が次々と導き出される。問いかけはまだ続いている。内山書店に、あんなにも大切に蔵されたものを、当初はいったい誰が守っていたのか。扉にある丸印はだれのものか。縁とはかくも興味深く、尊い。
中島みゆき『糸』の歌詞を思い出した。
なぜ めぐり逢うのかを
私たちは なにも知らない
いつ めぐり逢うのかを
私たちは いつも知らない
どこにいたの 生きてきたの
遠い空の下 ふたつの物语
縦の糸はあなた 横の糸は私
織りなす布は いつか誰かを
暖めうるかもしれない
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年12月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。