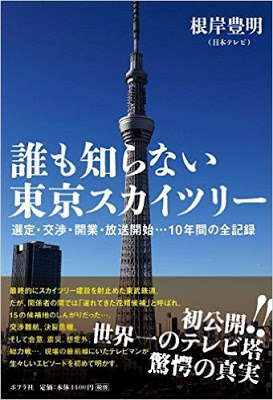スイス、ローザンヌ。故モーリス・ベジャールが手掛けた舞台「第九交響曲」再演のため、モーリス・ベジャール・バレエ団のダンサーたちは、厳しい練習に励んでいた。才能あるソリストのカテリーナは、第2幕のメインを務める予定だったが、妊娠が発覚し、役を降りることに。一方、共にステージを作る東京バレエ団のダンサーたちもまた、厳しい稽古に励んでいる。人種も国籍も言語も文化的背景も異なるダンサーたちが、ベジャールとベートーヴェンの遺志を継ぐために、ひとつのステージへと向かっていく…。
故・天才振付家モーリス・ベジャールが手掛けた伝説の舞台「第九交響曲」再演の舞台裏を描くドキュメンタリー「ダンシング・ベートーヴェン」。「第九交響曲」をバレエで表現するというだけで野心的な内容だと分かるが、ベジャール亡き後、長く封印されてきたそのステージが、今、復活するのは、許しあうこと、つながることが異文化への愛と尊敬を生み、融和へと導くという、極めて現代的なメッセージが必要とされているからだ。ダンサー、合唱団ら総勢350名によるビッグプロジェクトが、東京公演に向かって、徐々に盛り上がるプロセスは、見ているこちらも自然と興奮させられる。
ナビゲート役でインタビュアーは、ベジャールの後を継いだ芸術監督ジル・ロマンの娘である女優のマリヤ・ロマン。彼女によって、ダンサーたちの内面の苦悩や喜びに迫っていく構成が上手い。妊娠によって役を降りたカテリーナはキャリアの中断への不安と子どもへの愛情の間で揺れ動き、彼女のパートナーで同じくダンサーのオスカーは良き父親になろうと決心している。またインタビューを行うマリヤの両親もまた、ダンスと結婚、子育てについて語り、バレエへの情熱と共に、人生や幸福についても考察している。だからこそ映画は、「第九交響曲」が持つ友愛というテーマに深くつながっていくのだ。監督を務めるのは、「ベジャール、そしてバレエはつづく」のアランチャ・アギーレ。ラストのステージは圧巻のパフォーマンスで、華やかさと力強さが融合した美に魅了された。名匠ズービン・メータ率いるイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団の音楽も素晴らしい。この伝説のステージに、日本のダンサーが重要な役割を果たしていることに、誇らしさを感じる。
【70点】
(原題「DANCING BEETHOVEN」)
(スイス・スペイン/アランチャ・アギーレ監督/マリヤ・ロマン、エリザベット・ロス、ズービン・メータ、他)
(洗練度:★★★★★)
この記事は、映画ライター渡まち子氏のブログ「映画通信シネマッシモ☆映画ライター渡まち子の映画評」2017年12月24日の記事を転載させていただきました(アイキャッチ画像は公式Twitterから)。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。