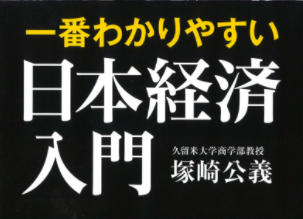シリア人の青年カーリドは戦乱のアレッポを逃れ、生き別れた妹を探しながらいくつもの国境を越えて、フィンランドの首都ヘルシンキにたどり着く。難民申請をするが受理されず、移民収容施設から逃亡したカーリドは不法滞在者となるが、スキンヘッドのネオナチに襲われゴミ捨て場で寝泊まりしているところを、レストランのオーナーのヴィクストロムに助けられる。人生をやり直そうとしているヴィクストロム、風変わりだが気のいい従業員らは、淡々とカーリドを助け、ついに妹とも再会を果たす。だが、そんなカーリドの前に再びネオナチが現れる…。
シリア難民の青年が壮年のレストランオーナーと出会って絆を育む人間ドラマ「希望のかなた」。フィンランドの名匠アキ・カウリスマキ監督が「ル・アーヴルの靴みがき」に続いて難民を描く、難民3部作の第2弾だが、本作はより過酷な現実を描き、反骨を込めた静かな力作に仕上がっている。カウリスマキ作品のトレードマークである、無表情の登場人物たちのとぼけたおかし味は健在。少ないせりふと無駄のない構図、独特の寒色系の色彩に、フィンランドのベテランミュージシャンが奏でるダサかっこいい音楽、毎度おなじみの犬(監督の愛犬ヴァルプ)が、完璧なアンサンブルを構成し、唯一無二のカウリスマキ・ワールドを形作っている。オフビートなエピソードで笑いを提供するのが、今回はヘンテコな寿司だったのが最高にウケた。
ほとんど表情を変えずに過酷な人生を淡々と語るカーリドは誇り高い人間だ。そんな彼を、にこりともせずに助けるヴィクストロムら周囲の人々の優しさが素敵すぎる。彼らがやがて擬似家族のようになる姿に心が温まるが、一方で、官僚主義の塊のような役人や移民排斥の極右ネオナチの存在を描いて、シビアな現実からも目をそらさない。無償の善意と残酷な暴力が同居するのがヨーロッパの“今”なのかもしれない。カウリスマキは、差別や偏見にNOと叫び、つつましく生きる市井の人々の優しさにYESと言っている。私たち観客は、誰かを助けるその勇気に感動する。物語の余韻はビターなものだが、その先にはきっと希望があると信じたくなる作品だ。
【75点】
(原題「TOIVON TUOLLA PUOLEN/THE OTHER SIDE OF HOPE」)
(フィンランド/アキ・カウリスマキ監督/シェルワン・ハジ、サカリ・クオスマネン、イルッカ・コイヴラ、他)
(ビタースウィート度:★★★★★)
この記事は、映画ライター渡まち子氏のブログ「映画通信シネマッシモ☆映画ライター渡まち子の映画評」2017年12月28日の記事を転載させていただきました(アイキャッチ画像は公式Twitterから)。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。