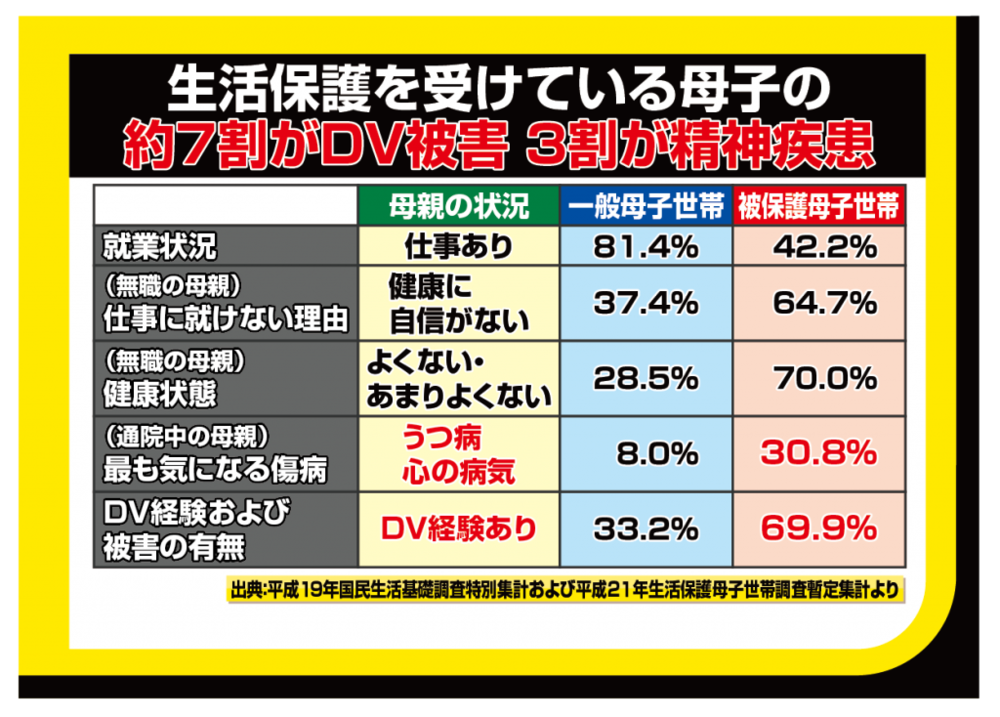丸山眞男が、1969年の東大紛争で研究室を荒らされた後、全共闘の学生たちに「君たちのような暴挙はナチスも日本の軍国主義もやらなかった」と述べたことは、有名である。
全く不謹慎な表現である。第二次世界大戦の死者は、推計5,000万人以上、ナチスによる凄惨な虐殺の被害者は推計500万人以上という規模だ。一人の大学教授の研究室の本が読めなくなったことなどが、それを上回る暴挙であるはずはない。丸山の発言は、日本の知識人がいかに世界情勢に疎く、独りよがりのレトリックに沈殿していたかを示す象徴例だ。
逆に言えば、日本の知識人が言う「戦前の復活」「ナチスの再来」などは、大学教授の研究室が荒らさられる程度にも酷いことではなく、いわば頻繁に起こっている日常的なことでしかない、ということだ。そのレトリックは、国際的には使ってはならないタブーだとしても、日本ガラパゴス島の知識人でいる限りは大した問題にはならないので、憲法学者らが毎日毎日せっせと他人を罵倒する際に使っている、それだけのことにすぎない。
「立憲主義の破壊」などといった大仰な言葉も、ふたを開ければ、東大法学部出身者ではない者を内閣法制局長官にした、といったレベルの話でしかない。このことを、たくましい想像力によるものだとみなすか、枯渇した感性によるものだとみなすかは、どちらでもいい。本来は、知識人層は、「アベ政治を許さない、と唱えれば、君も立憲主義者だ」、のような話を延々と続けるだけの態度を、恥じるべきだ。少なくとも、もう少し物事を長期的に、できれば本質的に、見た話をするべきだ。
憲法学会の「隊長」・長谷部恭男教授は、「国民には、法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかない」と述べる。そして、社会契約論を否定する(『憲法と平和を問い直す』[2004年])。残っているのは憲法学者による独裁制だろう。拙著『ほんとうの憲法』では、このような憲法学者の独裁主義は、日本国憲法の否定である、と論じた。
日本国憲法に「三大原理」なるものがあり、その一つが「国民主権」であるというのは、1960年代に小林直樹・東大法学部教授らによって憲法学会の通説になり、学校教科書などに入り込み、社会に浸透した。しかし憲法典を素直に読めば、そのような読解は自然ではない。憲法が「基く」「人類普遍の原理」とは、人民の人民による人民のための「国政は、国民の厳粛な信託による」という考え方である。「信託(trust)」の解釈にはニュアンスがあっていいだろうが、社会契約の論理の完全否定は、致命的な反立憲主義だ。
現在、日本は、低経済成長が常態化する中、巨額の財政赤字を膨らませ続けながら、人口減少時代に突入しようとしている。これこそが現在の日本の立憲主義の本質的危機であることを、知識人層は、きちんと説明すべきだ。
立憲主義は、「信託」に基づく「責任政治」によって成り立つ。社会構成員は、自分の権利を守り、安全を確保し、さらに幸福を追求するために、そのための環境の整備という任務を政府に与え、「国政」を「託す」。定期的にチェックし、不備があれば政府を取り換える仕組みを維持しつつ、責任を持った活動を行わせるための「信託」は行う。
もしそうであれば、政府の活動に必要な経費は、社会構成員が負担するのが当然である。事業委託者は、費用負担を前提にして、事業受託者に、業務遂行を委託する。受託者(実施者)による契約不履行の場合、委託者(発注者)が契約を破棄できるのは、費用負担していればこそである。逆に、委託者(発注者)が費用を負担しないなら、受託者(実施者)は、事業の実施を拒絶する。それが契約というものだ。
イギリスやアメリカの古典的な立憲主義体制においては、選挙権は、財産=納税の有無によって制限されていた。自治の論理を純粋に追求すれば、納税の有無が決定的な要因であってもやむをえなかった。後に民主主義的価値観の広がりにより、納税能力を選挙権の制限に適用することは廃止され、累進課税や法人税の考え方も発展したが、「契約」関係を重視する立憲主義の考え方は、英米社会では消えなかった。
現代世界において、天然資源を豊富に持つ「レンティア国家」で立憲政治が育たないのは、税金徴収を媒介にした「契約」関係に基づく責任政治が育たないからだと考えられている。たとえば石油収入だけで政府を運営することができ、国民も石油収入のおこぼれにあずかることだけを求めているような社会では、立憲政治は非常に難しい。政府は、石油市場への責任政治を重視しがちになるからだ。
また、国家収入のほとんどが外国からの援助で占められているような場合も、税金徴収を媒介にした「契約」関係に基づく責任政治が育たない。対外援助が恒常的なものであってはならないとされるのは、そのためである。政府は、援助提供者への責任政治を重視しがちになるからだ。
もう一つ、立憲主義に、天然資源や対外援助と同じ効果をもたらすのは、借金である。政府が借金漬けになれば、政府は債権者への責任政治を重視しがちになる。
日本の財政赤字をめぐっては、国債の暴落はあるか、という点に議論が収れんしがちである。そして政府保有資産額や国内債権者比率の評価の話になる。しかし立憲主義の観点から問題なのは、国債暴落の有無だけではない。そのような議論が蔓延しているということ自体が、本来の立憲主義の責任政治の観点からは問題なのだ。社会構成員が、少なくともその能力に応じて、社会を運営する活動に貢献して初めて、政府に責任政治を求める契約関係が発生する。政府資産の評価額や、国債保有者の国籍などは、関係がない。
心ある立憲主義者は、国債発行額のさらなる圧縮を目指し、財政健全化のために、知恵を絞るべきなのである。政党間対立は、そのための政策的競争を促すための誘因とするべきなのである。政権交代は、複数の方法を試してみるための制度的な保障とするべきなのである。
このような話をすると、9条改憲をすると軍事費が増大して、財政赤字が拡大する、といった憲法学者らの声が聞こえてきそうである。しかし9条改憲それ自体と、財政赤字には、論理的な連動性がない。「改憲はナチスの再来だ」といった自己催眠にかかる場合にのみ、連動性があるように感じられてくるだけだ。
むしろ国会議員を不毛なイデオロギー論争やパフォーマンス競争から解放し、真摯な政策論に専心させるためには、9条解釈を確定させることが望ましい。「立憲主義とは、アベを許さないということだ」といった低次元の扇動だけを繰り返すのではなく、もっと社会的問題の本質を論じていく努力を払うべきだ。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2018年1月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。