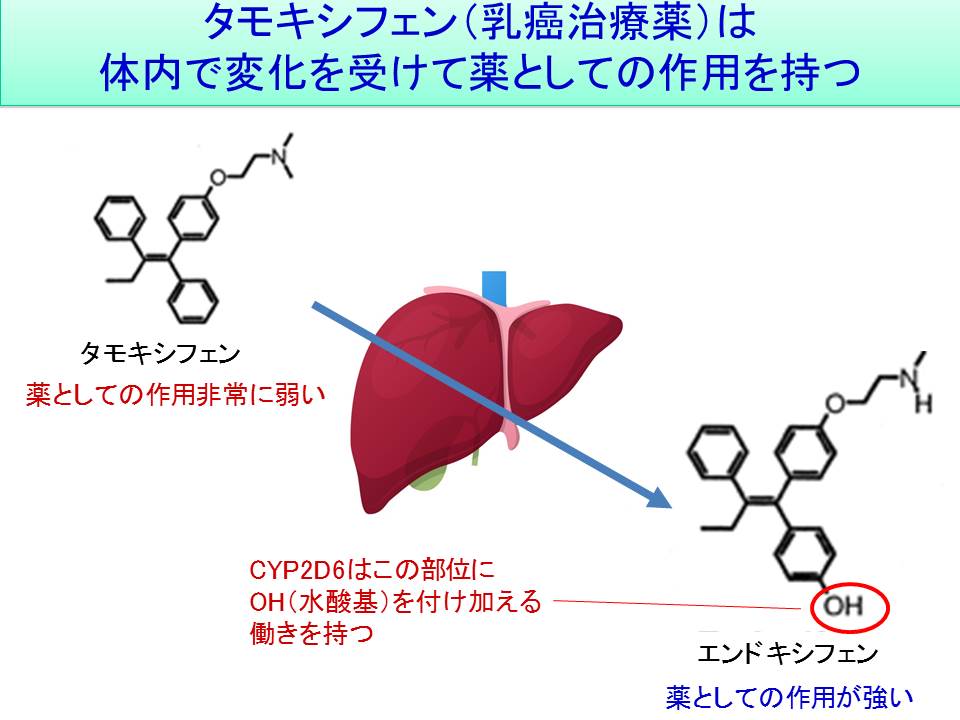小室哲哉さんを引退に追い込んだ週刊文春に対する世論が厳しくなりそうな雲行きだ。すでにツイッターでもハッシュタグ「#週刊文春を許さない」の運動も起きている。
どうして不倫と決めつけて報道したのか。ご本人は会見でC型肝炎と闘っていると公表。24時間体制で訪問看護を依頼していると。恥ずかしながら性欲は減退していて女性と云々という欲はないと、そんなことまで言わせて。何が楽しい?悲しくて仕方ないよ。
— m (@774moexxx) 2018年1月19日
やはり、小室さんや妻のKEIKOさんを取り巻く状況はおおかたの予想よりも深刻だったことが明らかになったことが大きいのだろう。きのうアゴラで速報的に書いたのは記者会見の詳報が流れる前のことで、オピニオンサイトでは最速だったようだが、その後、小室さんの記者会見の一問一答を読むにつれ、気の毒でしかなく、「自分が小室ファンなら文春に怒るだろうな」と思えた。
【全文1】小室哲哉が不倫騒動受けて引退発表 会見冒頭で夫婦生活を述懐「会話のやりとりがKEIKOとできなくなった」 https://t.co/vrf5b48Kh5
— logmi [ログミー] (@logmijp) 2018年1月19日
KEIKOさんの病状が「高次脳機能障害」だったことについて、週刊文春の当該記事を読むと、医師への取材などで取材時に想定していたことはうかがえるが、ここまでの状況からすると、「病気の妻を裏切った不逞の夫」シナリオありきで踏み込み過ぎたようだ。昨日も書いたように、著名人であろうと、不倫があろうと公益性はない。
実は最近、週刊文春の最盛期を築いた元編集長の花田紀凱さん(現「Hanada」編集長)と、門田隆将さん(元週刊新潮デスク)の対談本「『週刊文春』と『週刊新潮』闘うメディアの全内幕」(PHP新書)を読んだばかりで、書評を書こうとしていた矢先での引退報道だった。
花田さんは産経新聞での週刊誌評で、現編集長の新谷学氏にときおり苦言しているが、本書でも新谷編集長に直接「芸能ネタが多すぎる」「AKBの女の子がデートしたっていいじゃない。年頃なんだから。それを、夜の夜中に、大の男ども四、五人が張り込んで、そんな写真を撮ってどうなるの」と言ったことがあったと明らかにしている
芸能取材のエース級人材を補強し、「ゲス不倫」などのキラーコンテンツを仕掛け、週刊誌が売れない時代に“文春砲”ともてはやされるまでに同誌のプレゼンスを高めた新谷編集長の手腕自体は“見事”だといっていい。さらに(同書でも紹介されているが)芸能ネタをネットやワイドショーに提供するコンテンツとしてマネタイズに成功しているところもまた新谷文春の評価をあげてきたことも事実だ。
一方、残酷極まりない犯罪を起こした少年の実名報道に踏み切るなど、「本流」で勝負してきた花田さんの言葉を借りると、本書での苦言はそのまま今回のケースにも当てはまる。
週刊誌のスクープが芸能ネタばかりでいいとは思わないけど、それで潤うとなれば、狙いたくなる気持ちもわからないではない。しかし、スキャンダルがお金になるからと、そればかりを追いかけて雑誌の方向性が歪んでしまうのだとしたら、あまり褒められた話ではありませんね。(21ページより)
だけど、こういうことをやっていると、やめられなくなります。それは自らの首を絞めることになる。『週刊文春』が生き残っていくためには、ぼくも方針転換したほうがいいと思います。今のようなネタをやるのだったら、別の媒体でやればいい。たとえば、ネットだけでやるとか。(137ページより)
おそらく、現在の現場を預かる新谷編集長や取材に当たった記者・カメラマンたちは、「いまの現場の苦労を知らない爺さんが何を言っているのやら」という反発心を覚えるところだろう。あるいは「週刊誌への批判なんて昔からあったことで、今回も時間が経てば忘れ去られるに決まっている」とタカをくくっているかもしれない。
まあ、それくらいの鼻っぱしが強くなければ、週刊誌稼業などできないだろうが、今回の件が“やぶ蛇”になるのではないかと感じるのは、週刊誌に対する法規制が結果として強まることへの懸念だ。小室ファンなどが一時的に不買運動をする程度ならまだいい。問題は小室さんに同情する世論を隠れ蓑にして、公権力側に付け入られる機運を作りかねないことにある。
本書では、名誉毀損訴訟の賠償がどう高額化されてきたかの経緯を含め、新聞やテレビがだらしないときに権力者を戦慄させるスクープを放ってきた週刊誌を、公権力側が隙あらば規制しようとしてきたことも警鐘的に語られている。小室引退は「ポスト平成」における週刊誌ジャーナリズムのあり方を左右するのではないか。