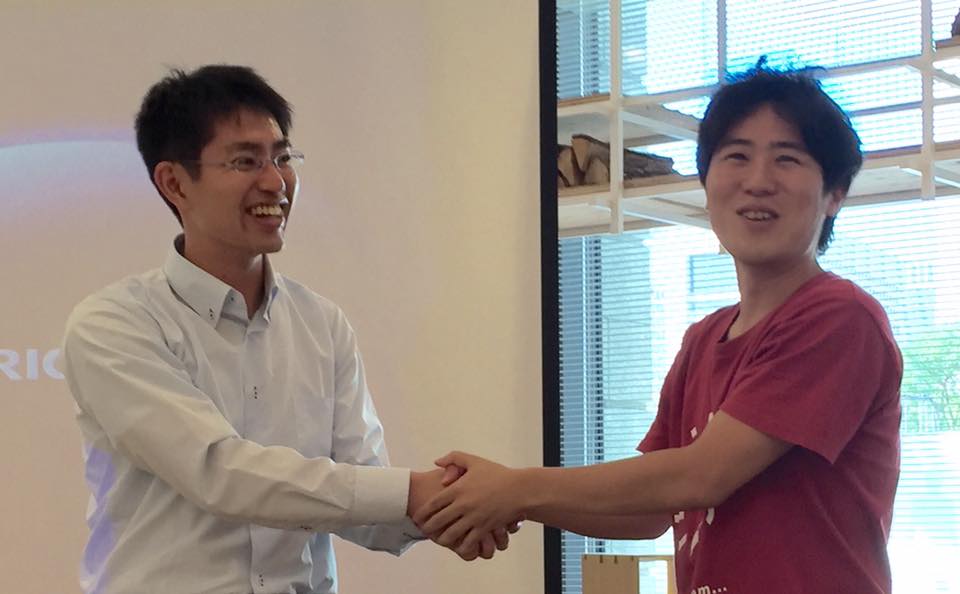次に、がんの遺伝的要因について話を進めたい。日本では、十分な遺伝学教育、特に病気と遺伝子の関連性に関する教育、が欠けているため、がんの発症に決定的な役割を果たす因子(決定因子)とがん発症の確率をわずがに高める危険因子が混同されることが多い。専門家と称する人たちでも、この点が識別されていないことが多い。まず、決定因子の話から進める。
特定の遺伝子に変異があると非常に高い確率でがんを発症する疾患(決定因子による遺伝性がん)としては下記の例などが挙げられる。これらの原因遺伝子に異常があっても、家族性大腸腺腫症(ほほ100%の確率で大腸に多数のポリープが生ずる)を除いて100%の確率でがんを発症するわけではない。比較的確率が高いBRCA1/BRCA2異常の場合でも、生きている間に乳がん・卵巣がんを発症する割合(生涯リスク)は60-80%と推定されている。Cowden病の場合などは不明な点も多く、がんが発症する生涯リスクは10%程度と低い。ただし、75%前後が乳腺の良性疾患と診断されるとのことだ。
これらの遺伝子が見つかり始めた25年ほど前、「将来がんに罹ると診断するなどおぞましいことだ」と無知なコメントを発していたメディアが少なくなかった。医学・科学を理解しない、一面的かつ感傷的なコメントであった。そのような姿勢が今日に至るまで継続されていて、それが日本の医療のガラパゴス化を引き起こす一因になっている。
| 疾患名 | 原因遺伝子 | がんができやすい部位 |
| 網膜芽細胞腫 | RB1 | 網膜 |
| Li-Fraumeni症候群 | p53 | 骨軟部(脳・副腎など) |
| 家族性大腸腺腫症 | APC | 大腸 |
| 遺伝性非腺腫性大腸がん | DNAミスマッチ修復遺伝子
(MLH1,MSH2,MSH6,PMS1,PMS2) |
大腸・子宮(卵巣・胃など) |
| Wilms腫瘍 | WT1 | 腎臓 |
| 家族性乳がん・卵巣がん | BRCA1,BRCA2 | 乳腺・卵巣 |
| Von Hippel-Lindau病 | VHL | 腎臓(脳・副腎など) |
| 多発性内分泌腫瘍症I型 | MEN1 | 下垂体・膵臓(内分泌)・副甲状腺 |
| 多発性内分泌腫瘍症II型 | RET | 甲状腺・副腎 |
| Cowden病 | PTEN | 乳腺・甲状腺・子宮など |
| 遺伝性黒色腫 | p16 | 皮膚(メラノサイト) |
上記の疾患は、常染色体優性遺伝性の疾患である。もちろん、突然変異によって、両親には存在しない遺伝子変異が子供にだけ生ずることがあるのだが、親がこれらの遺伝子変異を持っていれば、50%の確率で子供に伝えられる(継承される)。遺伝子診断を受けるか、受けないかは、個人の自由だが、診断を受けて陰性であれば、精神的な負担から開放される。この点が全く理解されていない。陽性であれば、頻回に検査を受けることによって、がんで命を落とすことを回避できる可能性が高くなる。
生命倫理学者の中には、何か足らないことを批判することだけに生き甲斐を感じている人たちが少なくない。陽性と判断されれば、「いつ、がんが発症するかもしれないという精神的な負担が生ずる」ことは否定できない。これだけを強調して、「遺伝子診断は恐ろしい」と、さも自分たちこそ弱者の味方だというフリをする。しかし、優性遺伝である以上、親がその疾患に罹患していれば、子供は50%の確率で決定因子を受け継ぐのだ。この世に生まれてきた以上、「50%確率」という運命は変えられないのである。
この現実を前提に、がんで命を落とさないためにと考えることはできないものなのか?もちろん、陰性にならば、「50%確率」という不安から解き放たれる。問題を提起した人たちは、陽性の方たちの精神的不安を和らげるための活動などをするわけでもないし、患者さんが抗がん剤治療で苦しんだ末に、がんで命を落としても、何の責任を取ってくれるわけでもない。無責任な評論家が人の命を軽視しているように思えてならない。
言うまでもないが、優性遺伝という現実を前提に、最終的に遺伝子診断を受けたくないという選択をする自由は確保されるべきである。
編集部より:この記事は、シカゴ大学医学部内科教授・外科教授、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のシカゴ便り」2018年1月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。