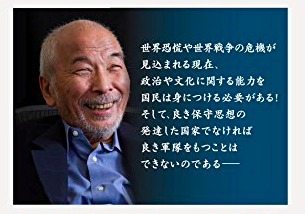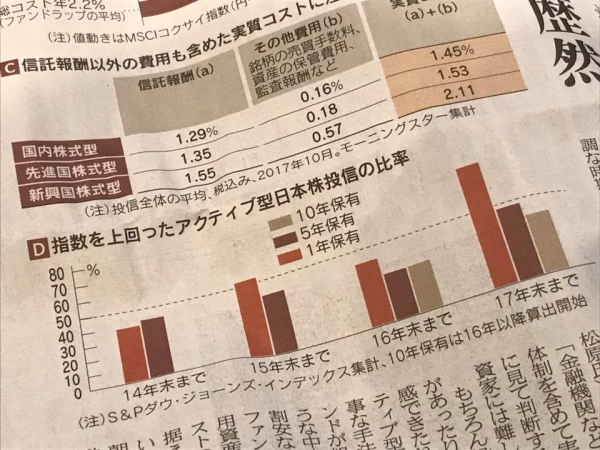大学人にとって、3月は調査出張シーズンだ。私も、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカと渡り歩いてきている(ブログも海外から更新している)。ただ国立大学に勤めていると、試験監督などには戻ってこなければならない。3月は12日に後期入試があったので、その前後は日本にいた。そういう時には予定をつめこんでしまうのだが、本屋に行って目に付いた最新刊を購入するようなこともする。
たとえば、1月21日に亡くなられた西部邁氏の新書は、何となく気になったので購入した。
西部邁さんが自らの運命を予告か 「ある私的な振る舞い」の意味(Jcastニュース)
西部氏は保守派の論客として一時代を築かれ、著作も多数に渡る方なので、一冊の本の内容だけを取り上げて云々することは難しい。ただ、西部氏の国際法に対する言及には、非常に印象深く感じるものがあった。
「インターナショナル・ロー(国際法)なるものの不安定さの反映ともいえる。つまり、国際法への違反があったとしても、それに制裁を加える政治主体が公式には存在しないということである。・・・国家秩序に先行する国際秩序などありはしないのだ。・・・国際法なるものの実体は、国連における決議や宣言の集まりなのであり、その経緯を左右しているのは安保理常任理事国などの世界列強である。・・・世界政府などは、存在しない以上に存在してはならぬものなのである。・・・」(西部邁『保守の神髄』51-52頁)
西部氏は、安保闘争時の学生運動家から、保守思想の論客となるまでの経歴で、一貫してナショナリストであっただろう。それは「対米追従からの自立」といったテーマで表現される(参照:現代ビジネス「西部邁の自殺に影響を与えたかもしれない、「ある女性の死」」)。その思想的立場からすれば、国際法の拒絶は、必然的な部分があるのだろう。したがって西部氏の国際法理解は、いわゆる左右両陣営が共有しているようなものであろう。「憲法学優越説」なるものが、日本人の良心の最後の砦のように語られるのも、つまるところ、憲法学者も保守思想家も、国際法を信用していないからだろう(拙稿:日本社会における国際法の認知度の低さ)。
僭越ながら、私に言わせれば、「国家秩序に先行する国際秩序などありはしない」というのは、世界の現実から乖離した断定だ。南スーダンに行こうが、東ティモールに行こうが、世界の大多数の国々は、20世紀後半の国際秩序の成立を大前提として、国家を成立させている。ヨーロッパにおいてすら、ほとんどの国々は、第一次世界大戦以降の国際秩序の成立によって生まれたものだ。西半球世界が19世紀以来ヨーロッパ植民地の桎梏から逃れたのは、モンロー・ドクトリンの国際地域秩序のおかげである。
端的に言って、「国家秩序に先行する国際秩序などありはしない」という断言は、日本国憲法が、アメリカ人によって起草されたものであり、その思想的淵源は、アメリカ独立宣言、合衆国憲法、大西洋憲章、国連憲章といった英米法及び国際法の秩序観にある、という事実を無視しよう、という提唱にほかならない。日米安全保障条約が、日本が主権回復したのと同時に締結されたものであり、20世紀後半の日本の国家存在と密接不可分な存在であることを無視しよう、という提唱だ。「国家秩序に先行する国際秩序などありはしない」という保守思想、及び「憲法優越説」を掲げる日本の憲法学は、政治的動機付けに訴えて、歴史的経緯を否定することを唱える立場だと言わざるを得ない。
西部氏は、世界政府の不存在が国際法の実体性の欠如を証明していると論じるが、これは国際法という法規範に対する根本的な誤認である。拙著『集団的自衛権の思想史』や『ほんとうの憲法』で、日本の憲法学におけるドイツ国法学の影響(戦前の憲法学の栄光を否定できなかったこと)からいびつな日本国憲法解釈が生まれたことを論じたが、「憲法優越説」をイデオロギー的に掲げる人々の国際法への蔑視も、同じように考えることができる。
国際政治学の古典とされる著作の一つにへドリー・ブルの『アナーキカル・ソサエティ』があるが、その題名が意味するのは、国際社会は無政府である社会である、という基本メッセージである。ブルは、人類学者による無政府社会の秩序に関する研究を参照しながら、無政府社会が、無秩序社会とは違うことを、無政府社会には無政府社会なりの社会秩序があることを、この古典的著作で、丁寧に説明している。
法律とは、主権者の命令である、と19世紀前半の法学者ジョン・オースティンは定義した。オースティンは、したがって諸国民の法(law of nations)は法ではない、と断じた。二百年前のヨーロッパの話である。国際法(international law)規範が確立された21世紀の今日、オースティンを信じる者は世界の少数派だ。
国際社会にも主権者はいる。ただ、単一ではなく、分散的に200弱程度の数で、存在しているだけだ。主権者は、絶対に単一不可分でなければならず、200近くもいたらそれは主権者ではない、と主張して初めて、国際法の法的性格を否定することができる。だが、そんなことは、一つのイデオロギー的かつ歴史制約的な意見でしかない。
国際法秩序は、国内法秩序とは異なる。だがそのことを理由にして国際法の法規範性を否定するのは、悪しき「国内的類推(domestic analogy)」の陥穽である。
国際法に制裁がない、というのは誤認である。経済制裁だけでなく、武力行使を伴う制裁もある。国内法でも違犯行為があり、キャリア官僚群が組織防衛に走れば公文書改ざんがされ、問題になると、制裁が加えらたり、加えられなかったりする。国際法でも違犯行為があれば、制裁が加えられたり、加えられなかったりする。脱法行為の形態が違うのは、社会の仕組みが違うからで、法がないからではない。
国内法と同じでなければ法ではないのであれば、国際法が法ではないことは自明であろう。だが国内法も広い意味での法の一形態であり、国際法もまたそうなのだ。
戦後日本を覆い続けた硬直した左右の対立構造は、ただ一言、国際法は法である、と言ってみるだけで、溶解していくだろう。遅まきながら、そのような態度が日本人に求められ続けていることを、そろそろもう少し認知してもいいのではないか。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2018年3月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。