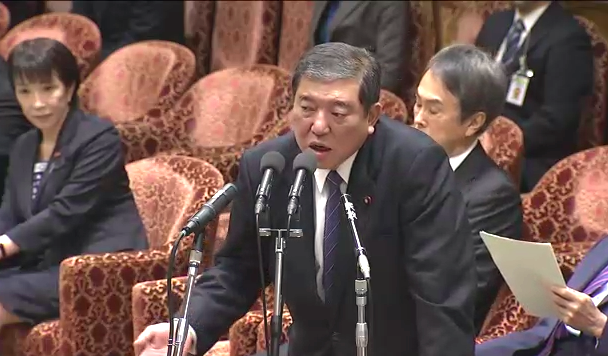陸自公式Flickrより:編集部
自民党の憲法改正推進本部が、「必要最小限の実力組織」という表現を取り除いて、改憲案をまとめる方針を固めた。それを見て、非常に曖昧で混乱を招いてきた概念なので、憲法典に挿入しない方がいい、というブログを書いた(『自民党憲法改正推進本部の動きについて』)。
思い出してみれば、「必要最小限の実力」は、私がこのブログを開設するきっかけになった概念でもある。
私が『集団的自衛権の思想史』執筆のために調査を始めた際、「必要最小限」の概念がいつ登場したのかは謎だった。内閣法制局は、1954年12月の鳩山一郎内閣の成立とともに「必要最小限の実力」が合憲だとされるようになったと国会答弁している。それを無批判・無検証で受け入れた憲法学関係の書物なども1954年12月登場説をとっている。しかし実際に1954年12月当時の記録を見ると、誰もそのような概念を使っていないのである。
そこで慎重に国会会議録を調べてみたところ、通常われわれが使う電子上の国会会議録に欠落があることがわかった。オリジナルの会議録と照らし合せてみると、「必要最小限」概念が登場することになった決定的な日、1955年6月16日の電子国会会議録において、決定的なやり取りが欠落していた。
当時の首相である鳩山一郎が、「「憲法九条に対しての解釈は、・・・私は意見を変えました」と言い放ったやり取りの部分が、ごっそり抜けていた。私は、欠落を、国会会議録管理者である国会図書館に通報した。その結果、現在では修復されている。
しかしそれまで電子上の国会会議録しか見ていなかった方は、実際の55年6月16日のやり取りに気づかず、誤った内閣法制局答弁と、それを鵜呑みにした参考書類を大量生産してきた憲法学者の見解を、絶対無謬の真理であるかのようにみなしてきたかもしれない。そこで私は、電子上の国会会議録が訂正されたことをインターネット上の記録にも残しておこうと思い、自分自身のブログを開設することにしたのである(本では、内容に沿った記述の流れがあるので、こうした経緯は書き込めない)。
このあたりのことは、『現代ビジネス』さんにも書かせていただいたが、「保守合同」の際に生まれ、冷戦期を通じて有用性を持った「必要最小限の実力」は、どちらにしても曖昧な概念で、しかも賞味期限切れだ。国際法にそって、「必要性」と「均衡性」による自衛権の制約の規範を、しっかりと受け入れるのが王道である。
なお点線以下は、拙著『集団的自衛権の思想史』第3章からの抜粋である。
――――――――――――――――
1955年6月16日、首相の鳩山一郎は、かつて自衛隊違憲論を掲げて憲法改正を唱えていたにもかかわらず、首相就任とともに自衛隊合憲論に転じたことについて、日本自由党の江崎真澄に質問された。そして次のように答弁した。「近代的の兵力、戦力というものでなければ持ってもいい、近代的の戦力を持つことは、やはり九条の禁止するところでありますというように、吉田君は唱えておったのであります。・・・私はそういうようには解釈いたしません。自衛のためならば、近代的な軍隊を持ってもいい」と答弁し(第22回国会衆議院内閣委員会議録第23号(1955年6月16日)、3頁)、吉田内閣時の政府見解を否定した。しかしなお「自衛の目的に必要な自衛力」の内容について厳しく質問され、答弁が途切れる場面も発生し、社会党議員から「暫時休憩」をとって政府統一見解を求める動議が提出された。そこで2時間半の休憩がとられた後、あらためて行った答弁において、鳩山は「言葉が足りなくて誤解を招いた」ことを詫び、「その真意」を説明する答弁を行った。そこで鳩山は初めて「自衛のため必要最小限度の防衛力を持てる」という考え方を披露し、「決して近代的な兵力を無制限に持ち得ると申したのではありません」と弁解したのであった。自衛権の歴史において決定的に重要な答弁を、この日の午後、鳩山は行った。
「私は戦力という言葉を、日本の場合はむしろ素朴に、侵略を防ぐために戦い得る力という意味に使っていまして、こういう戦力ならば自衛のため必要最小限度で持ち得ると言ったのであります。その意味において、自由党の見解と根本的に差はないものと考えております。独立国家としては主権あり、主権には自衛権は当然ついているものとの解釈に立って、政府は内外の情勢を勘案し、国力に相応した最小限の防衛力を整えたいと考えている」(同上、6頁。)
これに対して、質問者の江崎は、「だいぶ落ち着いた、はっきりした御答弁になりつつあるようでございます」と述べ、「必要最小限度の戦力を持てるというふうにだいぶん言葉が消極的になって参りました」と述べて評価をした。鳩山は率直にも、「憲法九条に対しての解釈は、先刻申し上げました通りに、私は意見を変えました。」と述べたため、そこで「意見を変えて自由党と同じになったのか」という野次まで入った(注1)。そこで「自由党のあり方というものは、今日では肯定なさっておると見て差しつかえございませんですね」と念押しをする江崎議員に対して、鳩山は再度、「先刻申しましたことによって御了解を願いたい」と答えた。その際、江崎議員が「結局今度は憲法第九条でいわゆる必要最小限という修飾語が入ったのでありますが」と述べていることからも、この1955年6月16日のやり取りにおいて、「必要最小限」という概念が日本政府公式見解に入り込んだようである(注2)。これは、自由党と民主党が「保守合同」する1955年11月の5カ月前の質疑応答であった。
解釈を変えた後、鳩山は、しばしば林内閣法制局長官(鳩山内閣成立にあわせて佐藤を継いで長官に就任)に答弁を譲った。林は滔々と次のように述べた。吉田内閣時の政府見解とは異なり、鳩山首相は素朴な意味で戦力を解釈している。
しかし憲法九条一項、二項をあわせて読めば、自国を守るために必要な最低限度の自衛のための実力、そういうものを持つことを禁止するものとは考えられない。この点は大体前の、当時の解釈と同じことと思います。そういう意味でお答え申し上げたのでございまして、その限度の内容につきましてはそう大した差はないのではないか、結局戦力という言葉の使い方の問題である、そういうふうに先ほど総理大臣はお答えしたものとかように考えております。」(同上、7頁。)
「大体」「大した」といった語を用いて、吉田と鳩山の相違を微細なものとして片付けようとする林の口調からは、以前の上司である佐藤の答弁をふまえた内閣法制局としての一貫性を確保しようとする意図も感じられる。
もともと鳩山は、自主的な防衛能力の整備を目指した改憲論者であった。その立場から「吉田ドクトリン」を否定していたのだとも言える。ところが1955年6月16日以降は、「必要」に加えて「最低(最小)の限度」といった表現を用いるようになった。たとえば6月27日における質疑において、鳩山首相は次のように答弁した。「このごろの戦争は、なかなか独力をもってしては防衛することはできないと思います。集団安全保障あるいは安保条約、とにかく集団の力をもってせずんば防衛はできないのであります。・・・集団の力の援助を受けるまでの、ある期間内において日本を防衛する必要にして最小なる限度というように考えなければならないと考えます。」(第22回国会衆議院内閣委員会議録第28号(1955年6月27日)、4頁。)
これ以降、鳩山内閣は、「自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められている」という見解を確立したと定式的に理解されるようになる。これにより、九条第二項が保持を禁止する「戦力」は、吉田内閣時の「近代戦争遂行能力」から「自衛のための必要最小限度を超える実力」に、いわば「大した差はない」「大体」の理解として、変更された。そしてこの政府統一見解の内容は、現在に至るまで維持されている。
このことがもたらした差は、計り知れないほど大きい。なぜなら自衛権の行使の問題としての九条二項の「戦力」に「最低限の範囲内」という概念が導入されたことによって、九条一項に関して留保されていると解釈された自衛権についても「最低限の範囲内」という概念が逆適用されるようになってしまったからである。当時、自衛権はあるが、戦力は持てない、という「武力なき自衛権」論が広く信奉され、社会党も採用する憲法解釈となっていた。しかし鳩山内閣統一見解(林長官説明)以来、「最低限」の概念が決定的な敷居となる新しい憲法解釈が公式化していくことになる。そしてほとんど誰も「最低限の自衛」や「最低限の戦力」が何なのかは明確に言えないため、九条解釈をめぐる議論は「最低限」をめぐって隘路に陥っていく。
(注1: 日本自由党憲法調査会は、吉田内閣末期の1954年11月5日付で「日本国憲法改正要綱」を公表し、「国力に応じた最小限度の軍隊を設置し得る」の規定を憲法に導入することを提案していた。なおあわせて「国際的平和の組織並びに集団防衛体制に参加する旨を明にする」ことや、「国際協力による集団安全保障体制への加入と、国際条約と主権制限の関係を明定する」ことも提案していた。永井憲一・利谷信義(編集代表)『資料日本国憲法2 1950-1959』(三省堂、1986年)、322-324頁。)
(注2: たとえば1972年11月13日参議院予算委員会で吉國法制局長官は、1954年12月(鳩山政権成立の月)以来「自衛のため必要な最小限度の実力」が戦力の定義として政府統一見解になったと答弁した。だが、より正確には、1955年6月16日ではないかと思われる。)
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2018年4月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。