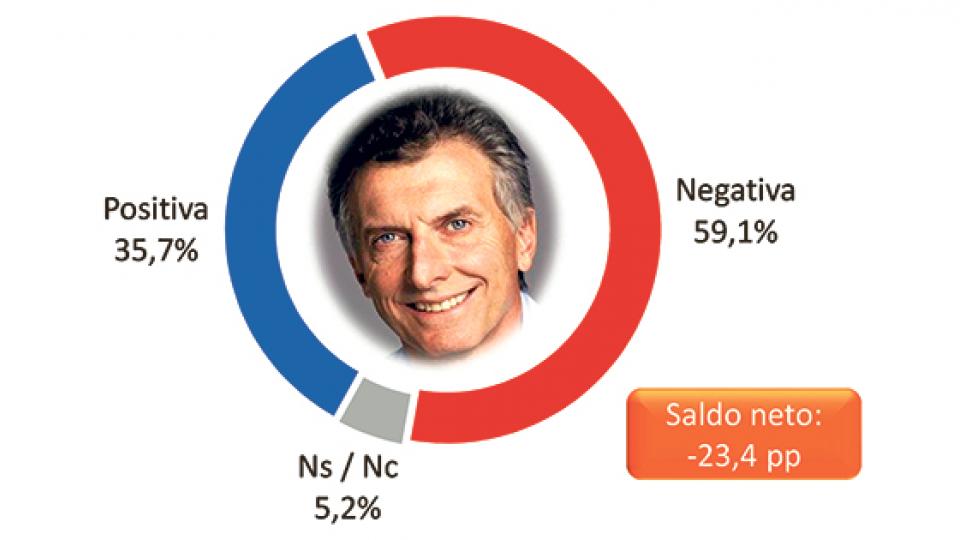2014年3月26日、埼玉県川口市で強盗殺人事件が起きた。加害者は当時 17歳の男性で、母方の祖父母を殺害した。強盗殺人などの罪に問われ、裁判員裁判を経て、懲役 15年(求刑・無期懲役)の判決を受けた。
この事件の背景を含む全体像について、毎日新聞さいたま支局の山寺香記者が『誰もボクを見ていない』(ポプラ社、2017年6月30日)という本にまとめた。題名に注目すると、「見ていなかった」という過去形ではなく、「見ていない」という現在形になっている。そのことに重要な意味があると思う。それは、今日においても、加害者少年である「ボク」と同じような境遇にいる子ども及びその親御さんについて、社会は目を向けていない、という社会の不作為に対する警鐘の意があると感じた。その意味で本書は、社会の木鐸である。
今や、7人に 1人(13.9%)の子どもが相対的貧困である。相対的貧困とは、可処分所得の中央値の半分以下の所得で生活している状態を示す。子どもの貧困は、同時に親の貧困でもある。親は、働きたくても働くことが出来ない精神状態にある人がいる。精神の不安定さは行政の支援を拒む恐れがある。それは、生きる目的や生きる喜びを喪 失してしまっているからだと思う。
そして、親としてのアイデンティティの確立が不十分となり、虐待に至ってしまうのだろう。通常、親であっても子どもに対して声を荒らげたり、手を挙げてしまったりすることもあるだろ う。だが、その場合、罪悪感を抱くのではないだろうか。虐待をする親は、そのような感情さえも感じられないくらい、何かに押しつぶされた精神状態にあるのではないかと推察する。
そのような場合、行政は積極的に支援するべきと考える。メンタルヘルスケアを行い、親が子育て出来る精神的環境を整備することから、支援の全ては始まるのではないだろうか。親の扶養義務を果たせるよう、専門的且つ継続的な支援が必要だ。但し、本人の同意無しに強制的に支援を行えるかは最大且つ人権上の問題でもある。支援対象者が行政の届ける善意を受け入れられるよう、自暴自棄やセルフネグレクトをどのように取り除くかという行政の在り方が大きく問われている。
また、支援の前段階として、行政の介入の度合いも問われることになるだろう。ここにおいては、人権や民事不介入の問題が立ちはだかる。そして、行きすぎた介入によって、責任を負いたくない思いがあったり、そもそも多くの人に対して細かな面倒を見る気持ちがなかったりするのかもしれない。
それは、公僕としてあるまじきことであることは言わずもがなだ。ただ、そうは言っても、行政には限界がある。最悪の事態を防ぐため、行政がどこまで 介入するべきかを精査し、法的根拠作りも視野に入れ、介入に強制性を持たせることも考える必要があるだろう。 現状に合わせた制度作りが求められている。
ここまで、行政の在り方について見てきた。では、我々一人ひとりには何が出来るのだろうか。
山寺氏は本書において、「どんなに同情したり心を痛めたりしても、行動を伴わない『善意』には現実を変える力はなかったのだ」(224 頁)と述べている。また、本書に収録された加害者少年の手記にも、「みんながみんな『こんな社会になってくれ』と望むだけで、誰もそうしようと行動しなければ意味がありません」(189 頁)とある。
つまり、口先だけで、 頭でっかちになっては無意味なのだ。それは、偽善であり、自己満足に過ぎない。一歩踏み込んだ対応が求められる。それは、例えば寄付などがある。その他にも、困っている人に手を差し伸べることも考えられる。それらがどのくらいの効力を持つかは定かではないが、その勇気が大事だ。
社会を生きていく上で、誰しも苦しい立場に立たされてしまうことはある。それを自業自得、自己責任と一蹴しては何の解決にもならない。社会全体で支え合う体制を整えることが大事ではないだろうか。だが、そこには不公平感が生まれる。それを埋めるべく、例えば国の予算配分について、前年度予算配分があまりなされなかった分野について、今年度はそこに予算を割くというのはどうだろうか。
予算は限られており、全てを賄うことはキャパオーバーしてしまう。少なくとも、国は貧困対策について予算を配分すべきだ。そのような政策が票にならないから行わないというふざけた理由は到底通用しない。為政者は国家・国民のためにいるのだから。
国は人々が生きたいと思える社会を作っていかなければならない。その一端を我々も担っている。理想の社会、苦しいこと、悩ましいことがあれば、公に訴え、社会を変える原動力にしていくことが大事だと思う。我々が主権者として国の在り方を決める権利を持っているのだから。それを有効に発揮させる一歩が選挙権の行使だ。国や為政者を動かすためには、まず我々が行動しなければ何も変わらない。
本書を拝読し、様々な思いが駆け巡った。その中でも無力感が一番大きい。結局、何もしないまま月日が過ぎていくのだろう。社会の諸問題についてそうだ。一番大事なことは自分や身の回りのことであるのだから仕方ないかも知れない。だが、それではいけないと思う。
また、一部の人だけを救うことは果たして公平なのか、という葛藤もある。ならば一層のこと、誰も救わない方が公平とさえ思えてくる。全ての人を救おうとしてもそれは不可能だ。だからと言って、誰も救わないことも罪であろう。畢竟、セーフティーネットを広げたとしても、どうしても漏れてしまう人はいる。
誰かを救うことは、同時に誰かを見捨て、救えないということでもあるのだ。非常に悲しいことではあるが、それが現実だ。それと向き合い、人々に生きる喜びを多少なりとも与えることをその人なりにすることが、我々に出来る一歩である。
—
丸山 貴大 学生
1998年(平成10年)埼玉県さいたま市生まれ。幼少期、警察官になりたく、