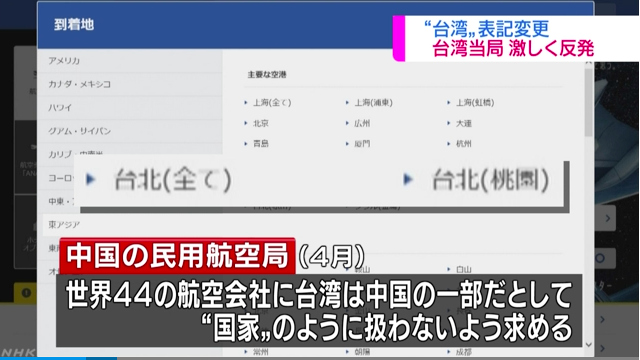がん医療の標準化が進んだ。標準化、均霑化は全体としてみればいいことだが、標準化療法が終わった後の希望が限定的だ。マニュアルに書かれていることにしたがって治療するのが標準医療であり、分子標的治療薬以外は、患者さん自身の多様性やがん細胞で起こった複雑で多様な変化をほとんど考慮しない医療でもある。
もちろん、標準的治療法がなくなれば、緩和ケアへと進む標準化が残されている。「緩和医療」という言葉は優しいが、がんに対する積極的な治療はせず、患者さん自身にも家族にも精神的に辛い日々が待ち構えている。
「標準医療以外や標準療法以降の医療・希望を求める」患者さんや家族は、白衣を着た詐欺師にはとっては格好の標的となる、と批判してきたが、日本の医療制度、臨床試験研究支援体制が、悪がはびこることに貢献しているのが事実だ。「あなたの場合、平均的生前期間は6ヶ月から1年で、薬が効かない場合には、また考えましょう」では患者さんや家族は不安を募らせるばかりだ。
「希望なく生きることを強い、不安になるのはそちらの勝手だ」とマニュアルにしたがっていることを誇りにしている医師も少なくない。希望という救いをもとめる人たちの行き場を国として十分に確保・提供できていないことが大きな問題なのだ。もちろん、心ある多くの医師たちは、患者さんに寄り添う道を模索しているのだが、システムとして機能していないのが現実だ。
こんな状況で、私一人があがいても、どうにもならないことはよくわかっているが、誰かがこの閉塞した状況を破らない限り、世界は変わらない。十数年前に、何とか流れを変えようとペプチドワクチン療法のネットワークを作り、必死であがいたが、それは朝日新聞によって阻まれてしまった。あの時のネットワークの流れが広がっていれば、日本は免疫療法で世界をリードしていたかもしれないが、覆水盆に返らずだ。
自分が歳を取ってきたと実感せざるを得ない今、再び、一から築き上げるのは大変だし、私が生きている間に実現するのかどうか自信はまったくないが、待っていてくれる患者さんや家族の期待に応えて頑張るしかない。数少ないが、応援団員が存在してくれることが心の支えだ。6月には「週刊新潮」が、そして、今日は「フライデー」が援護射撃をしてくれた。「異端児」・「一匹狼」に私には、本当にありがたいことだ。
不器用な人間は、不器用に生きるしかない。直球しか投げられない私が、野球選手になっていたら、ホームランを浴びやすい投手になっていただろう。それでも、直球を投げ続けて、直球で相手をなぎ倒すしか、私には道はなかったと思う。たとえ、ピークを過ぎたとしても、これを貫き通して、駄目ならば、引退するしかない。
常に断崖絶壁を背負って生きてきたような人生なのだから、いつでも覚悟ができている。「鳴かぬなら 殺してしまえ ほととぎす」と言うほどの気力も迫力もなくなった。
「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ほととぎす」「人の一生は、重荷を負うて遠き道を行くが如し、急ぐべからず」と思うことができるほど残された人生は長くない。仲間を増やすのが大切だとしみじみ思う。
編集部より:この記事は、医学者、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のこれでいいのか日本の医療」2018年7月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。