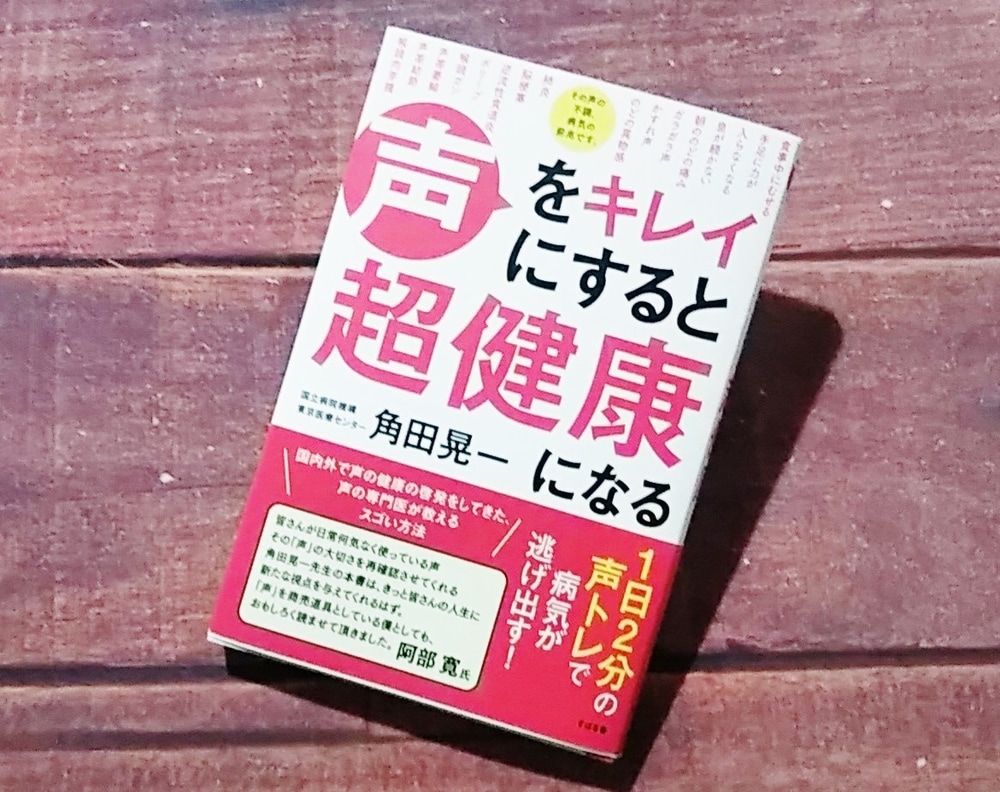今から約10年前、某大学教授が、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(1962年東京都条例第103号)における第5条「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない」第1項「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」の疑い、いわゆる痴漢で現行犯逮捕された。

被疑者は容疑を認め、送検された後、釈放された。だが、大学の調査に対しては、一転して容疑を否認した。そして大学教授を辞職した。現在は他大学の教授である。
上記の話をある人から聞き、調べたところ、衝撃を受けた。某教授は、新聞のコラムにおいて拝見したことがある人だったからだ。その話をした人曰く、某教授は法律に明るかった故、あえて示談を了承して保釈金を払ったそうだ。裁判をやったところで、無意味だと思ったのだろう。
そのような話の後、映画『それでもボクはやってない』(周防正行監督、2007年公開)を見た。この映画も上記の話もそうだが、誰が罪を犯したかは分からない。だからこそ、被疑者は刑が確定するまでは「推定無罪」とされる訳だ。
余談だが、「無罪」と「無実」の意味は異なる。前者は、有罪であることが証明されないことを意味する。後者は、罪を犯していないことを意味する。つまり、無罪であっても、有罪であるかも知れないし、無実であるかもしれないのだ。
さて、「推定無罪」は、「疑わしきは罰せず」或いは「疑わしきは被告人の利益に」とも言われ、近代司法の大原則とされている。
そのような考えは、「世界人権宣言」(1948年採択)第11条第1項において、「犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する」というように明文化されている。
さらに、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(1966年採択)第14条第2項においても、「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」と定められている。
畢竟、裁判において検察側が、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証、又は、合理的な疑いを超える証明、即ち、有罪を立証することが出来なければ、裁判所は無罪を言い渡さなければならない、ということになる。
そのような原則が如何に形骸化しているかを、周防監督は描いたのだ。このような現実を知らなければそれまでだ。
裁判所は、警察・検察を否定してまで「無罪」を言い渡す度胸はない。それらを敵に回し、左遷されることを恐れてのことだろう。
そのような裁判においては、公平且つ冷静な判断に基づく客観的な事実認定は行われない。裁判官は事件を早急に処理することで実績を上げる、という保身がなされるだけなのだ。
有罪率が95%を超える日本の裁判において、無罪を訴える被告人の前においては、今一度、感情を抑え、理性に基づき、司法の原点に返るべきだ。そのような判決が正しく評価されることを願ってやまない。
—
丸山 貴大 大学生
1998年(平成10年)埼玉県さいたま市生まれ。幼少期、警察官になりたく、