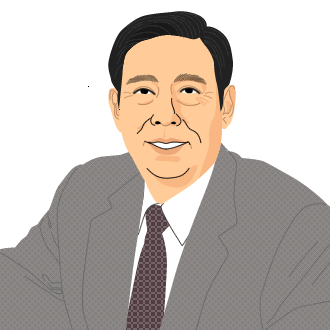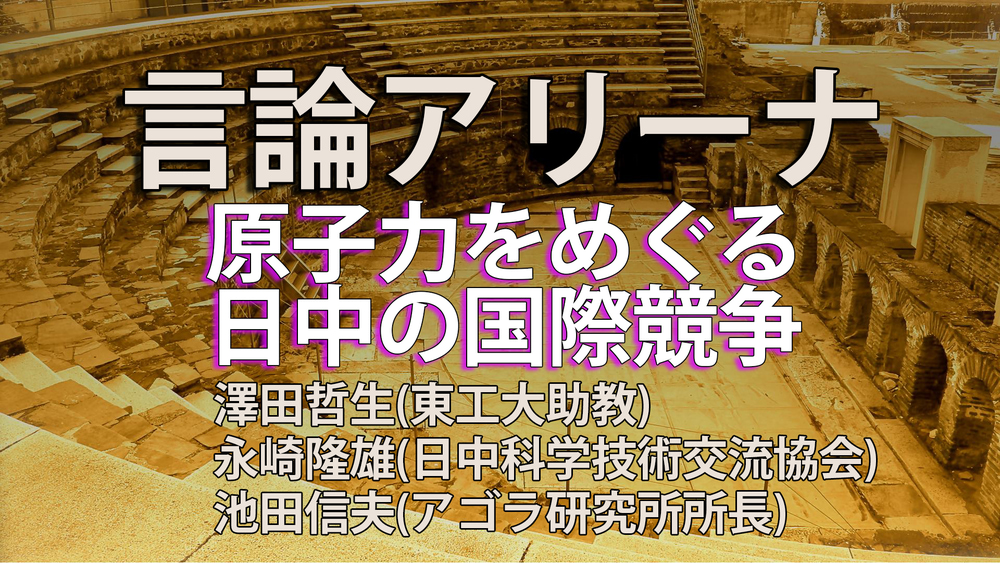19日夕刻、東京地検特捜部は、日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役を逮捕した。容疑事実は「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑」、2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったとの虚偽の記載をして提出したとのことだ。

日産サイトより:編集部
倒産寸前だった日産をV字回復させるなど、経営者としての手腕を高く評価され、今や、日産のほか、三菱自動車、フランスのルノーという3社の会長を務めるゴーン氏だ。しかも、容疑事実は「役員報酬を過少申告した有価証券報告書の虚偽記載」とされているが、大企業であれば、有価証券報告書は、総務などの担当部門で情報を集約して作成・提出する。その有価証券報告書での役員報酬が過少に記載されていたのであれば、会社の組織の問題だ。何が問題なのか、よくわからない。
西川廣人社長は、同日夜の記者会見で、内部通報に基づき数か月にわたって社内調査を行い、逮捕容疑である報酬額の虚偽記載のほか、私的な目的での投資資金の支出、私的な目的の経費の支出が確認されたので、検察に情報を提供し、全面協力したと述べた。
それにしても、この事件、まだ事実関係がほとんど明らかになっていないからだが、不可解な点が多々ある。
有価証券報告書の虚偽記載として処罰価値はあるのか
まず、役員報酬についての記載の問題が有価証券報告書の虚偽記載罪に問われた事例は聞いたことがなく、そもそも刑事立件すべき事件かどうかという点に対する疑問だ。
有価証券報告書は、事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料であり、投資家の判断の重要な資料となる。その「虚偽記載罪」としては、利益や売上、資産・負債の金額を偽る「粉飾決算」が典型だ。しかも、前期の売上約12兆円、最終利益約7500億円という日産の経営規模からすると、1期あたり約10億円という虚偽記載額は僅少であり、一般的な感覚からすると、有価証券報告書の虚偽記載罪に問うべき事件のようには思えない。
上場企業に1億円以上の役員報酬の個別開示が義務付けられたのは2010年3月期からだ。それは、経営者が高額報酬を受けていること自体が、経営者に関する重要事実であり、株主・投資家に開示することが重要と考えられたからだろう。そういう意味では、役員報酬を偽ることは、事業の状況や資産・負債に関する虚偽記載とは性格が異なるとは言えるであろう。
経営者の報酬についての「欧米基準」と「日本基準」
最大の問題は、役員報酬の隠ぺいが行われたとして、それを誰が主導したのか、という点だ。
報道によると、ゴーン氏への役員報酬とされたのは、海外の住宅の無償提供などで、通常の役員報酬とは別個の支払が長年にわたって続いていたようだ。
問題の背景には、会社は株主のものであり、その利益に貢献した経営者には、それに見合う報酬が支払われるのが当然という「欧米基準」と、会社は社員やその家族のものであり、社員が働いて生み出した利益が会社の利益なのだから、社員を代表する経営者の報酬は相応の金額に抑えられるべきという「日本基準」の違いがあると考えられる。
「欧米基準」からすると、90年代末に倒産寸前の経営状態だった日産をV字回復させて株主に多大な貢献をしたゴーン氏に多額の報酬が支払われるのは当然だ。その金額を「日本基準」から大きく乖離させないために、報酬の一部を他の名目にして秘匿する動機があるとすれば、それは日本人の会社経営陣側ということになる。
一方、「日本基準」を前提にすれば、ゴーン氏に支払う役員報酬にも限度があることになる。ゴーン氏が、表向きはその限度を受け入れた上で、別の名目で報酬を受け取り、それを秘匿して開示することを主導していたということもあり得る。
そのいずれであるかによって、事件の性格は全く異なったものとなる。
前者であれば、具体的なやり方を認識していたかどうかはともかく、会社幹部は、ゴーン氏には正規の報酬以外の実質報酬がわたっていたことを認識していたことになり、今回の事件は、それを敢えて検察に持ち込んだ「クーデター」的性格が強くなる。
一方、後者だとすると、ゴーン氏主導の個人犯罪が内部告発と内部調査によって明らかになったという、西川社長の説明どおりだということになる。
本件がそのいずれであるかを判断するためには、ゴーン氏が日産の経営トップに就任して以降、その役員報酬をめぐって、ゴーン氏自身と歴代の日産経営陣の間でどのようなやり取りがあり、どのような対応をとってきたのか、実質的な報酬についてどのように認識してきたのかを解明する必要がある。
「司法取引」はどのように使われたのか
今回の事件では、今年6月の刑訴法改正で施行された日本版司法取引が使われたようだが、それをどう評価するかだ。
司法取引の初適用事案となった、タイの発電所建設事業をめぐる不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)事件では、事業を受注した「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS)と、捜査している東京地検特捜部との間で、法人の刑事責任を免れる見返りに、不正に関与した社員への捜査に協力する司法取引が行われたが、この事例では、犯罪によって事業上の利益を得る「会社」が免責されるのと引き換えに、犯罪行為に関わった「社員」の刑事責任を追及する方向での「取引合意」だったことが「想定とは逆」だと受け止められ、世の中やマスコミには評判はあまり良くなかった。
今回の日産の事件では、ゴーン氏の部下と検察官との間で司法取引が成立したと報じられており(11月20日朝日新聞)、下位者と取引をして捜査に協力させることで上位者の犯罪事実を明らかにするという、司法取引の本来の目的に沿う適用と一応は言えるだろう。しかし、この有価証券報告書への虚偽記載の事件について、何が「司法取引によって引き出された供述」なのか、よくわからない。
自宅の提供、家賃の支払等が役員報酬だとしても、それについては客観的な立証が可能であり、特に、司法取引による供述が必要だとは思えない。考えられることは、有価証券報告書に虚偽記載して提出することについての担当者との共謀についての供述だが、それについてゴーン氏の部下と検察官との司法取引が成立したのだとすると、ゴーン氏は有価証券報告書の作成に相当深く関わっていたことになる。
司法取引による供述については、立法時から「引き込み」による冤罪の危険が指摘されてきた。ゴーン氏の犯罪事実立証についても、その恐れがないかを慎重に見極める必要があるだろう。
また、司法取引の初適用事案と同様に、日産が会社として捜査に協力したことの見返りに有価証券報告書の虚偽記載罪についての法人処罰を免れる司法取引が行われる可能性もある。もっとも、金融商品取引法の虚偽記載罪の罰金の上限は7億円なので、会社として起訴を免れることの経済的利益はそれ程大きくはない。法人処罰を免れることで、捜査への協力が評価されたという事実をアピールすることにメリットはあるが、ゴーン氏への正規の方法ではない役員報酬の支払が、会社主導で行われていた事実があるとすると、それについて会社として負うべき責任が、ゴーン氏への捜査協力によって免除されることには違和感を覚えないでもない。
検察捜査・司法判断だけでは「ゴーン時代」を終焉させることはできない
ゴーン氏の認否は明らかになっていないが、常識的にみれば、全面否認、徹底抗戦の可能性が高いであろう。その背景となるのは、経営者の報酬についての「海外基準」の考え方だろう。
一方、西川社長は、昨日の会見で、「日産のV字回復は個人に帰するものというより従業員すべての努力の結果だ。」と述べ、まさに「日本基準」の考え方を強調していた。その西川社長中心の社内調査と連携してゴーン氏を逮捕した検察も、もはや「引き返すこと」はあり得ない。
今後の検察の捜査の対象となっていくのは、事実上、容疑事実とされている2011年以降に限られる。
そういう意味で、重要となるのは、今後日産が設置する調査組織の体制だ。ゴーン氏と、そのゴーン氏の犯罪を検察に持ち込んだ会社幹部らのいずれからも独立した第三者委員会を設置し、中立的・客観的な立場から調査を行うことで、ゴーン氏就任以降、報酬がどのように決められてきたか、そこに会社幹部がどのように関わってきたのかを明らかにし、それを通して、ゴーン氏の役員報酬がどのような形でどのように支払われたのか、その一部が隠匿されたとすると、それは、ゴーン氏主導なのか、会社組織主導なのかを明らかにする必要がある。
ゴーン氏は、「日産が90年代の苦境からV字回復を遂げた」という一つの歴史を築いた。検察捜査と司法判断にすべてを委ねただけでは「ゴーン氏の時代」を終焉させることはできない。そのゴーン経営と会社組織とがどのよう関係であったのか、会社幹部はどう行動してきたのかを明らかにしたうえで、全体を総括する必要があるだろう。
編集部より:このブログは「郷原信郎が斬る」2018年11月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、こちらをご覧ください。