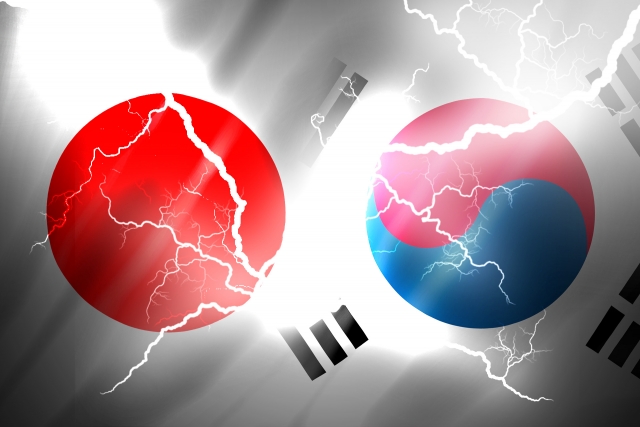2019年の8月というのは実に意義深い。都知事選まで残り1年というカウントダウンでもあれば、都議選から2年。いわば都議会のハーフタイムで、前半戦を振り返ることができる。
振り返れば、都民ファーストの会というのは、歴史的にも極めて稀な形で誕生した地域政党と言える。都議会で50議席を超える新党の誕生は過去に例がなく、日本新党ブームに湧いた1993年の日本新党でも20議席にとどまったし、97年の都議選で躍り出た民主党も13議席を超えることはなかった。

2016年都知事選当時の小池氏Facebookより(編集部)
では、なぜ、国政政党でもなかった都民ファーストの会が一夜にして都議会第一党に踊り出ることができたのか。そのことを特に、都民ファーストの会の私たちは検証しておかなければいけない。
そもそも都政ほど、国家的な予算規模を誇り、国を凌ぐほどの影響力を持ちながら、地味な存在はなかった。スタープレーヤーが耳目を集める国政の陰に隠れ、都政の記事が新聞紙面を飾ることはほとんどなかったし、都議会議員の名前はほとんど知られることなく、顔の見えない議会のもとに都政7兆円もの予算案が議決されていた。国政と都政では、メジャーリーグとマイナーリーグほどの差があったわけだ。
しかし、名前こそ知らないマイナーリーグの選手たちが、国に匹敵する予算を握り、操っていた事実を都民が知った時、都民に二つのインパクトを与えた。都政という巨大官庁の意思決定が、小さな村の小さな議会以上に、密室のなかで行われていたことに加えて、知事を凌ぐほどの権力が一部議員に集中していたからだ。
それが首都東京の行政への不信を一気に煽る形になった。
それをメディアが生んだ虚像とか、神話とか都市伝説と言って退けようとする勢力がいる。しかし、現実に、都政の重要案件の報告を知事よりも先に受けていた議員がいたことは、その多くを物語っている。
この、都民の知らない世界が遂に暴露されるようになったのは、猪瀬直樹氏、舛添要一氏と二代続けての辞任劇が引き金だった。知事の問題が拡大するほどに、例えば、豪華すぎる海外視察などを見過ごしてきた議会の責任を問う声が日増しに高まり、遂に都議会のベールがはがされることになったのだ。
その象徴が、200億円にものぼる政党復活枠の予算だった。
47ある都道府県議会において、議会が知事の予算編成権を侵して、政党復活枠なる予算枠を持っている議会は都議会の他にない。
分かりやすく会社に例えるなら、議会は監査役で、知事や都庁幹部は会社の執行役員である。その監査役が執行役員から予算の枠をもらって、独自に予算を提案することは余りに常識から外れている。ばかりか、役割分担を不明確にし、監査役としての機能を麻痺させることは明らかだ。
会社の予算案に監査役が提案した予算が入っていては、厳格な予算管理への監査役のチェック機能が全うされるわけがなく、その機能が疑われても仕方がない。この歪みの元凶、政党復活枠なる予算が、なぜ都議会にだけ出現したのかを検証しなければいけない。その検証を加える上で、石原慎太郎知事の存在を無しには語れないと私は考える。

都知事時代の石原氏(都庁サイトより:編集部)
私が議員になったのは石原知事3選目を果たした後だった。
当時、都庁の幹部職員から何度も聞かされたのは、「知事は、哲学はあるが、出勤がない」とのぼやきだった。「シュウイチ知事」、「ツキイチ知事」と言われるほどに石原知事の出勤回数は少なかったらしく、「決済を得られなくて、自分たちの政策判断に自信を持てない」と漏らした職員もいた。
私が察するに、都庁職員ほど有能であるとともに、政策決定に慎重な姿勢を崩さない行政マンはいない。その分だけに、重要案件において、政治家の意思決定に重きをおいてくれている。
だからこそ、与党の議員に対しては、知事の出勤が極端に少ないという「ぼやき」では終わらないのだ。私の想像だが、石原知事が登頂しないだけに、知事の代わりに、「先生、この方向で行きたいと思いますが、いかがでしょうか?」と一部議員に判断を仰がざるを得なかったと想像できる。あるいは、そんな実情を察して、ますます都政への関心を石原知事(当時)が薄めていたのかもしれない。それが歪みの始まりだ。
最近でも、支援者から「あんなに大騒ぎになった都政だけど、結局何が問題だったの?」と聞かれることがある。そんな時は、私は、こう言って説明をしている。
「いつの間にか都政は議員内閣制になってしまったんです。本来、都政は二元代表制ですから、議員が大臣になることも、局長になることもありません。あくまで、知事に対する監視役であり、政策の提案者。しかし、石原知事があんまり登庁しないので、議員が代わりに決済するようになってしまった。まるで議員内閣制のようです」
この悪影響が最も顕著に現れたのが、都庁職員の人事意識だ。どこの組織でも、その長が握る最大の権力は人事に他ならない。特に、巨大都庁という組織において、庁内の枢要ポストに就けるか就けないかは、都庁マンの人生を大きく変えるだけに、人事権こそ都庁を動かす究極の権力と言っても過言ではない。
本来、二元代表制のもとで、その権力が知事に集中していることは言うまでもないが、議員内閣制の性格を帯びた都政ではどうなるか。
結果、議会サイドへの猛烈な忖度と遠慮が生まれる。とりわけて、この遠慮が都政の停滞を生む。遠慮が生まれる構造はこうだ。
人事権者が実質的に知事ではなく、議会サイドに寄った場合、人事評価の基準も不特定の議員に寄るところとなり、不特定な分だけ、評価基準も不明瞭となる。特定者による加点主義にならない分、議会サイドの噂が職員への評価に直結するため、おのずから減点主義に傾斜してしまうのだ。
「あの職員は果敢にこの政策に挑んでいった」というような勇敢さよりも、「あの職員は問題だ」といった議会棟から伝わる噂が、真偽も十分に検証されることなく、人事に悪影響を及ぼす構造となるのだ。
都庁マンもこの構造を経験的に理解しているので、問題視されそうな目立った政策はできる限り遠ざけ、議会サイドから物言いが付かない政策に徹するようになる。自然と、守りに徹した政策ばかりが並び、首都東京らしい近代的なイノベーションがはかられなくなったのだ。当時、国に先駆けて都が打ち出した政策の多くが、石原知事の発案によるものに限定されたのもこの証左であるし、話を戻せば、200億円の政党復活枠予算なる議会への忖度制度が温存されたのも、その紛れもない証である。
一方で、小池百合子知事は就任すると、この都政の「遠慮の構造」を見抜き、少なくても4つのことに着手した。
(下)に続く(編集部より:14日に掲載します)

伊藤 悠(いとうゆう)東京都議会議員(目黒区選出)、都民ファーストの会 政調会長代理
1976年生まれ。早稲田大学卒業後、目黒区議を経て、2005年の都議選で民主党(当時)から出馬し初当選。13年都議選では3選はならずも、17年都議選では都民ファーストの会から立候補し、トップ当選で返り咲いた(3期目)。都民ファーストの会では、政調会長代理を務める。