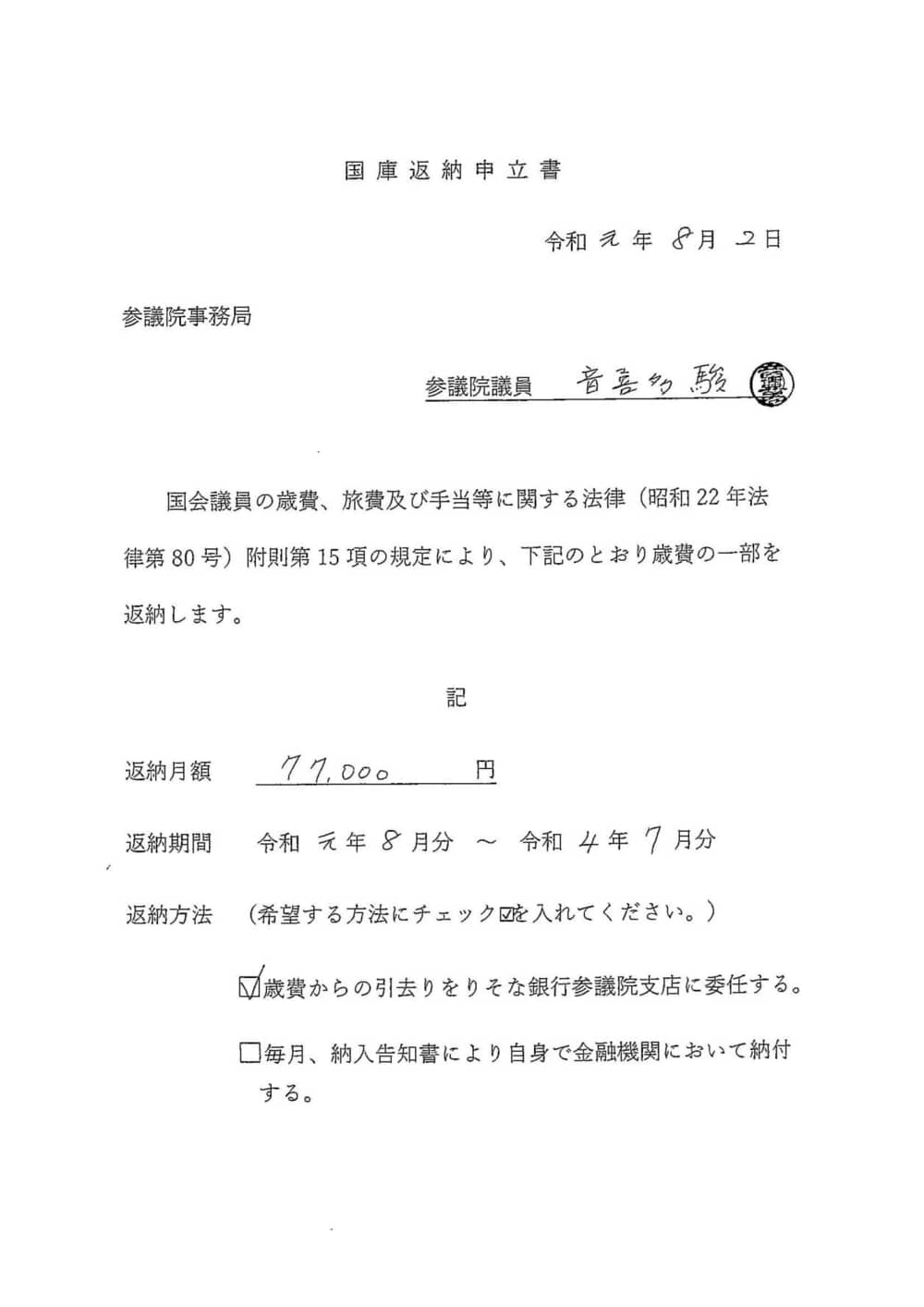先日、「日韓対立は国際法vs.歴史認識、そして日本国内も」という題名の文章を書いた。

韓国大統領府インスタグラムより:編集部
国際法の構造転換が起こり、帝国が解体され始めたのは、第一次世界大戦後のことである。国連憲章に民族自決権が明記され、脱植民地化の運動が世界を席巻したのは、第二次世界大戦後のことである。法規範の転換は図られた。植民地主義は否定された。しかし、遡及的に過去の行為が無効化されることはない。法の不遡及は一般原則だ。1910年の日韓併合を、国際法の観点から無効化するのは、無理だろう。
不正な法的現実は、正す運動を起こすべきだ。だが遡及的に過去の法的事実の無効を訴えることはできない。ガンジーであれ誰であれ、民族自決運動に立ち上がった偉人たちは皆、未来に向かって、運動をした。
現代世界では国際刑事裁判所で戦争犯罪人が訴追されたりする。だが、それはあくまでも犯罪の時点で成立していた国際人道法にのっとってのことである。
大韓民国憲法は、その前文の冒頭で、「3・1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統」についてふれている。1919年、ウッドロー・ウィルソン大統領が「民族自決」の思想を携えてパリ講和会議に乗り込んだとき、アジアでも民族独立運動が高まった。「3・1運動」は、その際の独立運動のことである。「3・1運動」で立ち上がった韓国人たちは、無残に弾圧された。非常に悲しい歴史だ。
だが第一次世界大戦の敗戦国となったオーストリア帝国やオスマン帝国の解体を、民族自決の考え方で処理しようとしたウィルソンですら、同じ考え方をアジアに適用する意図は全く持っていなかった。
「3・1運動」が起こった1919年から、韓国が独立国としての法的基盤を得たと考えるのは、無理だ。ポツダム宣言受諾時に国民が「革命」を起こしたとする日本の憲法学の「八月革命」説と同じくらいに、荒唐無稽である。本来、法的議論ではない。
だが自国内の法体系においてだけなら、荒唐無稽な議論を確立してしまうことは、不可能ではない。2018年韓国大法院判決の元徴用工をめぐる判決がそれであるだろうし、「八月革命」説にもとづいて憲法学者が自由自在に国際法概念を無視してみせるのも、似たようなものだ。「憲法優位説」なるアイディアを持ち出して、国際法体系に真っ向から挑戦をする確信犯が集団で力を持ってしまうと、もう混乱を収拾することができない。
1910年の日韓併合直後に、韓国併合の法的位置づけをめぐり、憲法学の東大法学部教授の美濃部達吉と、国際法学の東大法学部教授の立作太郎が、『法学協会雑誌』を舞台にして、数多くの論文で反論しあった有名な論争があった。双方が漢文調の長文の論文を繰り返し掲載して行われた論争なので、詳細は学術論文での紹介に譲りたいが(参照拙稿:「統治権」という妖怪の徘徊 ― 明治憲法の制約を受け続ける日本の立憲主義)、結論を言えば、不毛な論争であった。
美濃部は、韓国が持っていた「統治権」が、日韓併合によって日本に承継された、と主張した。そこで韓国の「統治権」に付随していた制約が、そのまま日本に承継された、と主張した。韓国という国家の存在を実体的に捉えたうえで、その実体性を持った国家が日本と合併したという捉え方である。
これに対して立は、日韓併合によって、韓国の統治権が消滅し、いわば無主地になった地域を、日本が領土権のいわば「原始取得」を行って、その固有の統治権を拡大することになった、と考えた。立は、当時の欧州列強の植民地支配の現実をふまえた国際法規範を自明視していたため、併合されてしまった韓国の国家存在を実体的に捉える視点が希薄だった。
美濃部と立の論争のほとんどは、「主権」とは何か、「統治権」とは何か、という原理論にあてられている。両者が遂に分かり合うことができなかったのは、憲法学者の美濃部が「統治権」の実在性を信じて譲らなかったのに対して、国際法学者の立が「統治権」なるものに関心を示さず、「統治権」は存在するとしてもせいぜい「主権」と同じものに過ぎない、という突き放した態度をとったためであった。
驚くべきことに、21世紀の今日においても、日本の憲法学者の基本書に「統治権」の概念が登場する。しかしその法的根拠が説明されることは、決してない。
「統治権」は、大日本帝国憲法の概念である。ロエスレルが起草した憲法案における「主権」の概念は、ヨーロッパ的過ぎて日本の風土になじまない、と伊藤博文と井上毅は考えた。そこで『古事記』における「シ(統)ラス」という概念に着想を得て、「発明」したのが、「統治権」概念であった。極めてロマン主義的な政治的配慮で大日本帝国憲法第四条に挿入された概念で、法的精緻さは欠いていた。
ところが美濃部達吉は、「統治権」の実在を、ほとんど憲法学者としての生命をかけて、信じ続けた。その普遍的な適用性を信じるあまり、併合される前に存在していた韓国の「統治権」は、併合後も残存し続けている、といった空理空論を主張し続けた。国際法学者の立にしてみれば、美濃部の主張は、ほとんど小説家のものであり、全く理解できない主張であった。
恐るべきことに、21世紀の今になっても、日本の憲法学では、「統治権」なる謎の概念の実在が、絶対的なこととなっている。
国際的には、全く通用しないガラパゴスな「信念」である。
似たような事情は、憲法9条2項に登場する「交戦権」にもあてはまる。憲法学者は、「交戦権」が否認されているので、日本は自衛権を行使することができない、などと主張する。しかし国際法に「交戦権」なる概念は存在していない。自衛権の行使に「交戦権」の保持が必要だ、などという謎の議論を提示しているのは、世界中で、日本の憲法学者だけだ。憲法学者の議論は、国際法上の概念である自衛権を否定する議論としては、全く的外れなのである。
ところが憲法学は、日本国内の大学人事、司法試験、公務員試験、マスコミを掌握することによって、ガラパゴスな議論を、日本国内においてだけは通用する常識に仕立て上げてしまった。
「交戦権」は、戦前の日本においても、語られていなかった。ただし戦中においては、登場していた。太平洋戦争中の著作において、信夫淳平という国際法学者は、次のように書いた。宣戦布告を行うような「開戦」の方式は、「当該国家の交戦権の適法の発動に由るを要すること論を俟たない。その権能の本源如何は国内憲法上の問題に係り、国際法の管轄以外に属する」。(信夫淳平『戦時国際法提要上巻』[1943年]
真珠湾攻撃後の日本において、「交戦権」なるものを肯定する気運が高まった。だが国際法には根拠がない。そこで大日本帝国憲法における「統治権」や「統帥権」のような謎の概念に訴えて、国際的な「交戦権」の根拠とする、という倒錯を、信夫は犯してしまった。
マッカーサーが、「交戦権」否認を通じて、否定したかったのは、これであった。つまり、自国の憲法を理由にして、国際法では認められていない行動を正当化しようとするガラパゴスな発想であった。ところが、ガラパゴス主義を撲滅するためのマッカーサーの「交戦権」否認条項が、今度は国際法における自衛権を否定する日本の憲法学者に利用されてしまった。歴史の悲劇である。
この悲劇から得ることができる教訓は、次のようなものである。
国内法で新奇な概念を作り出して、国際法を否定したつもりになるのは、危険な火遊びである。今後の日本はいっそう、こうしたガラパゴス憲法論の弊害に気を付けて、国際法とともに生きていくことを心がけていくべきだ。
国民民主党の玉木雄一郎代表が、「自衛権に制約」をかける「護憲的改憲」を目指すと述べているニュースを見た。
とても心配である。

国民民主党インスタグラムより:編集部
自衛権は、国際法上の概念である。勝手な概念を国内憲法に並べ立てて、「制約した」などと威張ってみせても、必ず、国際社会で、矛盾や乖離が露呈する。現場の人間に多大な負担がかかる。政策も停滞する。やめたほうがいい。
何でもかんでも憲法で制限するのが善いことだというのなら、国際貿易のルールや、国際人道法の原則なども、すべて日本国憲法で制約するべきなのだろうか。国際法規範を片っ端から憲法で制約していくと、日本の「立憲主義」の進展になるので素晴らしい、と、本気で考えているのだろうか。
以前にも指摘したが、玉木氏を含めて、日本の司法試験・公務員試験受験組に、こうした発想が顕著に見られる。残念なガラパゴス主義である。
繰り返すが、自衛権は、国際法上の概念である。勝手な概念を憲法に並べてたてて制約したつもりになったりするべきではない。少なくとも国際法の概念構成に沿った形で議論をすすめていくべきだ。そうでなければ、日本は必ず国際的に行き詰る。

篠田 英朗(しのだ ひであき)東京外国語大学総合国際学研究院教授
1968年生まれ。専門は国際関係論。早稲田大学卒業後、