
ペリー(Wikipedia)
前回も書いたように、中国系官僚に操られた琉球王府関係者が、清との関係も続けたいとしていたのにもかかわらず、日本への併合が成功したのは、幸運だったともいえるが、欧米人たちが日本への併合が自然な成り行きだとみたことも大きかった。
琉球に上陸したペリー提督も、「琉球の言語、衣装、習慣、美徳、悪徳いずれも日本と同じ」、「日本人の多くが居住し雑婚し普通に生活をしているのに対して中国人は外国人として扱われておりここは日本の領土だ」、「清とは年一隻の船しか行き来しないが、日本とは年数百隻の船だ」と記しており、朝貢関係があるといっても、それは、近代的な意味での領土というのとはほど遠い概念だとみていたのである。
そして、琉球の王府関係者が清との関係に固執するのは、自分たちの地位・特権・財産が守られるかという危惧のためであり民衆的な基盤があったわけでなかったこともある。
琉球国王であった尚家は、侯爵となった。沖縄の経済規模からすれば、子爵か伯爵相当だが、特別の配慮で普通は30万石以上の大名でないとなれない侯爵としたのは二段階特進で最大限の配慮といえ、沖縄は経済的にも援助を受けてかなり優遇されたのである。
琉球処分から太平洋戦争が始まるまでの日本政府の沖縄統治は、全体としてはまずまず高い評価をすべきだと私は思う。
旧支配層の離反を怖れて、政府は旧慣尊重をしばらく方針とした。これに対して、第二代目の県令として赴任した上杉治憲はこうした守旧策を批判し、沖縄県民本位の統治を提案したので、いまでも県民からたいへん尊敬されている。
沖縄では1894年に、沖縄尋常中学(現在の首里高校)で、新任の校長が、普通語(標準語)すらままならない生徒に外国語まで教えるのは気の毒として、外国語をカリキュラムからはずすという事件があり、馬鹿にするなと怒った生徒が6か月のストまでした。

漢那憲和(Wikipedia)
この時の首謀者がのちに海軍少将となり、昭和天皇訪欧の際のお召し艦の艦長だった漢那憲和である。退学処分になったが、奈良原知事の配慮で海軍士官学校に進んだというのが、明治人のおおらかさである。
ただ、沖縄の場合には、台湾の開発などと比べると将来性が乏しく戦略的な意味もないという判断がされた。一方、台湾の統治は、沖縄に中継地としての役割を与え、台湾に帝国大学など上級学校が設立されたことは、沖縄の人にとって大きな恩恵になった。
また、気候が似た台湾や南洋群島へ多くの沖縄県民がチャンスを求めて出稼ぎへ行き、南洋諸島などは、まさに沖縄人の王国となり、1943年には人口の65パーセントが韓国・台湾を含む日本人で、そのうち60パーセントが沖縄本籍だった。
そののち、沖縄の近代化は進められたが、義務教育が始まったのは1901年、国会に代表を送り出せるようになったのは1912年になってからのことだが、それでも、政府としては精一杯の近代化を進めたのである。
また、台湾とともに南洋道を設立しようという構想もあり、もし、これが実現していたら、戦後、沖縄が日本に留まることは難しかったかもしれない。
太平洋戦争が始まったころ、沖縄はそれほど重要な戦略上の要地でなく、「軍備は連隊長の軍馬一頭」などと揶揄されたほどで、大きな軍事基地もなかった。
ただ、太平洋の防御線が後退していく中で、1943年あたりから台湾ともども飛行場の建設が行われた。そしてサイパンが1944年6月に陥落すると、次は台湾か沖縄かと緊張が高まり、政府は疎開計画を立てたのだが、米軍の潜水艦による攻撃で対馬丸が撃沈され1500人が犠牲になる事件などもあり、疎開は十分に行われず、最終的には、本土に6万人、台湾に2万人が移ったが、それでも45万人の県民が残り、そのほとんどが激戦地となる中南部に集中した。
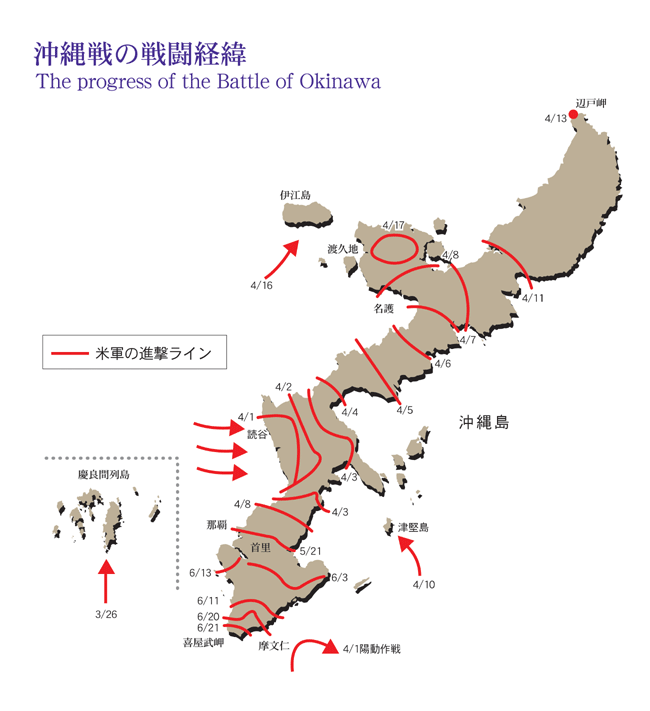
国立公文書館HP
しかも、強力な助っ人だった第九師団は、10月10日の空襲のあとフィリピン戦線支援のために台湾に移駐し、11万人の兵力はいたが、質は高いとは言えず、3分の1は現地召集の予備兵力だった。昭和天皇は沖縄戦で犠牲が多かった原因として兵力の少なさを上げていたが、もう少し兵力がいたら、そもそも、米軍は攻めて来なかったのではないかと思う。現在の沖縄で基地を減らせという人が多いが、私はそれこそ危険だと思う。
そして、作戦の目的を撃退でなく、上陸させてからゲリラ戦を展開して本土決戦までの時間稼ぎを主眼にした。首里から撤退直前に開かれた軍団長会議で、島田叡知事は「軍が武器弾薬もあり装備も整った首里で玉砕せずに摩文仁に撤退し、住民を道連れにするのは愚策」と反対したが、牛島は「第三二軍の使命は本土作戦を一日たりとも有利に導くこと」として南部移転を強行した。
この判断は、少なくとも結果論から見ると、軍の間違いだと言わざるを得ない。陸軍の牛島満司令官は「爾後各部隊は各局地ニオケル生存者ノ上級者コレヲ指揮シ最後マデ敢闘シ悠久ノ大義ニ生クベシ」といって自決して組織的抵抗は終わった(6月22日)。この中途半端な命令が沖縄ではその後も戦いが続いて民間人の犠牲者が増えた原因のひとつであって無責任といわざるをえない。
それに対して、海軍の大田実司令官は「沖縄県民斯く戦えり。県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを」と打電してから自決したので、牛島司令官に比べれば評判は良いのだが、大田中将が沖縄の人々の犠牲を少なくすることに貢献したのでもなく、事後に格別の配慮を願っただけなのでだから、それほど尊敬される理由もない。

米兵の火炎放射器(Wikipedia)
日本軍は南部に撤退し、ガマといわれた自然洞窟のなかにこもって戦いを続けたのだが、こうしたガマにはすでに民間人が避難していた。軍にしてみれば邪魔なわけで、追い出したり、スパイだと疑ったり、食料を奪ったりした。そして、集団自決したり、降伏しないまま生き埋めにされたり火炎放射器で焼かれたりした一般人が多くいた。
こうした状況について、たしかに、軍上層部からの司令があったのかといえば、少なくとも明確な形ではなかった。しかし、「アメリカ軍は恐ろしい」、「投降するのは非国民だ」といった刷り込みもされていたし、パニックを起こした末端の将兵が自殺用の手榴弾を渡すとか、一緒に死ぬことを勧めるとかさまざまな形で、本当の意味で自発な自決でないケースは多かったと見られる。
そういう状況では、軍の組織的命令がなかったとしても、起きた悲劇は予想外のものとはいえず、また、一般住民を巻き込まないように軍の末端に教育も指示もしてなかったわけで、沖縄の人が日本軍を恨むのは当然のことだ。間違っても、「日本軍は沖縄を守るために戦った」などというべきではない。
たしかに、個々の事件についていろいろ弁解することはできるかもしれないが、沖縄戦全体とその後の展開を全体として評価した場合に、弁解がましいことをいうことは、沖縄の人々の感情を致命的に逆なですることなのは当然である。
![]()
八幡 和郎
評論家、歴史作家、徳島文理大学教授













