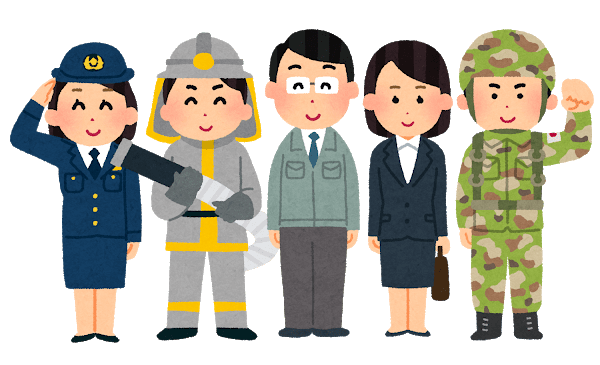スイスに関するニュースや情報を発信しているウェブサイト「スイスインフォ」によると、ホームシックはスイス人の200年前の国民病だった。「牧人の歌に故郷への思いを馳せ、スイスの代表的児童文学作品『アルプスの少女ハイジ』の主人公の少女もこの病に悩まされた」という。

朝の光が雲の間から降り注ぐ瞬間(2018年7月27日、ウィーンで撮影)
当方は欧州に居住して約40年を迎えるが、幸い、ホームシックとなって発熱したり、鬱(うつ)になったことはこれまでなかった。ところが、ここ数カ月、少し気分が落ちてきた。このような症状をオーストリアでは「秋の憂鬱」と呼ぶ。夏から秋に移り変わる時に陥る気分の低下だ。季節が変われば、再び活力が戻ってくるから、それほど深刻ではないと受け取られている。
なぜ当方は「秋の憂鬱」に陥ったかは薄々分かっている。左目の手術後だ。先月8日、左目の網膜・硝子体矯正手術を受けた。外科手術は上手くいったが、その手術後、左目の硝子体は赤く、膿は止まらない。定期的に清潔な紙で目の周りを拭く。視力は次第に回復してきたが、コンピューターでの仕事は長時間は難しい。光の反射が目に良くないからだ。
当方は20代に胆嚢を摘出し、40代に泌尿器系のがんになった。まだ若かったこともあって手術後の療養はしんどいとは思わずに過ごしたが、60代に入って右目の網膜剥離を患い、今度は左眼の手術を受けたが、その後の療養で体力の減退を感じる年齢となった。
目の病気は他の病気より、患者に様々な負担を与えることを実感している。がんの手術後、当方は普段と同じように取材で飛び歩いていたが、目は体のセンサーだ。そのセンサーが故障すると方向感覚が可笑しくなるだけではなく、目に入る情報が著しく減少する。目を悪くすると、生きていく上で大きなハンディを背負うことになるからだ。
「秋の憂鬱」下にあった先月末、いつものように朝5時半ごろ、駅前に新聞を取りに行った。その時、広告塔の宣伝文句が目に入った。曰く「ザイ・フライ……」(煩いから解放されよ)だ。それを読んだ瞬間、「その通りだ」と雷に打たれたようなショックと新鮮な感動を覚えた。同時に、言葉は言霊といわれているように、人間に大きな影響を与えるのを改めて実感した。
新約聖書「ヨハネによる福音書」の有名な聖句を思い出した。「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。すべてのものは、これによってできた」というのだ。この聖句を少し現代的に表現すれば、言葉を発するためにはエネルギーが不可欠だ。その結果、言葉は物質化する。質量を帯びた言葉に人がぶつかったり、触れば、その言葉の影響を否応なく受ける、というわけだ。
このコラム欄でも書いたが、精神分析学のパイオニア、ジークムント・フロイト(1856~1939年)は言葉を非常に重視してきた学者だ。診察台に横たわる患者が発する言葉からその人の潜在的な考えや感情を読み取り、分析する。
フロイトは精神分析でも視覚的な現象からだけでなく、患者が語る言葉の意味、その背景を重視して精神病患者を治療している。先ず、思考が“霧と靄に包まれて”浮かび上がる。それを言葉を通じて形態を付与する。フロイトは、「言葉は本来、人間を治癒する魔法」と信じていたが、「言葉がその魔法を次第に失ってきた」と懸念をも表している(「フロイト没後80年と『ノーベル賞』」2019年9月7日参考)。
朝の広告塔の宣伝文句に戻る。「ザイ・フライ……」がなぜ秋の憂鬱にあった当方に新鮮な驚きと一種の感動を与えたのかを考えた。目の手術後、当方も人並みに思い煩いに囚われていたのだろう。その「囚われから自由になれ」というメッセージだったからだ。
イエスは「明日のことを思い煩うな。明日のことは、明日自身が思い煩うであろう」(「マタイによる福音書」第6章)と述べている。その時、その瞬間を全力を出して生きていくべきだという考えだ。大げさに表現すれば、一種の悟りだ。
いずれにしても、当方は両目の手術を受けることで、目の大切さと共に、目の特殊な病によって失明し、右目を摘出し、義眼を移植した知人の息子さんの痛み、悲しみの一部を分かったように感じた。
■
「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2019年11月19日の記事に一部加筆。