今回も前日の続きで、元英駐在北朝鮮大使館公使だった太永浩氏の著書「北朝鮮外交秘録」(文芸春秋発行)の中で興味深い点を記録しておきたい。
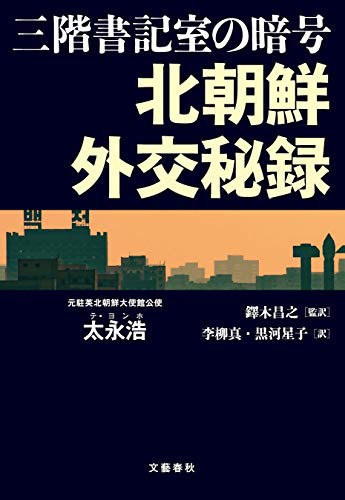
太永浩著「三階書記室の暗号、北朝鮮外交秘録」
先ず、先進7カ国(G7)の中で最初に北朝鮮と国交を締結したイタリアの外交官との接触場面だ。
イタリアは2000年1月にG7の中で先駆けて北朝鮮と国交を締結したが、同国は1992年に北朝鮮との国交交渉を始めている。外交関係の締結に向けてイタリア政府が動き出したことを知った金日成と金正日は大喜びだった。ソ連・東欧共産諸国が崩壊した直後で、北朝鮮は外交的にも孤立していただけに、イタリアとの国交が樹立されれば、その孤立を突破できると期待し、平壌に派遣された2人のイタリア外交官を懸命に接待する場面が面白い。
夜は木欄館で代表団との晩餐会が開かれた。そこには「喜び組」の女性たちも登場する。その場に接待役としていた著者が初めて「喜び組」の女性を目のあたり見てその美しさと共に戸惑いを感じるシーンが描かれている。
結局、イタリアの使節団は北側のホットな歓迎ぶりに戸惑ったのか、その場は余り盛り上がらずに終わった。イタリアと北朝鮮の国交締結はその8年後に実現する(「北朝鮮とイタリア」2007年5月5日参考)。
スイスに30年余り駐在していた元駐スイス北朝鮮大使館の李洙墉(リ・スヨン)大使についても言及されている。太永浩氏の李氏への評価は高い。

故金正日総書記の肖像画(Wikipediaより)
李氏は金正日の息子2人、金正哲と金正恩のスイス留学を世話したこともあって金ファミリーの信頼は厚かった。通常の北外交官ならばタブーで絶対に言えない内容も金正日に直言出来た数少ない北外交官だ。
著者は具体的な証を書いている。李洙墉氏は金日成バッチを北の外交官が必要に応じて外してもいい許可を金正日から得ている。その時の李氏の説明が非常にクレバーだ。
「スイスに大使として出向いて仕事をしていると、外交官の給料も多くないため、仕方なく安い店に行くこともある。それが恥ずかしいわけではないが、そうした場所に首領様の肖像バッチをお連れするのは申し訳なく思う。飛行機でも南朝鮮の傀儡どもの目に留まりやすく、身辺の安全上、不利な点でもある」(56頁)
李氏は若い外交官に対しても熱心に世話をするので、著者を含む他の外交官には受けが良かった。金正日はスイスのジュネーブ郊外に大きな館を購入したことがあった。西側メディアはその館が金ファミリーの亡命のためだと報じた。その館を購入したのはジュネーブ大使の李氏だったこともあって、当方は李氏はやり手で剛腕な外交官といったイメージが強かったので、太永浩氏の証を読んで、へェーと少し驚いた次第だ。
2013年12月、金正恩朝鮮労働党委員長の逆鱗に触れ、処刑された叔父の張成沢が1991年12月、ノルウェーで偽造旅券の所持容疑で拘束されたことがあったという。当方には初耳だ。スウェーデンに留学していた娘(張琴松)に会う目的でスウェーデンを訪問した後、観光目的でノルウェーに入ったところ、偽造旅券が発覚して逮捕された。なお、張琴松は2006年、留学先のパリで自殺している。
著書の前半で面白かったのは主体思想の創設者、黄長燁が1997年2月、中国の韓国総領事館に亡命申請した事件での北側の対応だ。最初は韓国情報員が拉致したとして韓国側に至急、釈放するように抗議し、世界の北外交官を動員して韓国批判を展開していたが、時間の経過と共に、「どうやら亡命だったらしい」と判明すると、「黄長燁が革命に背反して敵側に傾いたので、今後は釈放運動を中止し、全ての対外活動の中心を『卑怯者よ、行くなら行け』にしろ」というフランスの北朝鮮代表部経由から配信された金正日の指令に基づいて、批判の的を韓国から黄長燁に急遽変えている。
北外交官たちは主体思想の創設者の脱北にショックを受け、立ち上がれないほどだった。著者はその本の中で「彼の亡命は主体思想の亡命だった」と記述し、黄長燁の亡命事件の衝撃が如何に大きかったかを示唆している(90頁)。
北朝鮮では1990年代に入り、大粛清が行われた。多くの要人が処刑され、左遷させられていった。食糧飢饉の責任探しが行われ、食糧危機の主犯は「主体農法」をきちんと執行しなかった農業相の責任だったということになり、既に亡くなって埋葬されていた当時の農業相、金万金の墓を掘り起こし、死体に発砲して処刑した、といった具合だ(97頁)。
儒教とシャーマニズムの影響もあって、人間は死後も生きていると考えられている。だから、墓から死体を引き出し、処刑するということになるわけだ。
北で一旦「反逆者」のレッテルを貼られると、死んで埋葬されていても掘り起こされ、処刑されるわけだ。“永遠の眠り”といったロマンチックな世界は北では期待できない。
太永浩氏の「北朝鮮外交秘録」には多くの興味深い話、事実が記述されている。読み進めていくうちに、新しい話も出てくるから、その度、このコラム欄で紹介したい。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2019年12月28日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。














