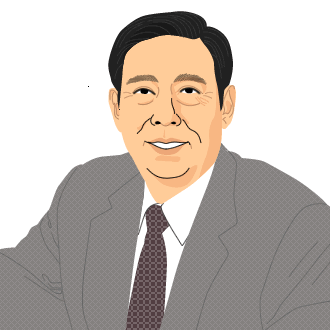安保闘争デモ隊に取り囲まれる国会周辺(Wikipedia)
日米安保条約が改訂されて60年。その記念日の1年前の今頃、東大の安田講堂において、8500名の警視庁機動隊と、2000名の過激派学生たちが激突し、学生運動史を象徴する歴史的な攻防戦が繰り広げられたことを記憶しているだろうか。その後に生まれた人にとっては過去の物語に過ぎないが、私には多感な青春の印象的な思い出のひとこまであるだけに何度も振り替えって来た。
機動隊の催涙ガスの音と弧を描く放水に対して、学生たちの投げる火炎ビンと投石。周囲は騒然とした雰囲気になり、機動隊が逃げ惑う学生たちを追い込み、叩きのめす姿が繰り返し報道されていた。私はまだ中学生だったが、いったい世の中では何が起こっているのかと、テレビや新聞の写真や活字を眺めて興奮していたことを思い出す。確か800名余りの負傷者が出て、700人近くが逮捕され、東大安田講堂は陥落した。
連日の国会を取り巻くデモ隊の足音と『安保粉砕、闘争勝利』のシュピレヒコールが不気味に響いた。まるで近年の香港の報道を想起させるような映像が、私の脳裏に焼きついているのだ。私はその現場にいないことに、まるで歴史の舞台に参加できないかのような決定的な悔しさを感じたことを思い出す。まさに時代の熱に侵されて、その高揚へのクライマックスの時期に、安保闘争を通じて政治に目覚めた『遅れてきた青年』だったことをそののち知らされることになるのである。
同じ年の高校入学の直後に、身近な出来事として唐突に、新左翼の過激派高校生たちが20人規模で、高校生の政治活動を禁じた大阪府教育委員会の通達の粉砕を叫んで校長室を占拠するという事件に遭遇するのだ。校庭には一部の生徒が連帯する集会を開き、マイクで演説をし始めたことで、全校が騒然となって、全ての授業が中止になった。暫く自習するようにとの担任の声で、義憤にかられた私は人質になった校長を助なければと咄嗟に思って、同級生に呼び掛け、竹刀を持って走り出したが、教師たちにスクラムを組んで止められたことを思い出す。
結局、2時間ほどで話し合いに応じた過激派たちはバリケードを解いて去って行った。ほとんどが他校の生徒だったというのだ。ほどなく授業が再開されたのだが、私は非日常的な出来事を飲み込むことが出来ずに、呆然とするばかりで、それ以降安保や思想の本をむさぼり読むようになって行った。その衝撃的な出来事を経て、何故かその日から私は右翼のレッテルをはられたのだが、その時には左翼という言葉の意味さえ知らなかった。ただ、学生運動とは何なのか。その背景に何がなあるのか。猛烈に興味を抱くようになったのである。
高校1年の夏休みには、いても立ってもいられなくなって一人上京し、東大安田講堂や大学のキャンパスに立て掛けられた独特な看板を見て歩いたり、左右の政治集会を覗いてみたりして、時代の空気に触れ、早く東京の大学に入って歴史に参加をしなくてはならないと幻想を覚えていたことを忘れられないでいる。稚拙な私は唯々諾々とアメリカに屈してしまっている政府への反発を強く感じていた。
そして、3年の後に、念願の東京の大学に入ってキャンパスに立った時、既に学生運動の嵐など跡形もなく、時代は日本人を経済へと駆り立て、政治の季節は見事に終わっていたことに気づかされるのである。国会を何十万人と取り囲んだあの安保闘争のうねりは何処へ消えてしまったのか。学生たちの反乱の情熱はいったい何だったのか。こんな簡単に先輩たちは資本主義の戦士に変貌してしまっていいのかと、私は呆然と無風になったキャンパスに立ち尽くしたことを忘れることが出来ない。
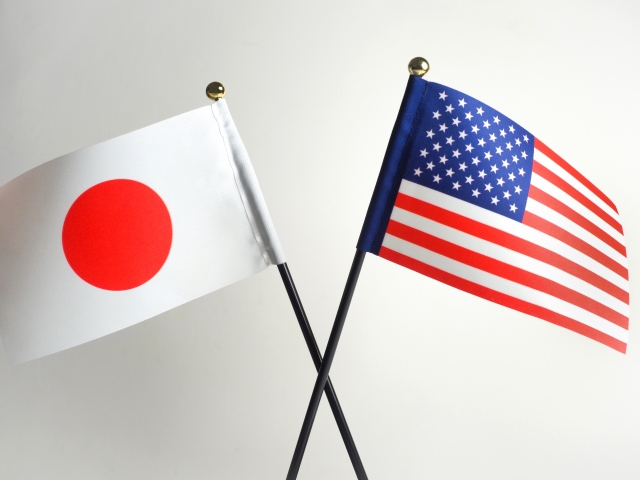
写真AC
そこから、いつの間にか、安保は日本人にとって所与のものとなって行き、自衛隊が合憲か否かと熱く議論する緊張感も消えてしまって、ましてこの国を自分たちの手で守らなくてはならないとする防衛意識も、アメリカに委ねてあたりまえだと大半の日本人は考えるようになり、国家とは何かという重い問いと、かつての戦争体験も含めて真摯に向かい合う姿勢を失ってしまった。
それゆえに、われわれが政治のことを考えようとする時に、根底にある大切な何かを忘れて来てしまった為に、国防も軍隊も言葉として正面から使用することが憚れる、そんな不思議な風潮を根深く日本人の心に植え付けてしまった。
それは日米安保条約の絆を深めれば深めるほど、経済国家として生きて来た日本の戦後意識の根底のところにある魂の空白とでも言うべきものにぶつかってしまうことに気づかされる。その呪縛から解放されない限り真の戦後は終わらないような気がしているのは私だけだろうか。果たしてそんなことを拘らないですむ新しい世代がすいすいと、日米関係を再構築してくれる時代が訪れるのだろうか。
日本にとってより自立する国家とは何か。政治の復権とともに避けては通ることの出来ない課題に直面して行く時が来ることを私はいつも感じている。日米地位協定の見直しもアメリカの壁に阻まれて一向に進まない現実の前に、平ん和の代償はもっと日本の存在の意義を未来に向かって問いかけていると、安保改訂60年の今日、痛感しない訳には行かないのである。

藤川 晋之助 政治アナリスト、国会議員秘書
23歳の時、選挙の手伝いをきっかけに国会議員秘書となる。代議士秘書、大臣秘書、地方議員、放浪と隠遁生活を経て東南アジアでいくつかの事業に挑戦。帰国後、東京で藤川事務所を設立し、国会議員や首長の政策立案、選挙をサポートする。政官マスコミに幅広い人脈を持つ。