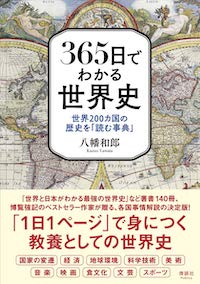ロンドン交響楽団(Wikipedia)
新刊『365日でわかる世界史 世界200カ国の歴史を「読む事典」』(清談社・4月12日発売)は、さまざまな分野でのベスト100にチャレンジしてみたということを書いたが、昨日の建築に続いて音楽について書いてみよう。
ここでは、西洋のクラシック音楽についてのみのベスト100である。ほかに、別枠でオペラ50選とバレエ20選を選んだ。また、ポピュラー音楽については、別途、ポピュラー音楽の歴史というかたちにして8ページほど割いて、そのなかで10大アーティストを選んでいる。
それは以下の通りだ。10大アーティストの代表曲
- エルヴィス・プレスリー → 「ハウンドドッグ」
- ザ・ビートルズ → 「抱きしめたい」 「イエスタデイ」 ほか
- レッド・ツェッペリン → 「胸いっぱいの愛を」
- ピンク・フロイド → 「原子心母」
- デヴィッド・ボウイ → 「ジギースターダスト」
- マイケル・ジャクソン → 「今夜はビートイット」
- プリンス → 「パープル・レイン」
- マドンナ → 「ライク・ア・ヴァージン」
- セックス・ピストルズ → 「アナーキー・イン・ザ UK」
- ニルヴァーナ → 「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」
さて、なぜ西洋音楽だけなのかだが、音楽については西洋音楽の優位がかなりはっきりしているし、邦楽も含めて、ほかの音楽は「名曲」という取り上げ方が可能なのか疑問でもある。というのは、西洋音楽は、グレゴリオ聖歌の頃から楽譜があり、再現性が高かった。数学などが盛んだったのも理論的分析を可能にしたのだろう。
もうひとつは、教会が音楽を大事にし、また、教会の建築が和声を発展させるのに相応しかったということもありそうだ。1オクターブを12に分割する音律が他民族の音楽にも応用できるとか、ハーモニーの妙味が他の地域の音楽に比べてずば抜けて発展したということもできよう。

York Minster/flickr
西洋音楽のはじまりは、中世の教会音楽だが、上記のような西洋音楽の特徴が確立したのは、バッハなどより少し前あたりからだろう。だから、取り上げたのはそのあたりからだ。
海外のセレクションにも目を通したし、優劣についての定評が明確でないものは、Facebookで意見を募ったりした。たとえば、モーツァルトのピアノ協奏曲、ベートーベンのピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲のなかで最高傑作は何かといってもなかなか難しいし、100という数が限られているから同一作曲家の同ジャンルのものはできるだけ一つにしておきたいからだ。
結論からいうと上記のジャンルでは、ピアノ協奏曲台23番、ピアノソナタ第32番、弦楽四重奏曲第15番を入れてある。
あまり同じ作曲家のものは入れたくなかったが、モーツァルトは8曲、ベートーベンは10曲入っている。ただし、モーツアルトは別にオペラ50選で5曲入れてある。
現代音楽をどう評価する
現代音楽の扱いも難しい。なにしろ、第一次世界大戦の頃までは、クラシック音楽が幅広い層にとって音楽芸術・娯楽の中心だった。ところが、映画やミュージカルが出現してオペラにとってかわった。オペラとミュージカルの違いは何かと言えば、オーケストラ伴奏かバンドの伴奏かだろうか。
そうなると、オペラはどんどん芸術性に純化して難しいものになった。だから、プッチーニを最後にして、世界で広く親しまれるオペラなんかないのである。
オーケストラ音楽も、映画音楽にその地位をかなり奪われた。ソ連ではクラシック音楽と映画音楽が分化しなかったし、大衆にクラシック音楽を聴かせたので、プロコイエフ、ショスタコービッチなどの音楽は大衆にも親しまれた。
西欧でもバレエは健在だったから、ラヴェルの「ボレロ」とかストラビンスキーの「春の祭典」などがなんとか広く愛されたが、戦後は苦しい。
結局、戦後の作品は、メシアンの「トゥーランガリラ交響曲」(1949年初演、YouTube参照)しか入れなかった。
もちろん戦前から活躍している作曲家で戦後も高い水準の作品を作曲し続けた人はいる。ショスタコービッチの交響曲では第9番以降が戦後の初演で、第10番、第14番、第15番あたりの評価は高いが、普通には戦時中に作曲された第5番「革命」とか第7番「レニングラード」が代表作とみなされている。
そのほかストラビンスキー、プロコイエフ、オネゲル、シベリウス、ヒンデミットなども戦後も活躍したが全盛期とはいえない。
そのほか21世紀になっても生きていた作曲家となると、一部の好事家に評価されていたとしても、幅広い支持を受けているとはいいがたい。そこで、作品をあげるのは諦めて、次のように記しておいた。
21世紀に入ってからも存命だった作曲家としては、ピエール・ブーレーズ、アンリ・デュティユー、クルターグ・ジェルジュ(フランス)、カールハインツ・シュトゥックハウゼン(ドイツ)、ジョルジュ・リゲティ(ハンガリー)、ルチアーノ・ベリオ(イタリア)、エリオット・カーター(アメリカ)あたり。ポピュラーとの境界では、エンニオ・モリコーネ、ニノ・ロータ(イタリア)、アンドルー・ロイド・ウェバー(イギリス)、ジョン・ウィリアムズ、レナード・バーンスタイン(アメリカ)など。
音楽史でプッチーニのあとに続くのは、ほとんど上演されないオペラを作曲した人でなく、イタリアでならモリコーネ、ニノ・ロータであり、エンタテインメントとしてならアンドルー・ロイド・ウェバー、ジョン・ウィリアムズのほうがよほどしっくりくる。
あるいは、バーンスタインが言ったように、「ビートルズは少なくともシューベルトよりは上」というのもわからなくもない。
あとクラシック音楽好きの学生時代における世間の評価との違いもいろいろ感慨深いものがある。
ワルターの先生みたいな評価だったマーラーが大衆的人気も十分な大作曲家になった。作品では昔は「巨人」が一番人気だったが、「太地の歌」、アダージョが人気の「第五番」の時代を経ていまは「復活」が断然人気曲だ。東京五輪にあわせてベルリン・フィルが新宿御苑で屋外コンサートするといってたが、どうなるのだろうか。ベスト100では「巨人」と「復活」を選んでおいた。「巨人」には若干、個人的な思い入れあり。
それと私はどちらかというと、作曲家でも音楽家でも若いときの曲や演奏が好きな傾向あり。そのあたりは、畏友である小川榮太郎氏が円熟好みなのと少し違うのは、彼の著書である『フルトベングラーとカラヤン』をめぐってネットテレビで議論したことがある。
それから、昔は題名のついた曲が好まれたが、最近はだいぶ、そういうことは減った。モーツァルトの「戴冠式協奏曲」、ブルックナーの「ロマンティック」、などほかの協奏曲や交響曲に題名がないので親しまれていた傾向があったと思う。ハイドンの交響曲では、第88番を選んでおいた。「時計」とか「驚愕」よりこちらがよい(「V字」という名で呼ばれることもあるが)。
また、「小品」への評価は上がったり下がったりだ。昔はSPレコードに入るような小品が人気があり、また、古いものは編曲したりもした。そういうものへの人気は純粋好みの人に嫌われて落ちていたが、NHKの「名曲アルバム」で復活して、最近はまた少し下降気味。
しかし、アルビノーニの「アダージョ」とかヴィターリ「シャコンヌ」など、本当は誰の作曲家であろうがいいものはいいと思う。