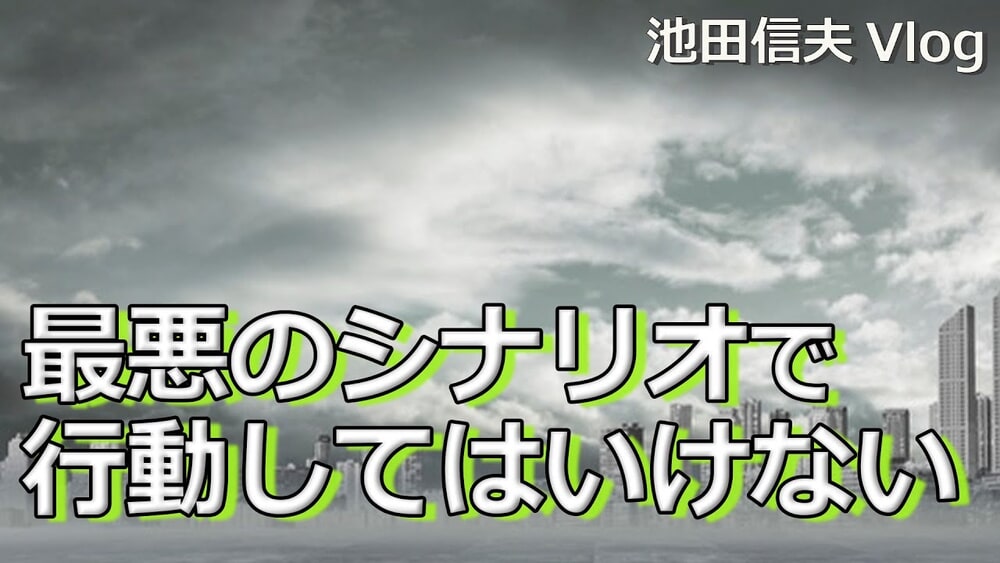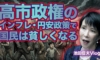中国発新型コロナウイルスの感染防止のため、ここ数週間、ゴミ捨てと新聞取り以外はほとんど家にいて、ネットフリックス(Netflix)で好きな米映画を見る傍ら、コラムを書く日々を過ごしている。
国連報道部からは時たまニュースレターが配信されてくるが、記者会見もここしばらく開催されない様子だ。新型コロナの感染防止のためにウィーンの国連機関でも会合は主にビデオ会議で、職員はホームオフィスで職務をこなしているだけで、外交官や国連職員の活発な動きはまだ見られない。

日本の代表的SF作家、現代の予言者・小松左京(小松左京事務所「株式会社イオ」公式サイトから)
時間があるので家人が以前、知人からもらった月刊誌「文藝春秋」を読みだしたが、とても感動する記事、片山杜秀・慶応義塾大学教授と作家小松左京の次男、小松実盛氏との対談が掲載されていた。タイトルは、「『日本沈没』小松左京の警鐘が蘇る」だ。
断っておくが、当方が読んだ月刊誌「文藝春秋」は2017年11月号だ。2年半前の月刊誌だ。当方が日本を去り、欧州に住んでいる時、日本に小松左京というSF作家が活躍し、日本の国民、世界、人類に向かって様々な警鐘を鳴らしていたことがわかった。
もちろん、小松左京というSF作家の名前は知っていたが、その人物や作品については全く無知だった。小松は大ベストセラーとなった「日本沈没」で有名だが、未来の出来事を予言し、警告を発する「予言者」とも呼ばわれていたことを知った。そして単にカタストロフィーを描くだけではなく、それを通じて日本国民、人類が試練に総力戦で戦い、乗り越えてほしいという思いが込められているというのだ。
片山教授と小松氏の対談を読んでいると、「2017年11月号」ではなく、「2020年5月号」の文藝春秋の記事を読んでいるのではないか、といった錯覚を覚えた。その内容は世界が中国発新型コロナウイルスの侵略に怯えている2020年のことを語っているように思えるからだ。
小松は1977年、「アメリカの壁」でアメリカ・ファーストを唱えるトランプ大統領の出現を予言し、「復活の日」では「新型ウイルスが世界に流行したら」というテーマを描いている。特に、後者は小松自身が2020年の現在に生きていたらびっくりするのではないだろうか。小松は近未来の出来事、危機をリアルに予知し、それを描くことが出来た稀な作家だったわけだ。
対談で心魅かれた部分を少し長いが引用する。小松ファンを自称する片山教授の発言だ。
「小松左京とは『予言者』ではなく、『警醒』の人だと思います。これから起こりうる危機を科学的知識をもとに検証し、それが起こった場合に、人々がとりうる行動を予測する。そして、いざ危機が起こったときに人は、どのように振舞うべきかを常に考えておこうと、警鐘を鳴らし、呼びかけてきました。……小松さんは日本だけではなく人類に『天国』に昇ってほしいと願っていたのですから」
話を2020年5月に戻す。新型コロナウイルスで多くの犠牲者が出た欧州では5月に入り、感染者数がピークアウトした国は封鎖を段階的に解除し、国民の夏季休暇を救済するためにさまざまな対策に乗り出してきた。欧州メディアの中には「ポスト・コロナ」という表現も現れ、「日常生活への段階的復帰」がテーマとなってきた。
小松が生きていたならば、「人類は次のウイルスの侵略に備え、地球規模の準備態勢を敷くべきだ」と警告を発したのではないか。残念ながら、世界の主要国家間でワクチン製造での独占権争いが展開されてきているからだ。
小松は人類の危機に対して「総力戦」、「全力戦」という表現を好んで使ったという。地球の危機に直面した人類が生き延びていくためは民族、国家の壁を越え総力戦で臨まなければ勝てないことを知っていたわけだ。
喉元過ぎれば熱さを忘れる、であってはならない。危機から学び、次の危機に対応する準備が欠かせられない。小松はSFという書割を通じて、ポスト危機の生き方を自然災害の大国・日本の読者に伝えたかったのだろう。
新型コロナの感染ピークは過ぎようとしているかもしれないが、人類はそこから教訓を引き出すべきだろう。感染の第2波、第3波を恐れるからではない。もっと悪質なウイルスが人類を襲撃するかもしれないからだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2020年5月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。