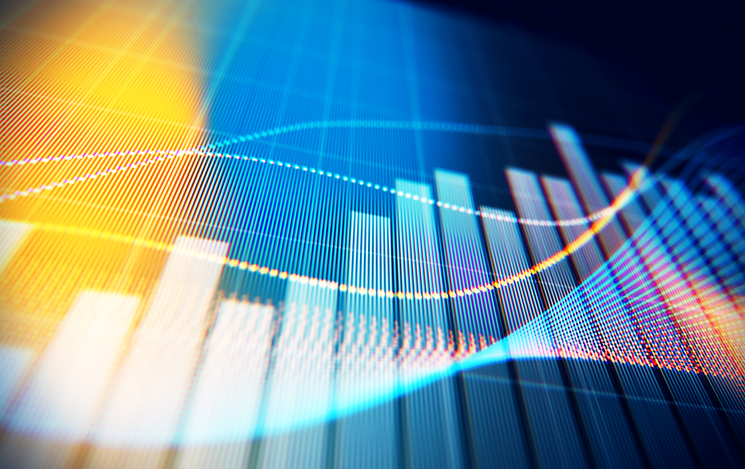MicroStockHub/istock
昨年は世界がコロナに翻弄された年になりました。NYがロックダウンになった3月以降、僕も年末までにマンハッタンのオフィスに出社したのは10回に満たなかったかもしれません。以前は当たり前に日米を往復できたのが、今では昔話のようです。いつもなら年間で日米を5~6往復、米国内出張も10~20回程度こなすのですが、昨年は日本に行ったのは1月と9月の2回だけで、米国内出張もコロナ前の数えるほどでした。
個人的には、昨年8月でちょうど米国滞在満20年ということになったのですが、日米をブリッジする仕事柄、時差の関係で20年前から基本的にリモートワークにならざるを得なかったことが今回のコロナでは幸いし、今ちょうど決算の数字を見ているのですが、思ったほど大きな打撃を受けずに乗り切れそうです。しかし、今やNYから普通に企業研修やカンファレンスでパネルディスカッションを行ったり、大学の講義を行うことができるようになりました。こんなこと、子供の頃はSFの世界の話でしたよね。
技術的に可能であることと、社会がそれに適応することは全く別物だと思いますが、コロナ禍が未来の先取り的に技術の適用を早めたと言えそうです。社会がようやく技術に追い付いてきた。今思えば、何であんなに苦しい思いをしてまで満員電車に詰め込まれていたんだろうなんて思っている人も少なくないのではないでしょうか。
コロナで自宅にいる時間が増え、また図らずも在米20年という節目を迎えたこともあり、仕事や人生を立ち止まって見つめなおす時間が持てました。その中で、自分の人生に一定の法則性というか、共通の原理のようなものが見つかりました。それが「自由」と「デタッチメント」です。どうもこの2つが僕の人生の大きなテーマになっているようなのです。
僕の人生にとって「自由」という価値観が非常に重要な意味を持っているのですが、それを理解し、実現するには「デタッチ」することが必要だったようです。他人事のような書き方になってしまうのは、意図的に「デタッチしよう」と思って行動を起こしたわけではなく、結果的にそうなっていたことが今になって薄っすらと分かってきたからです。
母性的な社会である日本では、アタッチメントがとても強く、昔から受験勉強とか就職活動とか、人生の重要な局面で顔をのぞかせる同調圧力が苦手でした。高校生の時にリゲインのCMを見て牛若丸三郎太のような世界を股にかけるビジネスマンに憧れ、大学生の時に白洲次郎の著作を読んでカントリージェントルマンという生き方に惹かれたのは、自分の人間としての基本的な性質に自由や独立を志向する抑えられない何かがあったからなのかもしれません。
一橋大学を受験したのも、コンサル会社を選んだのも、外資系企業に進んだのも、アメリカに留学したのも、起業して個人ベースで米国を拠点に仕事をしているのも、今なら自分の中で全てデタッチメントの文脈として理解しなおすことができます。大学時代、母性原理の強力な遂行集団としての体育会に所属しながら、米国の父性原理をルールの基にするアメリカンフットボールを体験できたのも、また社会人になって外資系コンサルの東京事務所で成果主義と長時間労働がミックスしたハードワークを叩きこまれたのも、和洋折衷という意味で、自分の人生の離陸に向けた助走期間だったのかもしれません。
今思えば、これらの意思決定に影響を与えた親や知人などの人間関係も含めて、全てが巧妙にアレンジされていたように感じます。丑年生まれの私は、今年は年男なのですが、50歳を目前にして、人生の折り返し地点を過ぎたことを実感しつつ、今後自分の人生をどう着地させるべきか(つまり、どのような形で死に向かっていくべきか)、そろそろ考え始めてもよい時期に来ているのかなと感じます。
僕が著作を愛読する河合隼雄氏によれば、デタッチメントを求めて出て行った人は、最終的にはアタッチメントを求めて戻ってくるとも言います。今後の自分の人生で、デタッチメントの文脈がアタッチメントに変化していくのかどうか、自分の中ではまだよく分かりません。しかし、アメリカに長くいればいるほど、自我の確立を強く求められる米国社会で日本人としてのアイデンティティを考えないわけにはいかず、アタッチメントがこれからの人生のキーワードになってくる予感はあります。
ところで、話は変わりますが、年末ふと本棚で目に留まった村上春樹氏の「アンダーグラウンド」と「約束された場所で」をパラパラめくって読み進めていたら止まらなくなってしまいました(両者は地下鉄サリン事件を題材にしたノンフィクションで、前者は事件の被害者、後者は加害者側のオウム真理教信者にインタビューを行ったもの)。このタイミングでこれらの著作を読み返そうと思ったのはまさにシンクロニシティとしか言いようがないですが、読み進めて行くうちに、麻原彰晃とトランプのリーダーシップや、オウム真理教信者とトランプ支持者のフォロワーシップが極めてよく似ていることに気づき、驚愕しました。

ホワイトハウス公式サイトより:編集部
麻原とトランプのリーダーシップに共通するのは、我々が基本的ルールとして受け入れて暮らしている資本主義が救えなかった人々に救済ストーリーを提供している点です。麻原は資本主義のルール自体に馴染めなかった人々を、トランプは資本主義を受け入れたものの、結果的に敗者となった人々を相手にしている点で、若干対象となった人々の社会的レイヤーは異なると思いますが、本質は似ています。また、麻原とトランプが提供したストーリーは非常に稚拙で荒唐無稽なものでしたが、それに代わる(彼らにとって説得力のある)救済ストーリーを他の誰も提供できなかった点も似ています。
またフォロワーシップにおいては、自我を全て“教祖様”に預けてしまい、自分で考えること自体を放棄してしまうという点も共通しています。麻原は絶対帰依を、トランプはロイヤリティ(忠誠)を支持者に求めます。時代の変わり目にはこういう自己愛性の強い人物による自己陶酔型の振る舞いが、一定の層からは強いリーダーに見えてしまうのかもしれません。
これは村上春樹氏も指摘していることですが、麻原という悪が生み出された一因は、資本主義というシステムに馴染めなかった人々に対しての救いのストーリーを、現在の社会が持っていなかったからではないでしょうか(もちろん、だからといってオウム真理教が行ったテロ行為が正当化されるわけでは当然ありませんが)。米国でトランプの支持拡大を目の当たりにしている自分としては非常に説得力のある仮説です。選挙で敗れたとはいえ、全米で7000万人以上、白人の実に58%がトランプを支持したという事実は、心底恐ろしいものがあります(トランプ支持者がテロを起こさないことを祈るばかりです)。これは、「あちら側」の問題のように見えて、実は「こちら側」の問題なのかもしれません。村上氏のいう“合わせ鏡”なのです。
閑話休題。日本は戦後の産業立国によって発展し、「いつかはクラウン」と国民に幸福ストーリーを提供してきましたが、今やそのストーリーが破綻しているのは誰の目にも明らかでしょう。人口が減り、高齢者比率が高まる国で、モノの豊かさで幸福を感じる生き方は説得力を失っています。「モノからコト」が重視されるようになってきたとはいえ、今もなお製造業による産業立国を前提とした均質的な人材育成(受験勉強)が学校教育の中心となっています。
資本主義がゲームのルールである社会に暮らしている以上、資本主義への適応を求められるのは仕方がありませんが、人生の価値が資本主義への適応度により判定されてしまうような風潮は明らかに行き過ぎでしょう。別に仕事で成功した人が偉いわけではありません。仕事は人生を豊かにする手段ですが、目的ではありません。これは自戒したいです。
今求められているのは、資本主義を補償し、バランスする幸福ストーリーではないかと思います。誤解を恐れずに言えば、宗教のない日本では、特にここが非常に弱いです。これからの日本では、人間の本質的・個別的幸福を追求する拠り所として「宗教」に相当する何らかの存在が必要になるのではないでしょうか。これからの時代を幸せに生きるために日本人全員で考えて行かなければならないチャレンジだと思いますが、その中でスポーツが果たせる役割も少なくないのではないかと思っています。
日本は欧米の上澄みだけをすくって西洋化を進めたため、(「赤信号みんなで渡れば怖くない」的な母性的強さはありますが)個人的・宗教的信念に根差した父性的強さが個人に欠けており、個人が社会システムの中に埋没してしまっているように見えます。平時にはこれが強さになりますが、有事にはこれが弱さになります。20年アメリカに住んでいる僕が断言しますが、欧米の後を追いかけるだけでは日本人は幸せにはなれません。独自の幸福への道を模索しなければなりません。
何だか話が大きくなってしまいましたが、強さを支えるのは、「自由」であり「好き」「喜び」という感性だと思います。「場」に配慮して「好き」を殺すのが美徳とされる日本では、「好き」を追い求めるには必要以上の「強さ」が必要になります。
「好き」「喜び」をもっと純粋に追及してもいいのではないでしょうか。そういう生き方を応援したいです。スポーツはそのための有効なツールになりうるのではないかと思います。
今年もまだ見ぬ同志との出会いを楽しみにしています。
編集部より:この記事は、在米スポーツマーケティングコンサルタント、鈴木友也氏のブログ「スポーツビジネス from NY」2020年1月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はスポーツビジネス from NYをご覧ください。