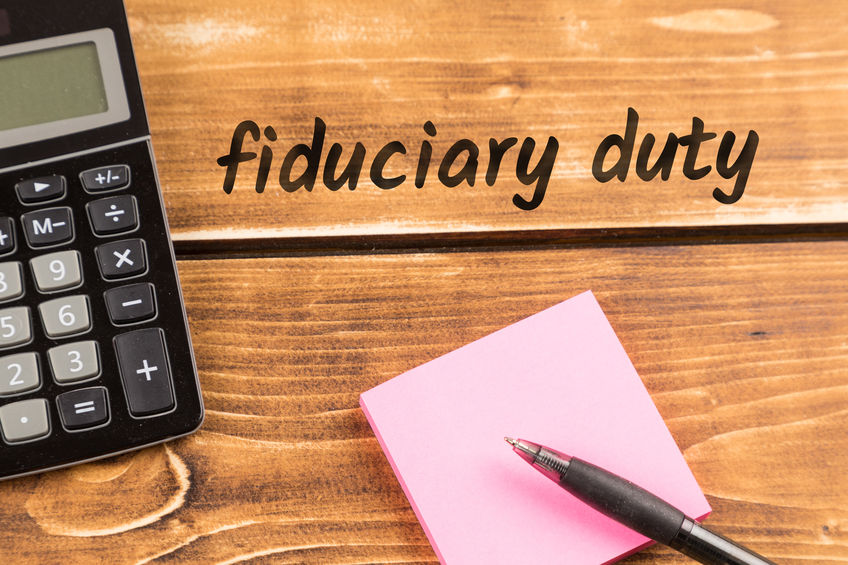金融庁の行政手法は、近時、抜本的に改革されたのだが、なかでも秀逸なのは、大きな言葉の巧みな使用である。代表例は、大成功を収めたフィデューシャリー・デューティーであり、それを広義化した顧客本位や、顧客との共通価値の創造、あるいは、少し前のものでは、事業性評価などである。
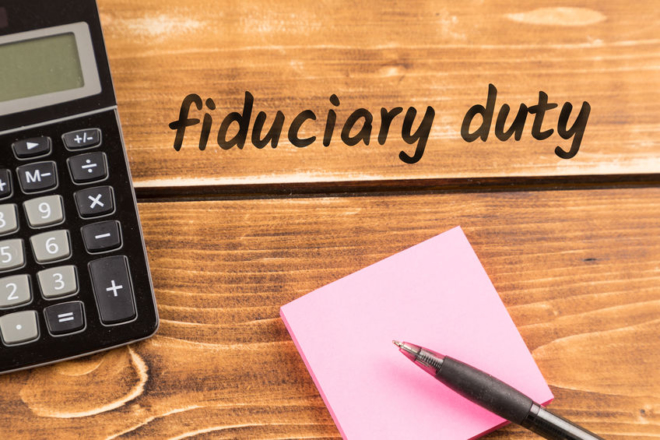
123RF
これらの言葉に共通していえるのは、どれも抽象的で具体的な意味がわかりにくいことである。わかりにくいわりには、非常に深遠な意味が籠められていることを予感させる。故に、足元の小さな利益にばかり気をとられ、また、表層的なルール遵守の徹底のなかで、ルールの意味を没却してきた金融機関に対して、施策として強い効果を発揮したのである。つまり、金融機関に意味を考えさせたということである。
金融庁は、ルールからプリンシプルという名のもとで、金融庁が定めたルールの履行を金融機関に強制する手法を放棄して、金融機関が自分自身に自主ルールを課す自律原則、すなわち、プリンシプルに転換している。このプリンシプルのもとでは、例えば、フィデューシャリー・デューティーという具体的内容のないものがでてくると、金融機関は、その意味を自分の頭で理解して、自分自身の行動規範として具現化しなければならなくなる。
ルールならば、その通りに遵守すればいいので、金融機関は、体を使いこそすれ、頭を使わない。故に、金融機関はルール遵守で馬鹿になりつつあったのである。そこで、金融庁は、路線転換し、考えさせるようにしたわけである。実際、理念だけのフィデューシャリー・デューティーは、空虚で大きな言葉だからこそ、金融機関自身が具体的な内容を充填しなければならないように強制力が働いたのである。
金融庁は、同時に、例えば、フィデューシャリー・デューティーについては、投資信託の販売と運用に関して、金融庁が問題視する事例を極めて厳しい口調で指摘していて、こうした指摘のもとでは、金融機関は、金融庁が本来あるべきであると考えているものを容易に想像できる。
従来のルールによる手法のもとでは、金融庁があるべきと考えるものがルール化されて提示されていたが、プリンシプルによる手法のもとでは、フィデューシャリー・デューティーのような大きな言葉で指導理念的なものが謳われると同時に、金融庁があるべきではないと考えるものが具体的に提示され、金融機関自身が自分のあるべき姿を考えて自律的な規範に具現化するのである。
そして、事実として、フィデューシャリー・デューティーに限らず、ここ数年にわたって金融庁が用いてきた大きな言葉は、金融機関自身の手によって内容の充実が図られ、自律的な規範として定着しつつある。もちろん、金融機関の数は多いので、取り組みの進展度に大きな開きがあるにしても、金融庁の意図したことは着実に成果を生みつつある。
森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
HC公式ウェブサイト:fromHC
twitter:nmorimoto_HC
facebook:森本 紀行