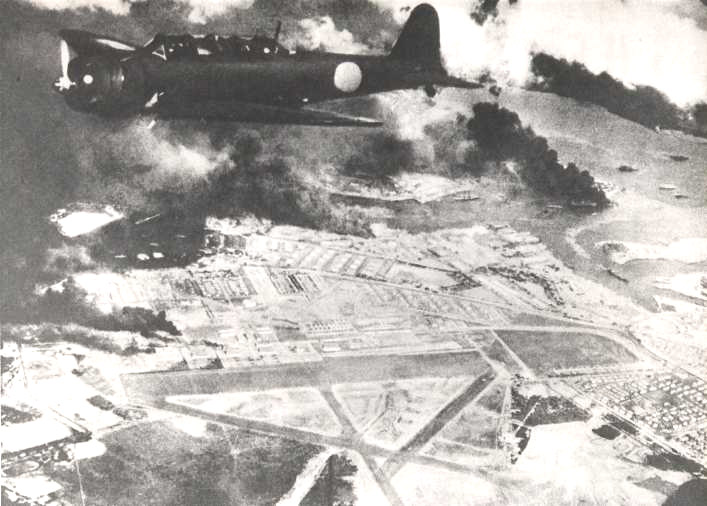私が私淑する明治の知の巨人・安岡正篤先生曰く、「学問というものは現実から遊離したものは駄目であって、どうしても自分の身につけて、足が地を離れぬように、その学問、その思想をもって自分の性格を作り、これを自分の環境に及ぼしてゆくという実践性がなければ活学ではない」ということです。
また先生は、南北朝時代の臨済宗の僧である虎関師錬禅師の言葉、「古教照心・心照古教」を挙げられて、「古教・心を照らすことはまだ行うことができる。心・古教を照らすに到って、真の活学というべきだ」とも述べておられます。「心が照らされるのではなくて、心がすべてを照らしてゆくような学問」が大切だと言われるのです。
そしてその為には、「自分が主になって、今まで読んだものを再び読んでみる。今度は自分の方が本を読む」ことだとされています。例えば「人間、いかに生きるべきか」を教える実学・活学の真髄ともいうべき書、『論語』を読んで問題意識を持ち、それを哲学的・科学的また体験等によって実証して行くことです。そこまでして漸く生きた学問、活学になるというのです。
要するに活学、学問が活きるとは、結局は主体性を持ち実践に移すということに繋がっており、言わば陽明学の祖・王陽明の言、「知は行の始めなり。行は知の成るなり」(『伝習録』)そのものであります。行を通じ、知で得たものを自分の血となり肉となるようして行くということです。
実践を伴わない学問には意味がありません。学んだ事柄を自分自身の生活において知行合一的に実践し、更に磨きを掛けなければ駄目なのです。学びを自分の方へと引き寄せて考えて見、自分の心の中でよく咀嚼し理解し血肉化させて、日常の中で活かして行くのです。これ正に活学というものであり、之が事上磨錬というものであります。
安岡先生は『人生の大則』の中で、次の通り述べておられます--儒教にしても仏教にしても道教にしても、神道にしても、そういう祖先以来の法蔵・道源をさぐれば限りなくある。ただしそれが何人かの熱烈な内面生活を通じて初めて生きてくるのであって、個人個人の魂を通ぜざるかぎり、人格を経由せざるかぎり、いかなる学問も信仰も、それは山の中にある原鉱石や、地中に埋もれておる木の根と同じである。
学問や信仰というものは個人の魂、個人の人格を通じて発してくるものでなければならないのです。魂から発するような活学をする為には、色々な体験・経験を経なくてはなりません。『論語』一つを読むにしても、体験や経験を積む程に言葉の深い意味が少しずつ理解出来るようなって行きます。勿論、知識も蔑ろには出来ません。そういうベーシックなものの上に、体験・経験を積み上げて行くような理解の仕方が大切だと私は思います。
編集部より:この記事は、北尾吉孝氏のブログ「北尾吉孝日記」2021年12月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。